今回はLunacyの「BEAM」について書いていこうと思います。
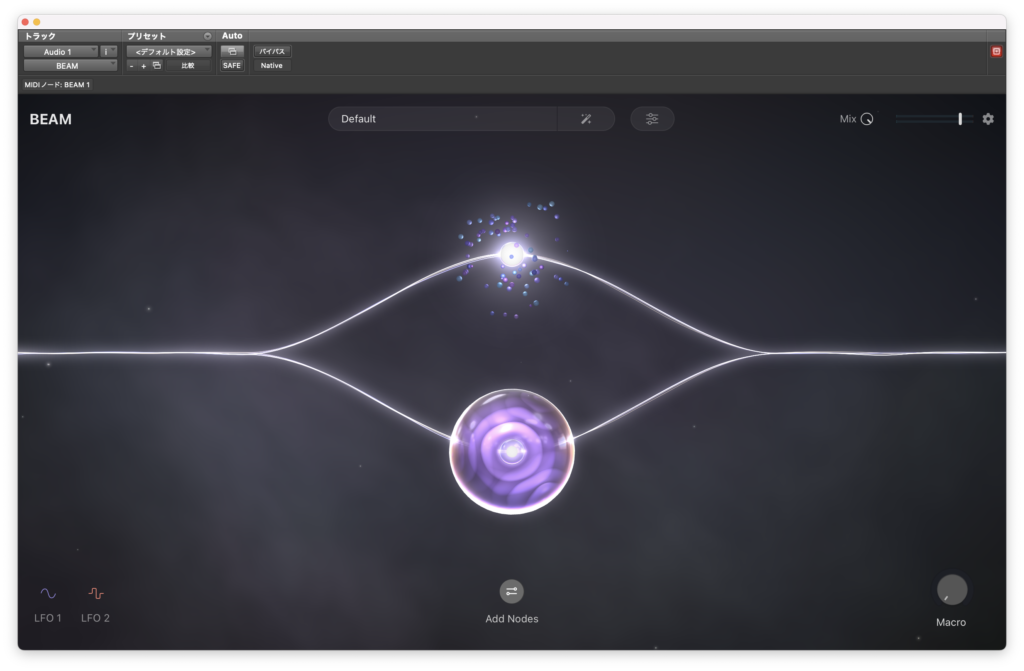
BEAM
神秘的で美しいUIが目を引くプラグインですね。
中身はSpace(リバーブのようなもの)とGrain(ピッチシフターとディレイを複合したもの)とフィルターをルーティングできるものとなっています。
とりあえずみていきましょう。今回のバイパス↓
デフォルトだとこんな感じ↓
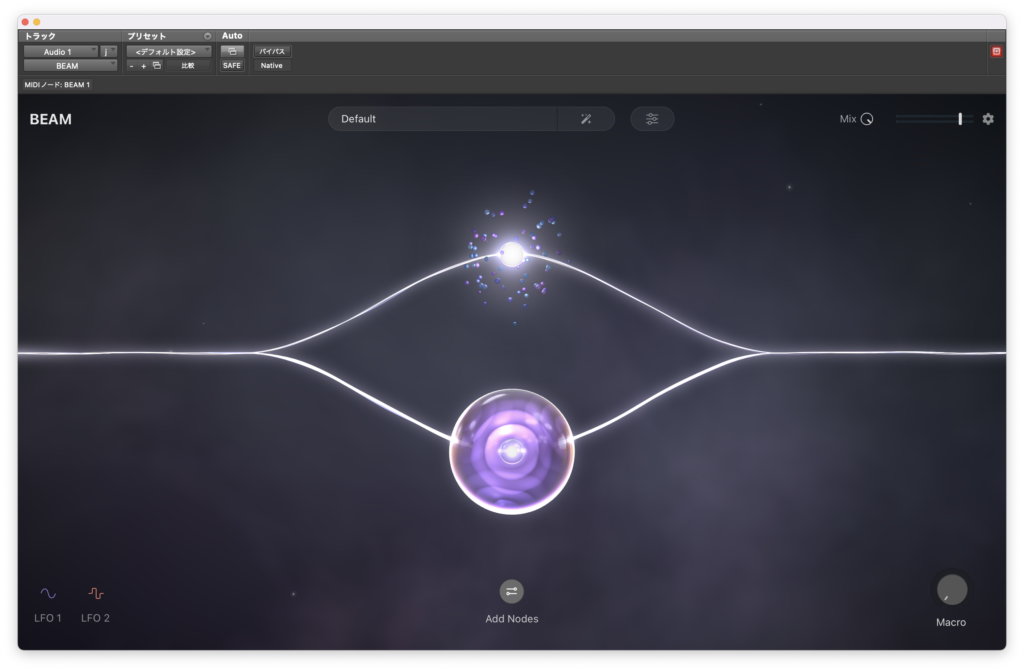
具体的には、下のAdd Nodesをクリックしてドラッグすると配置ができます。
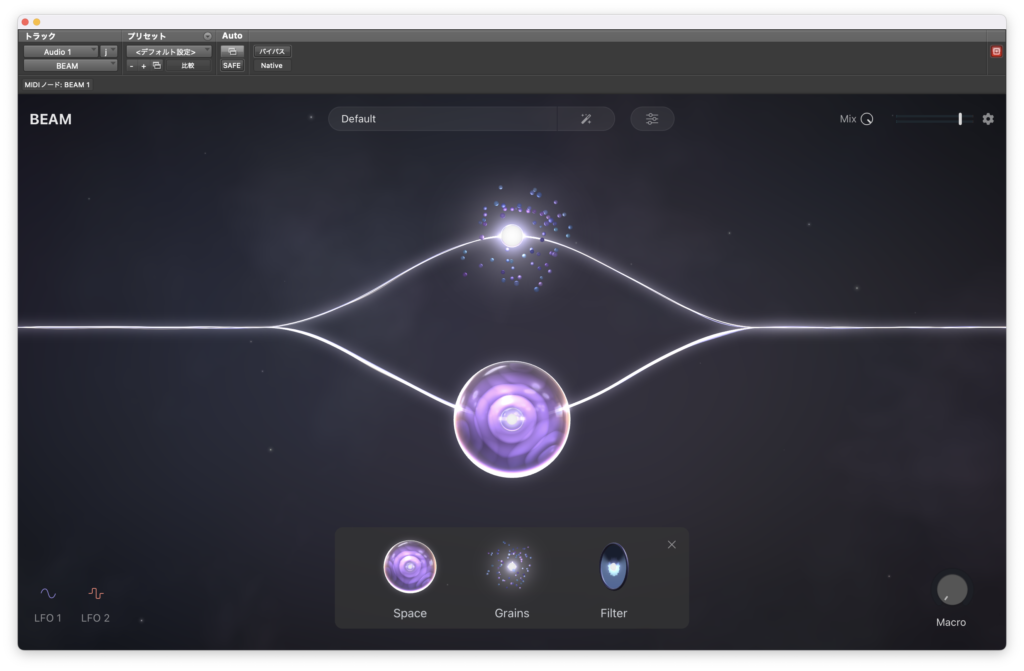
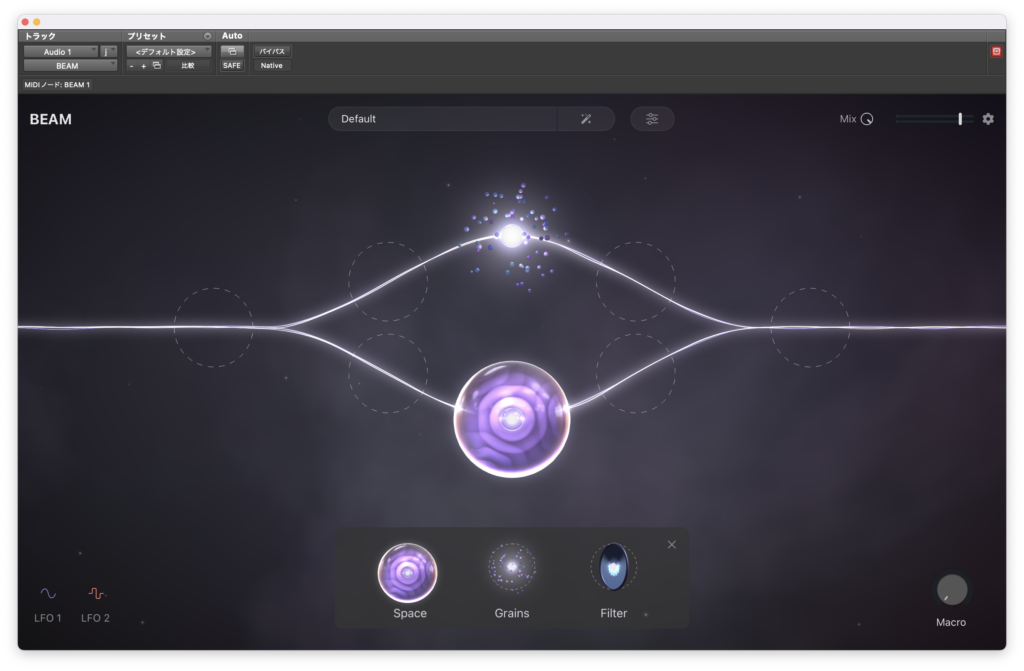
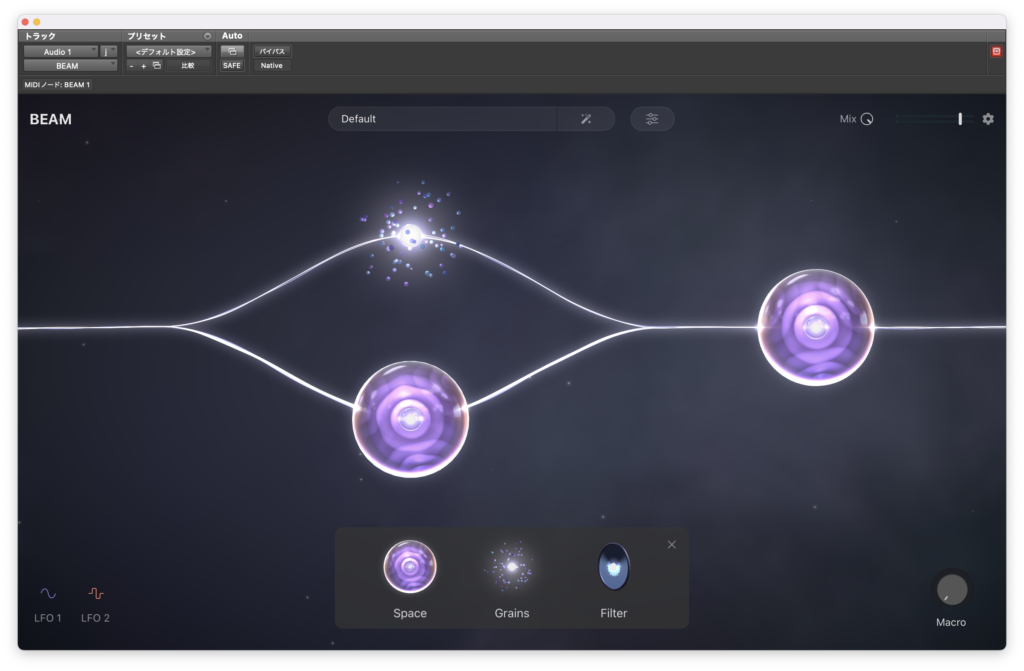
並列につなぐポイントを増やすには、分岐させたいところにカーソルを合わせてドラッグを行います。
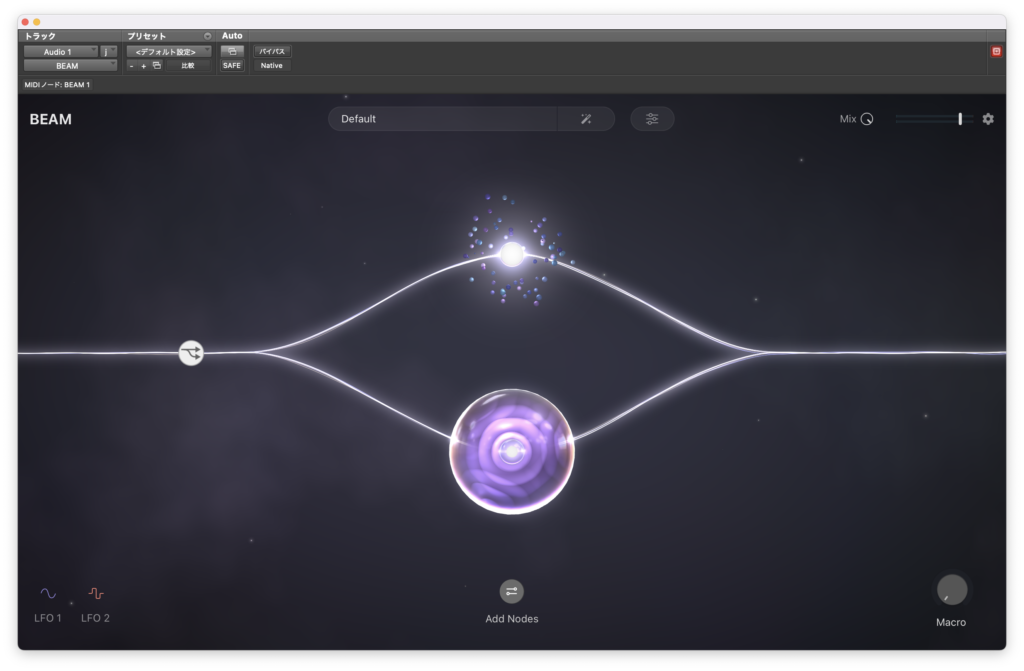
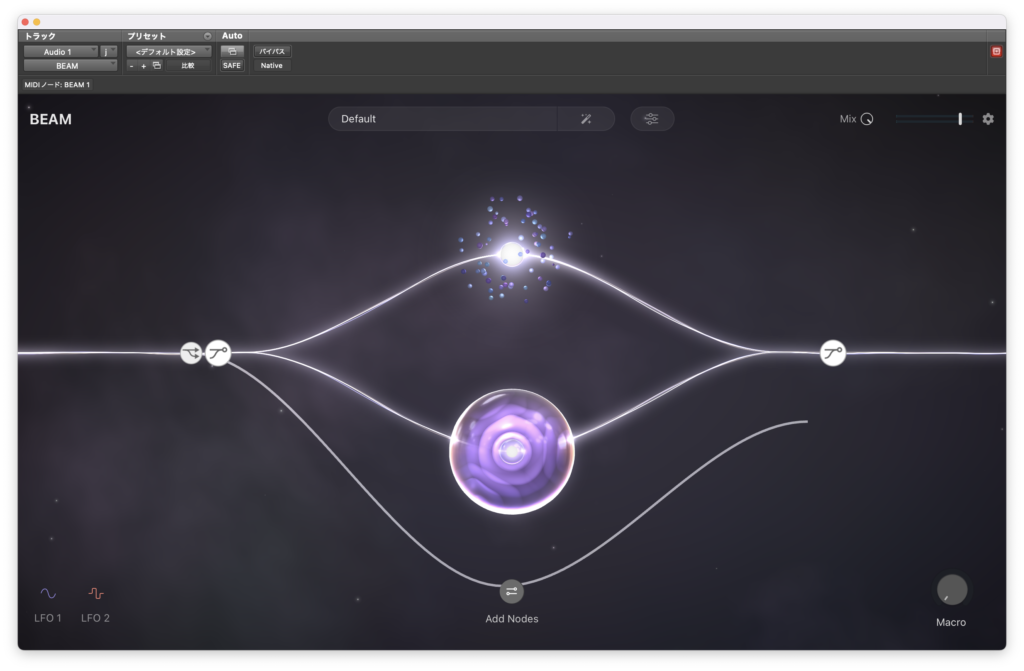
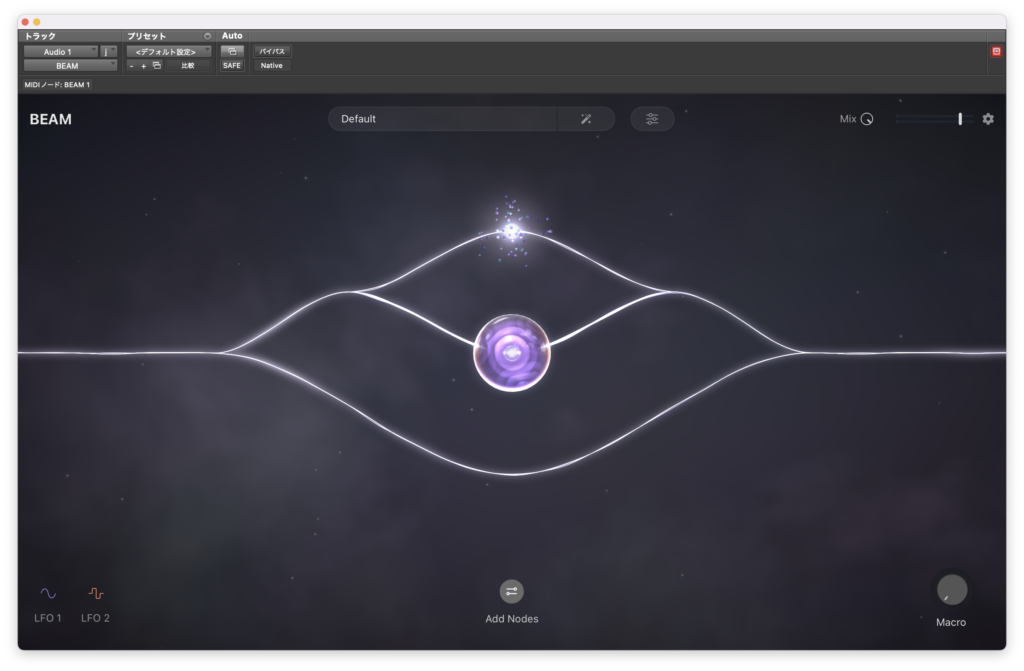
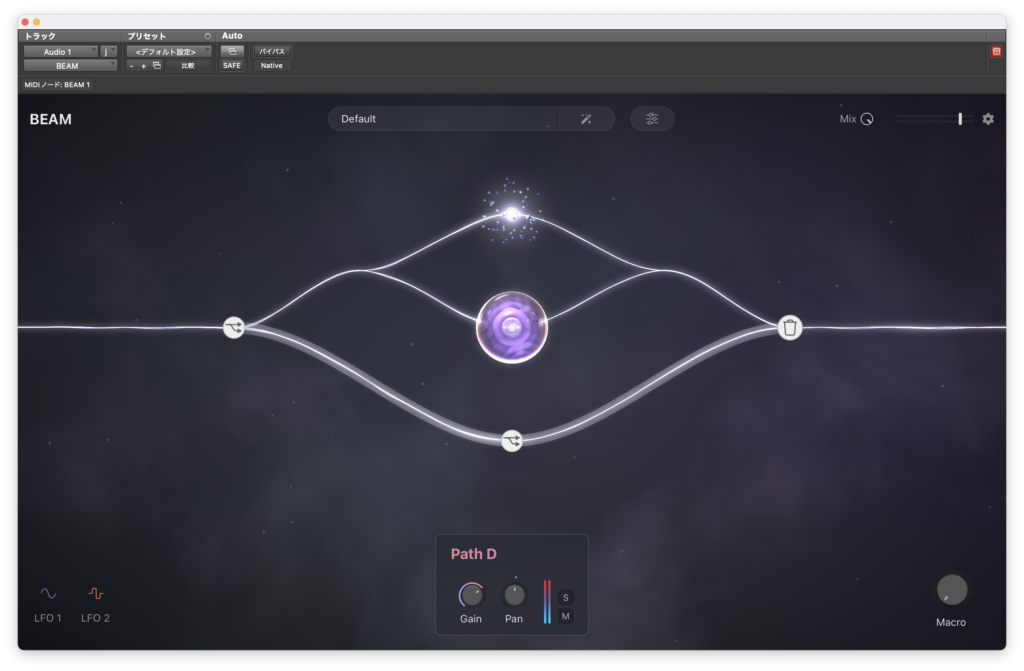
まずはSpace、Grains、Filterを一つずつみていきましょう。
Space
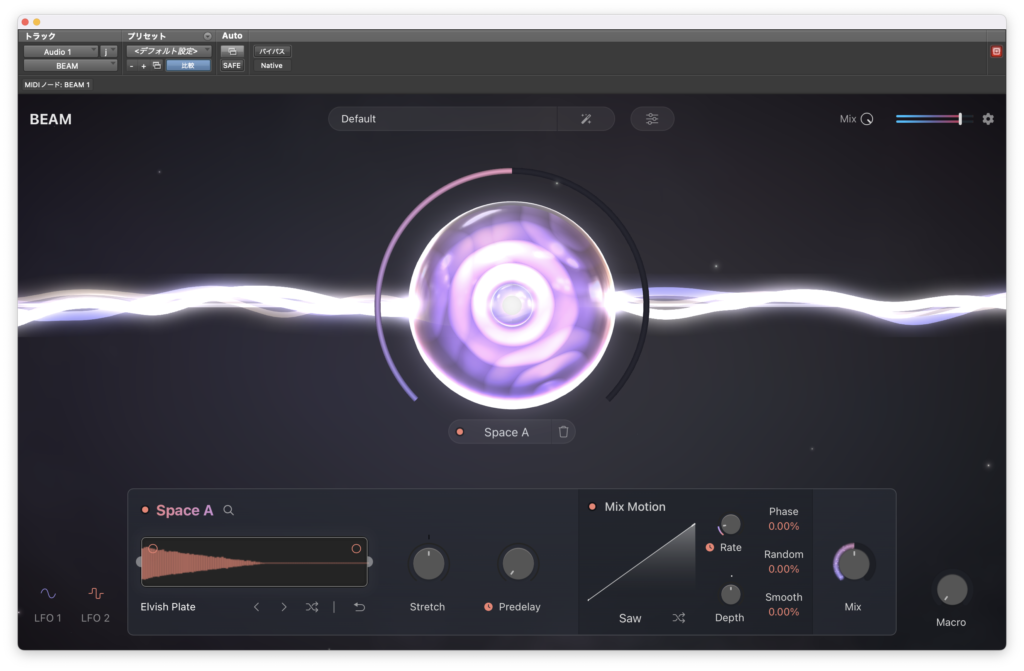
まず左下でリバーブの種類を決めるのですが、これがかなりたくさんのものが用意されています。
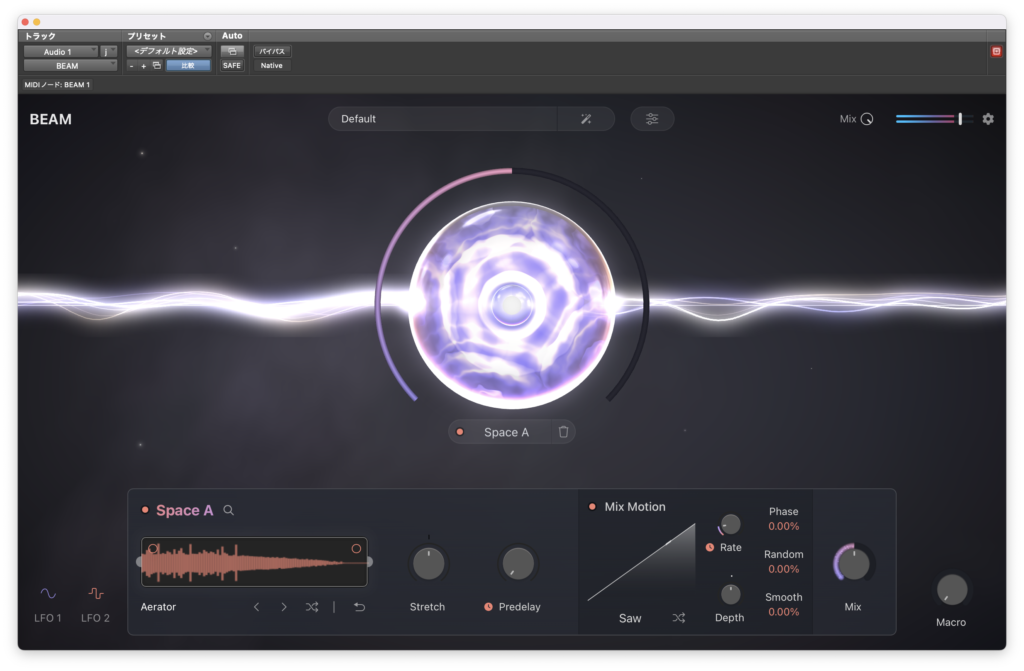
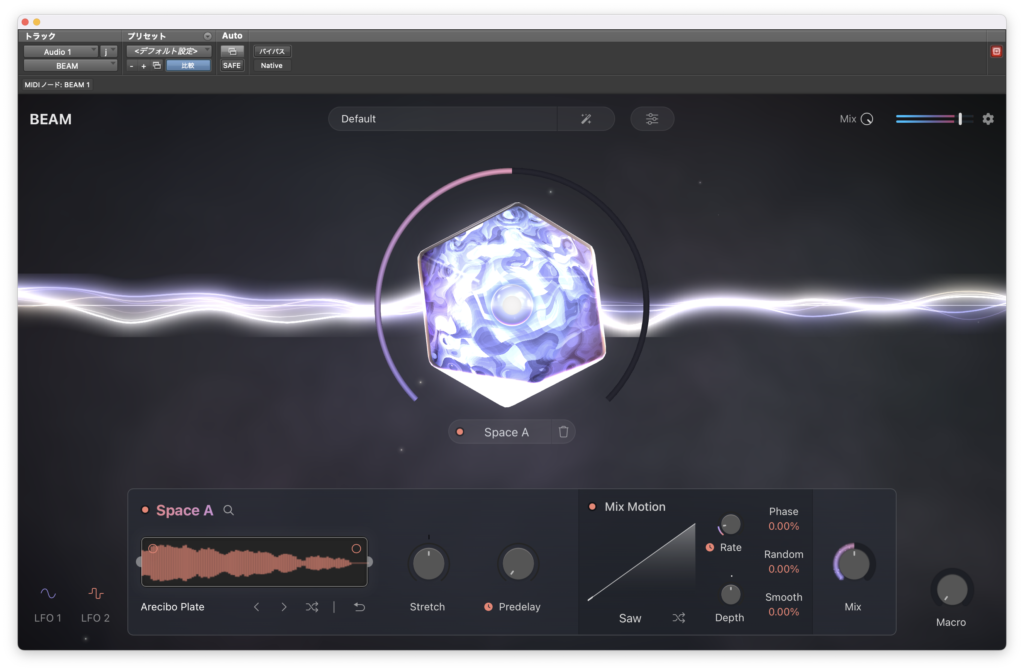
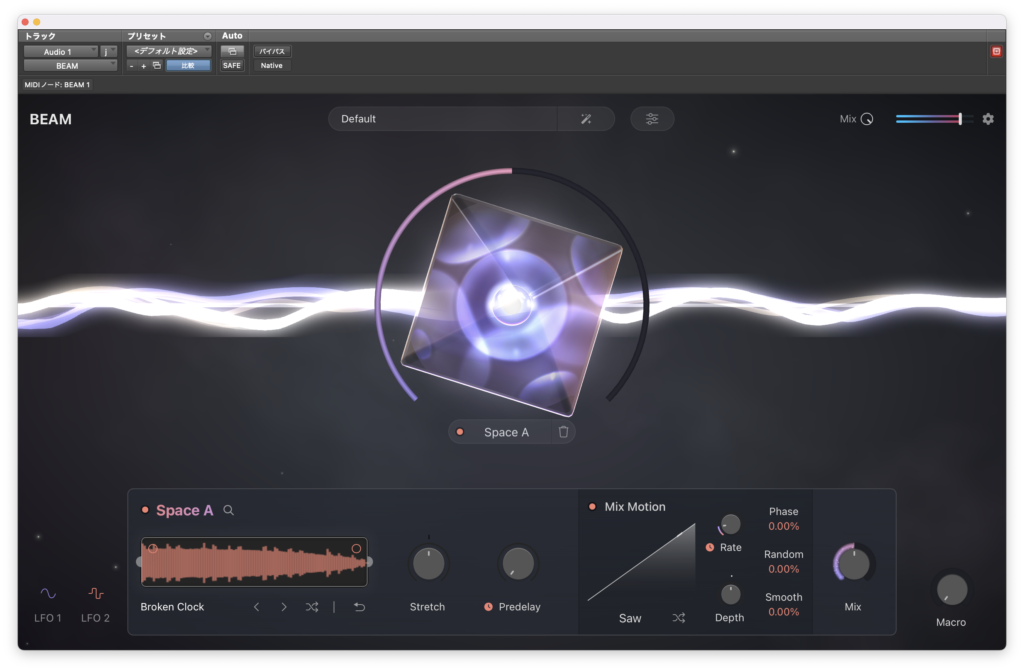
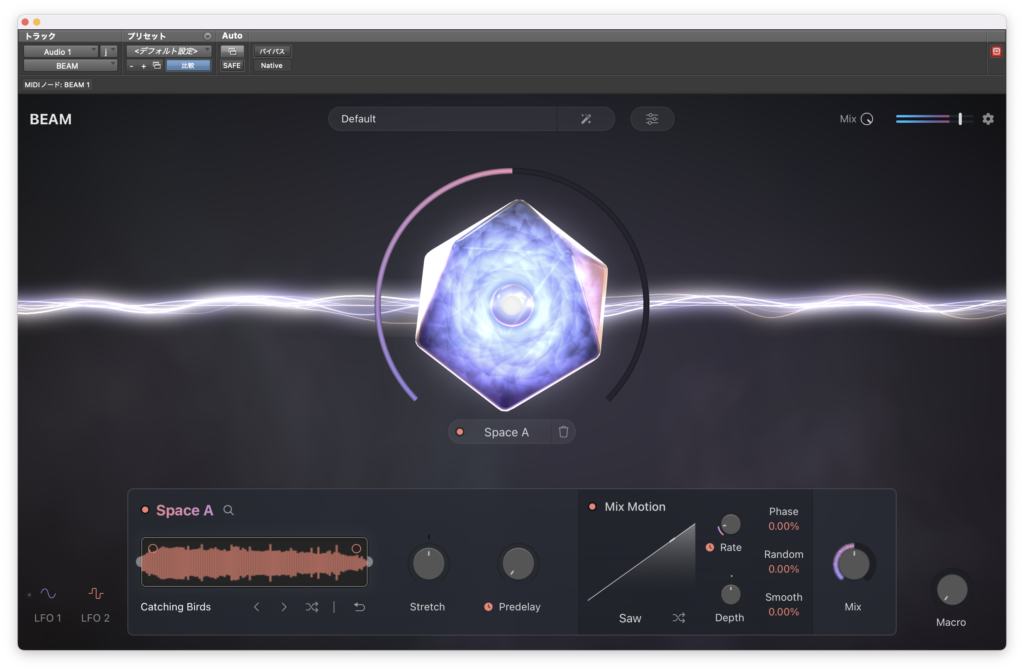
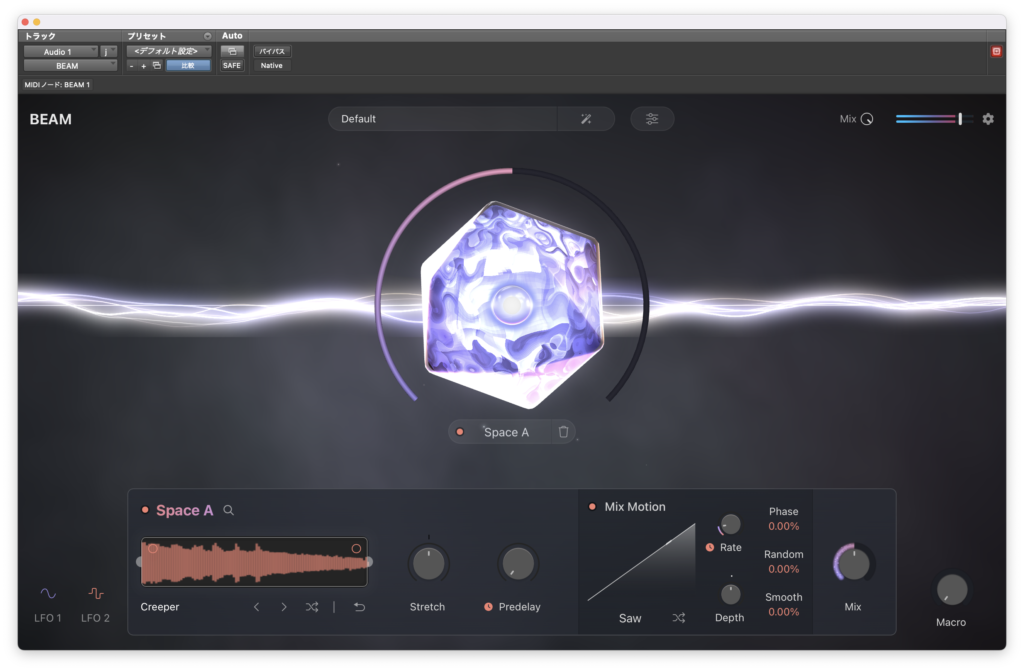
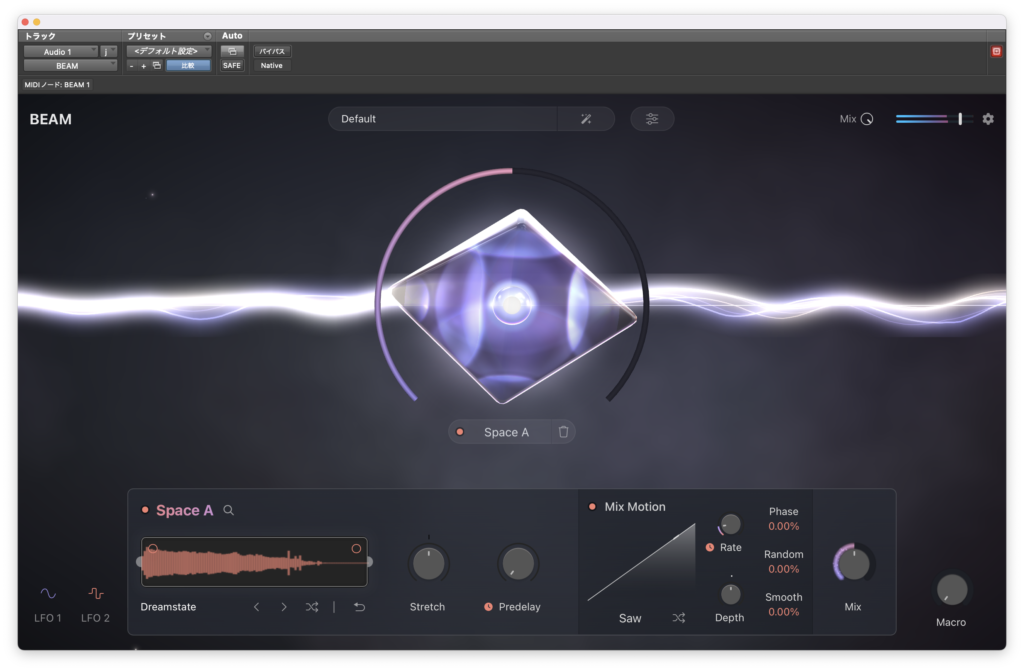
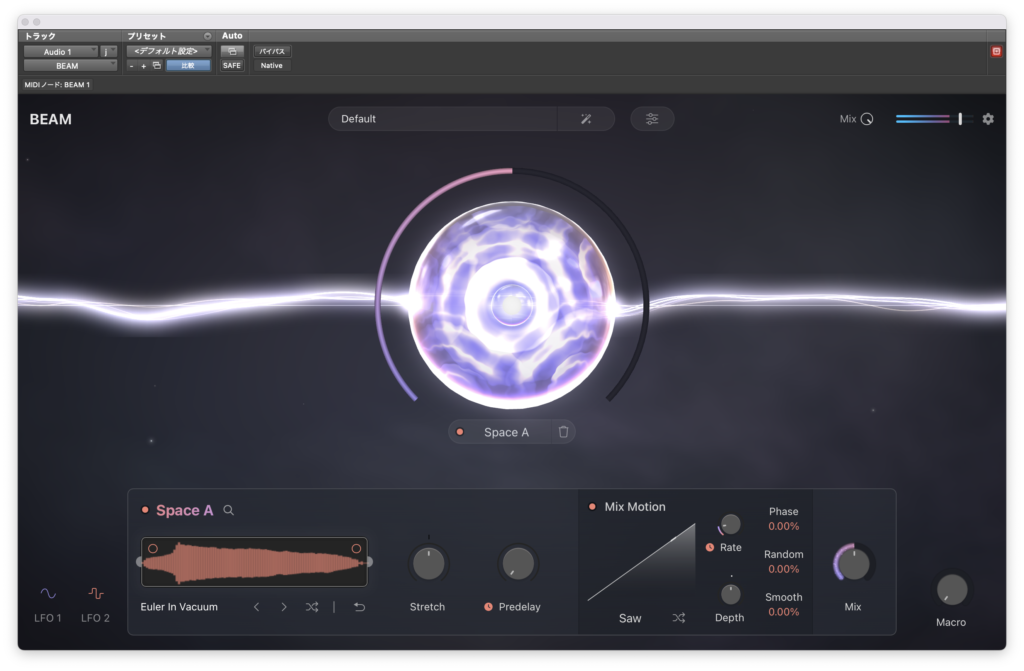
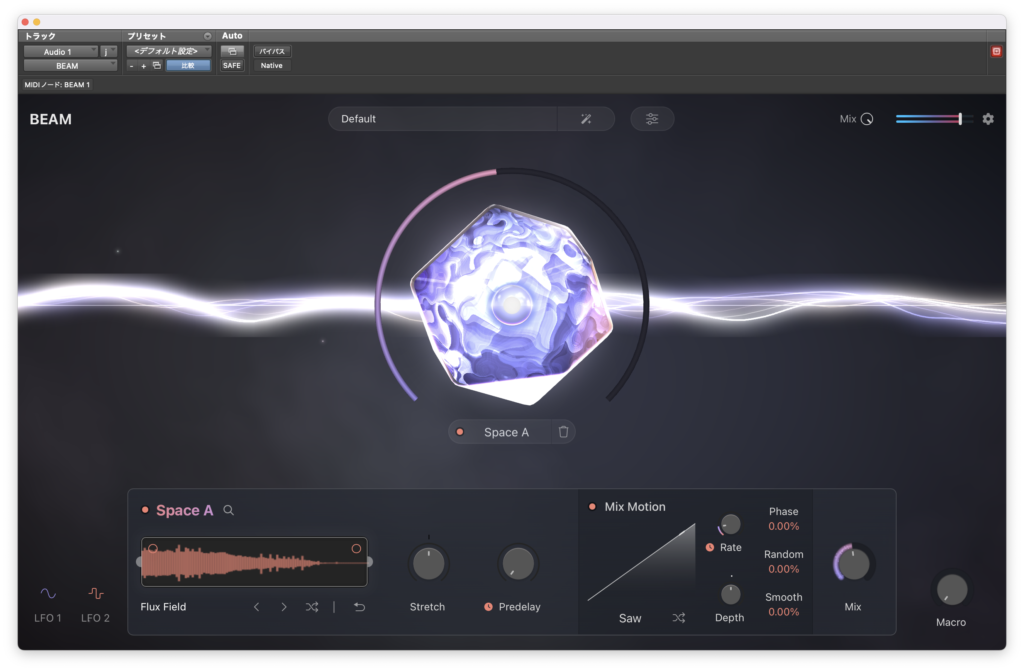
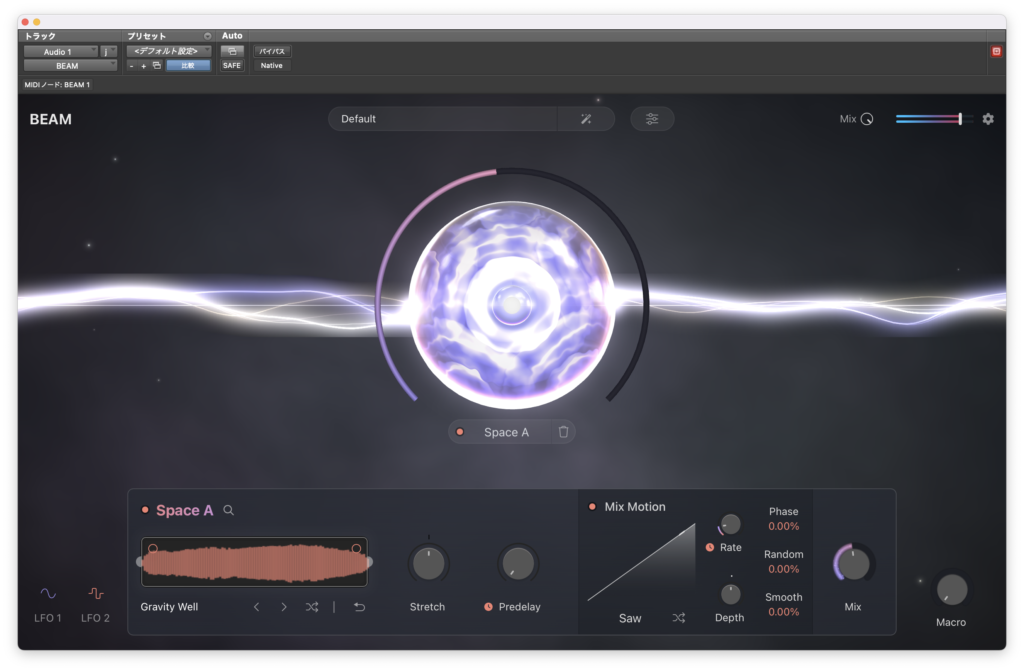
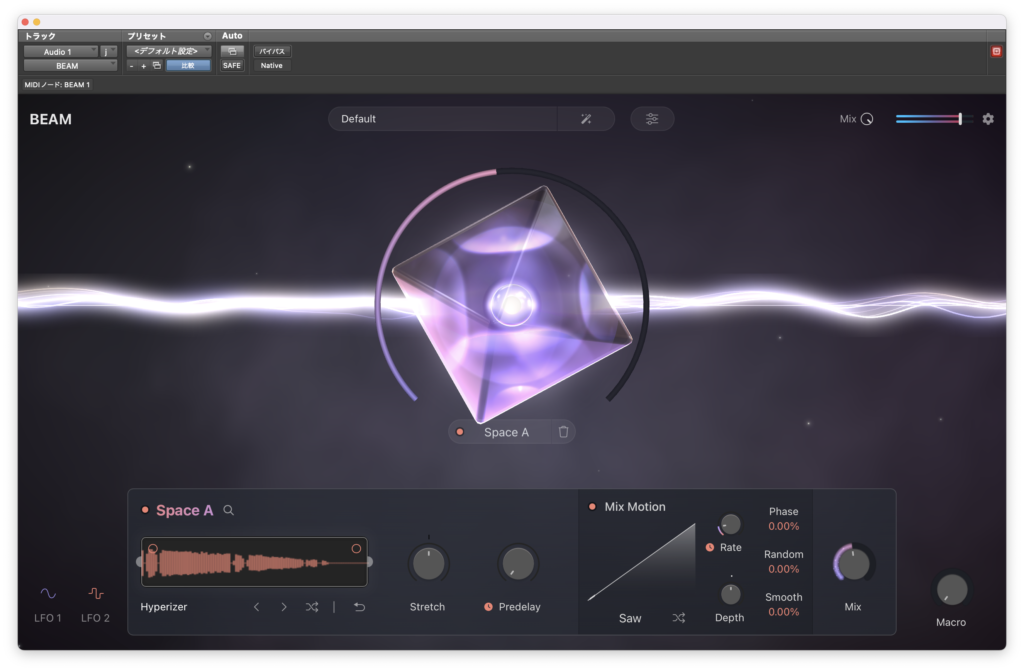
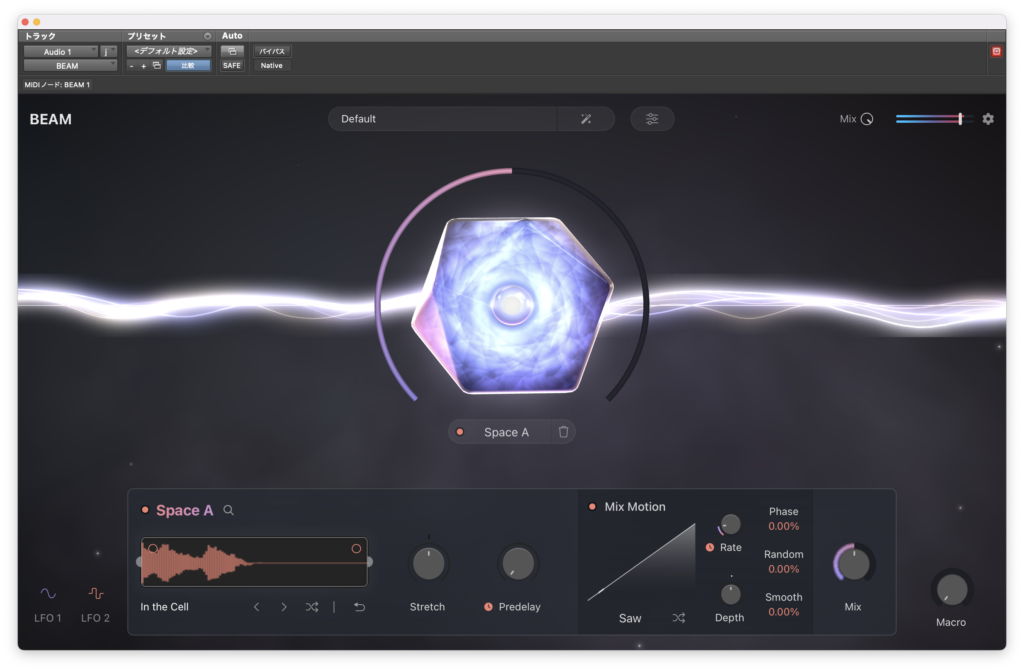
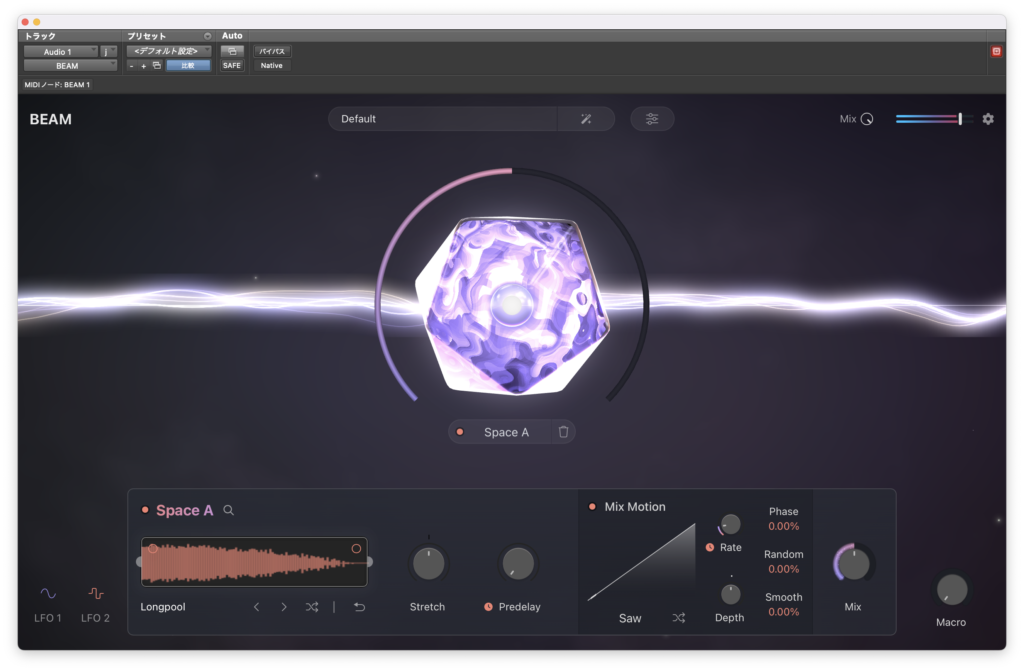
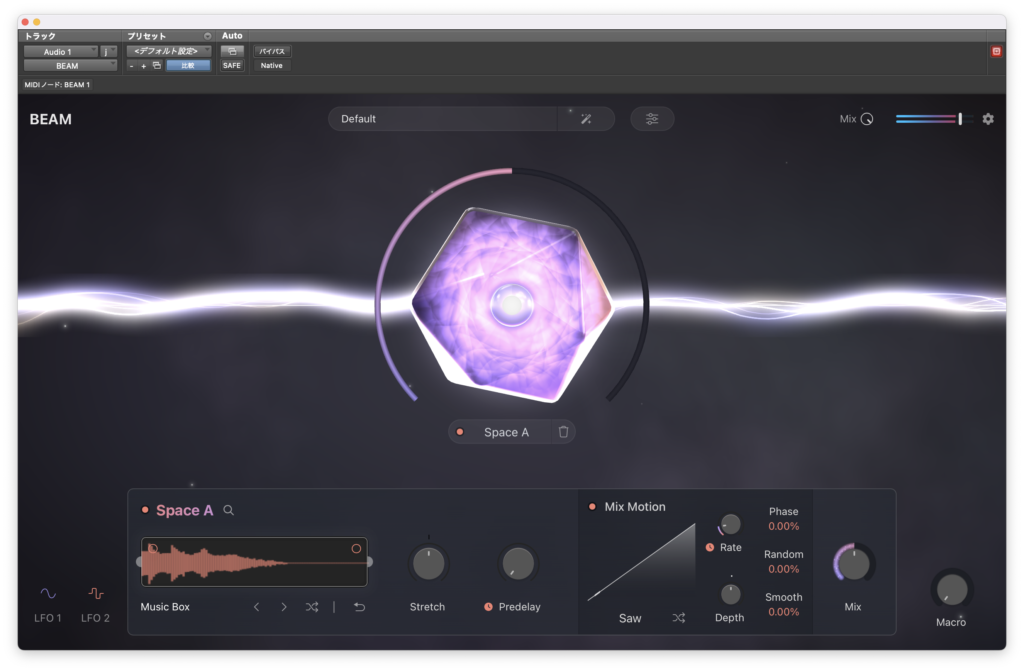
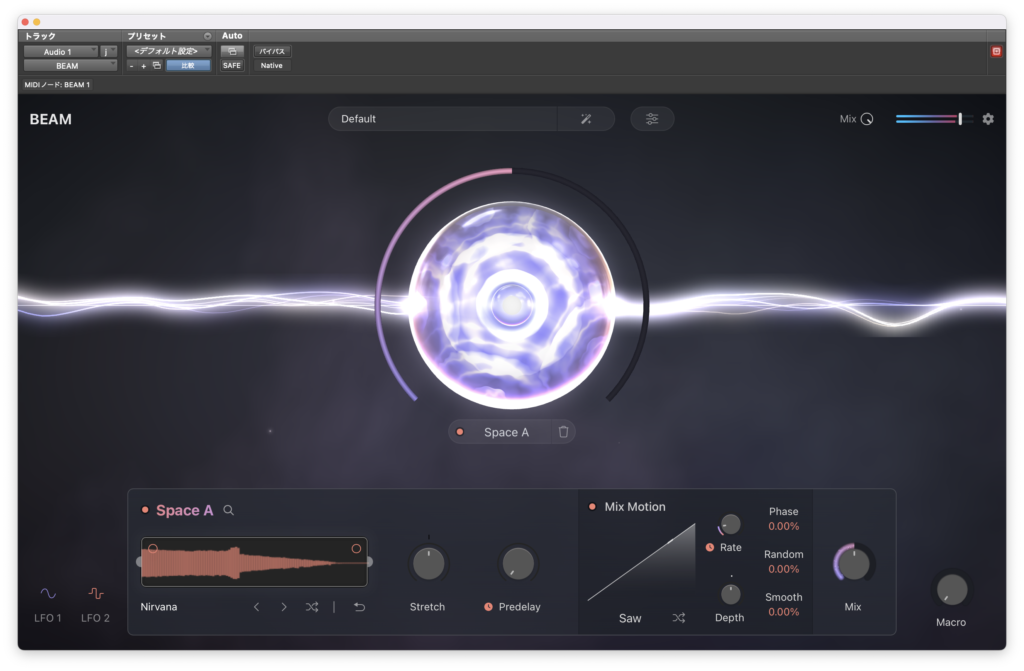

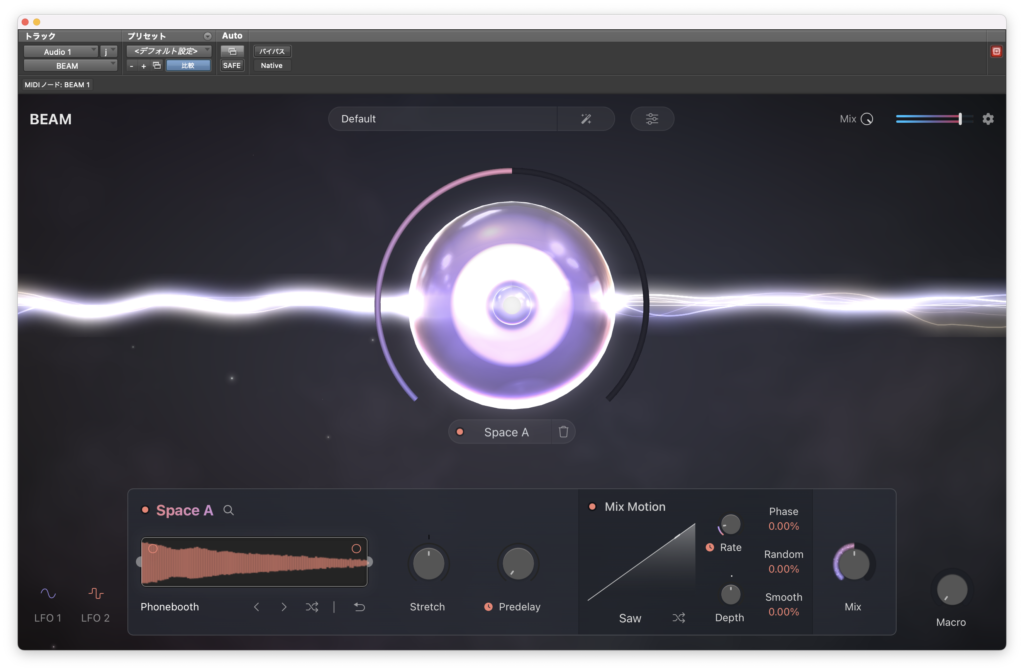
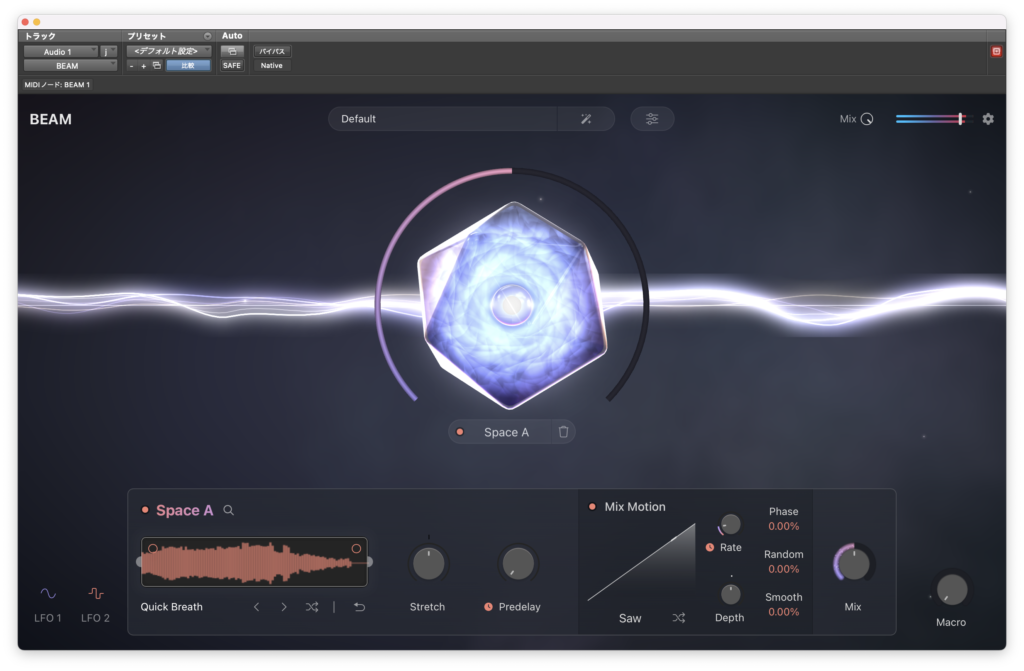
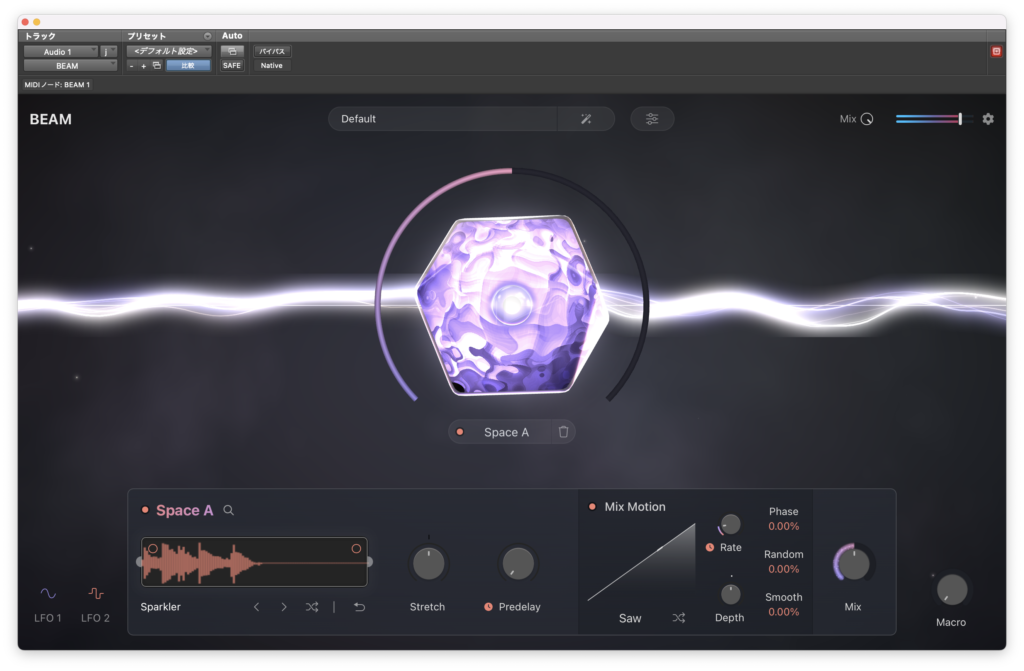
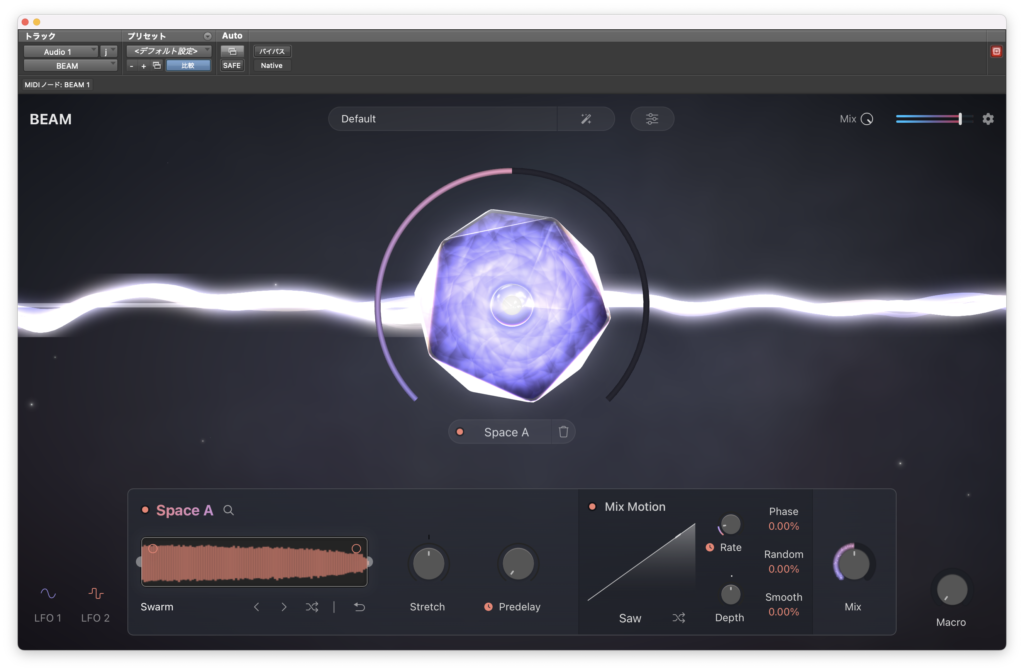
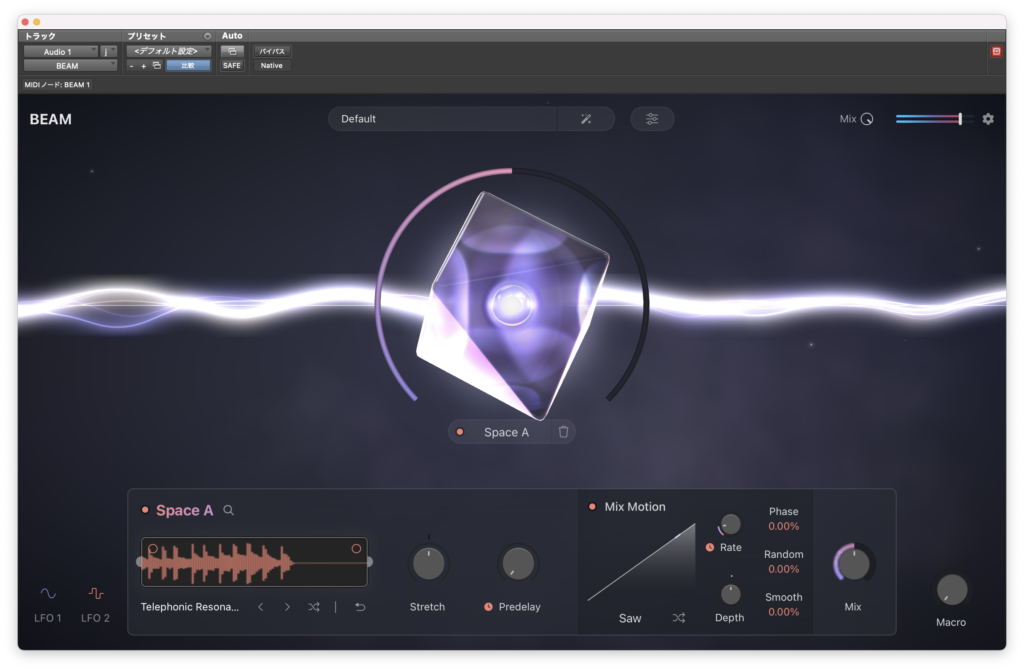
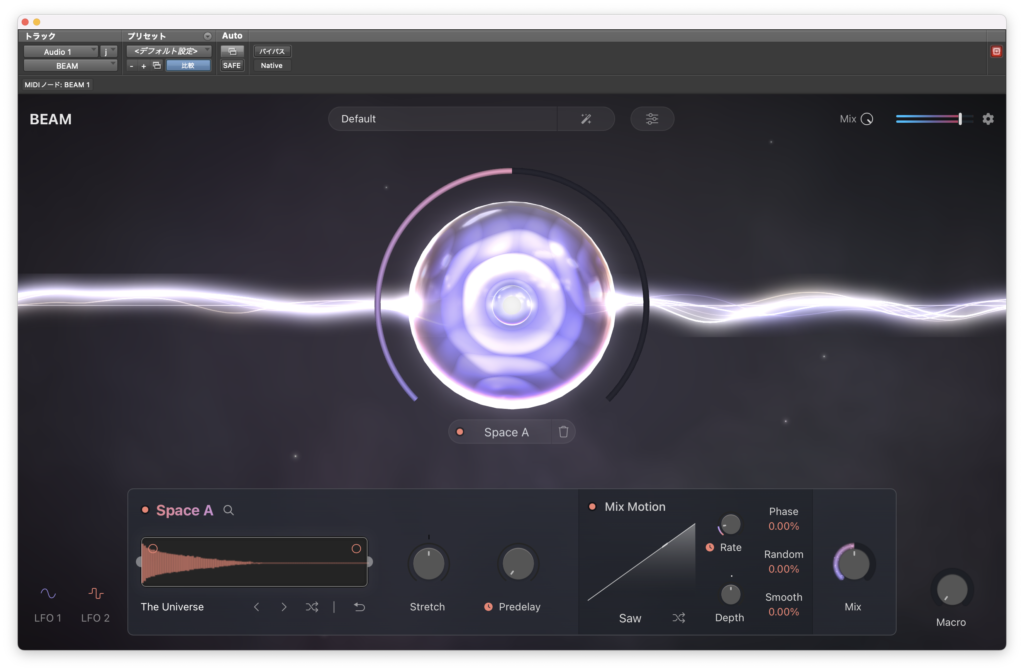
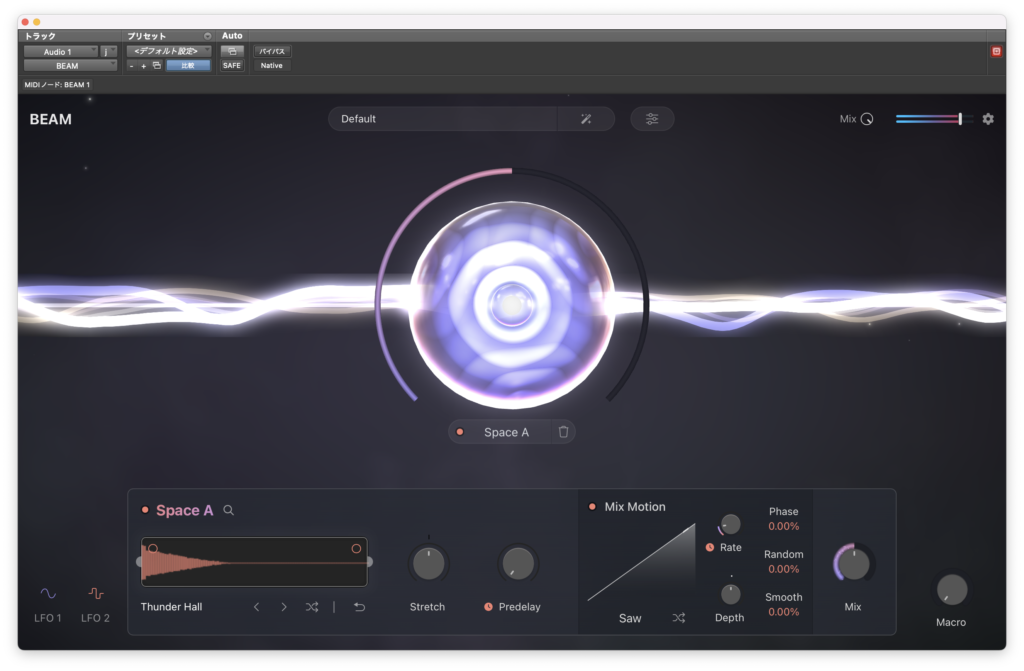
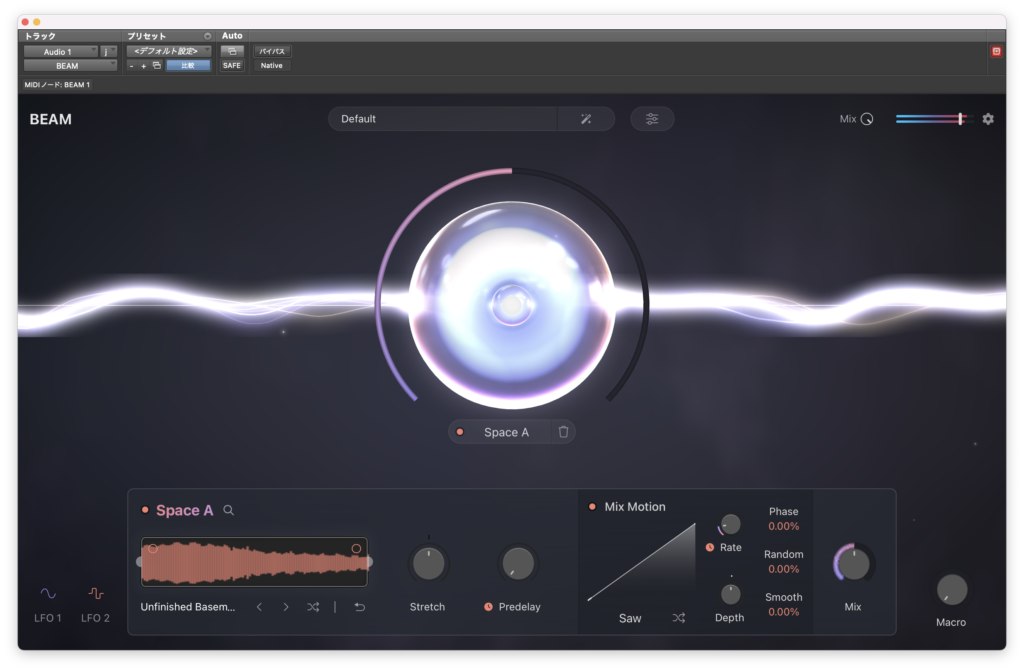
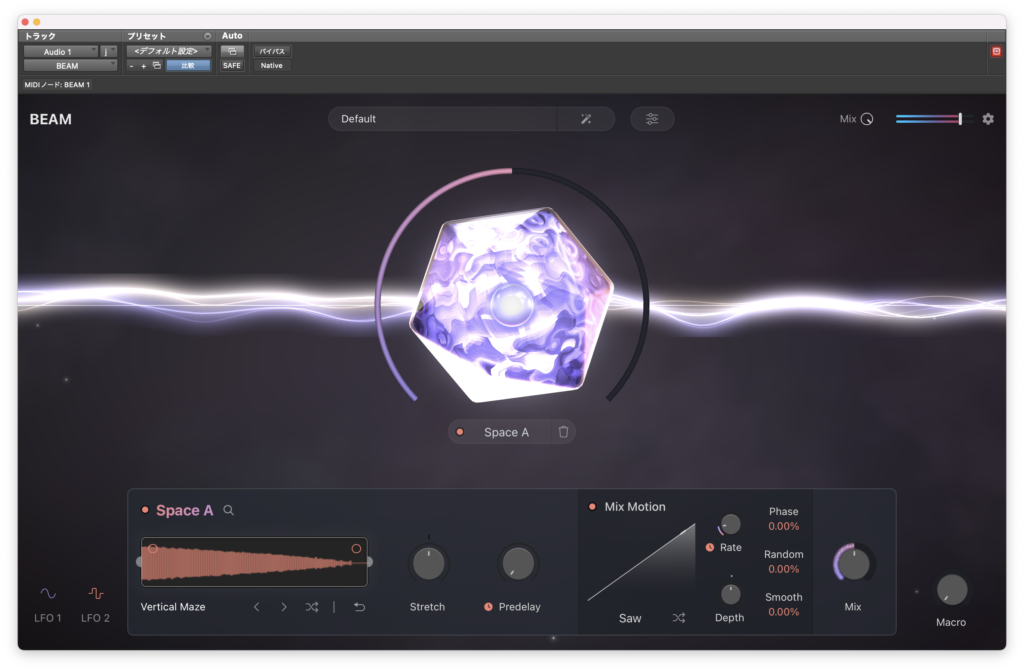
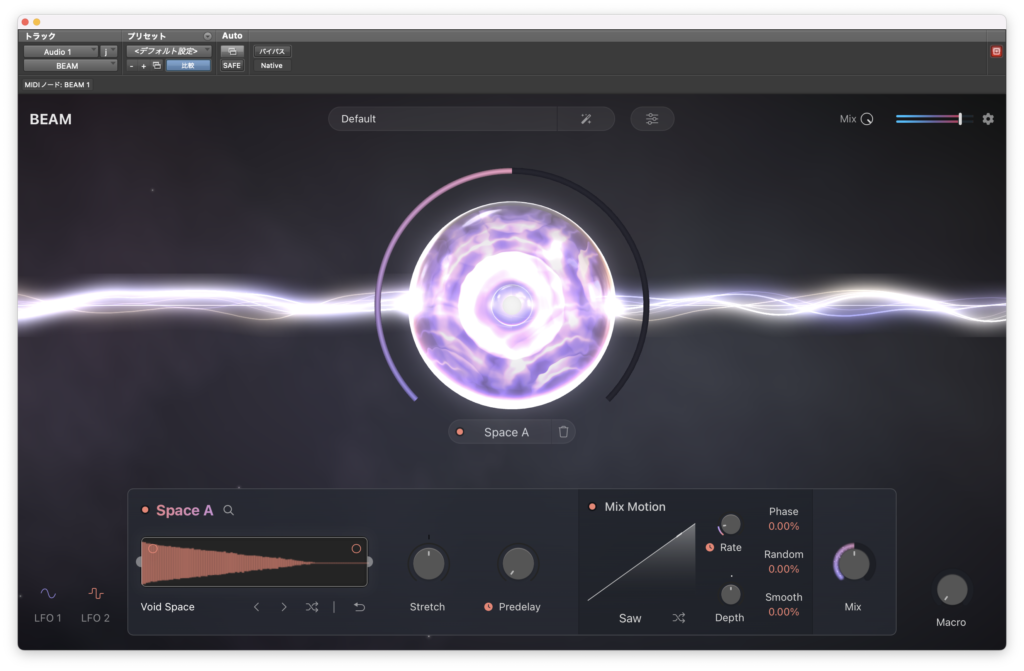
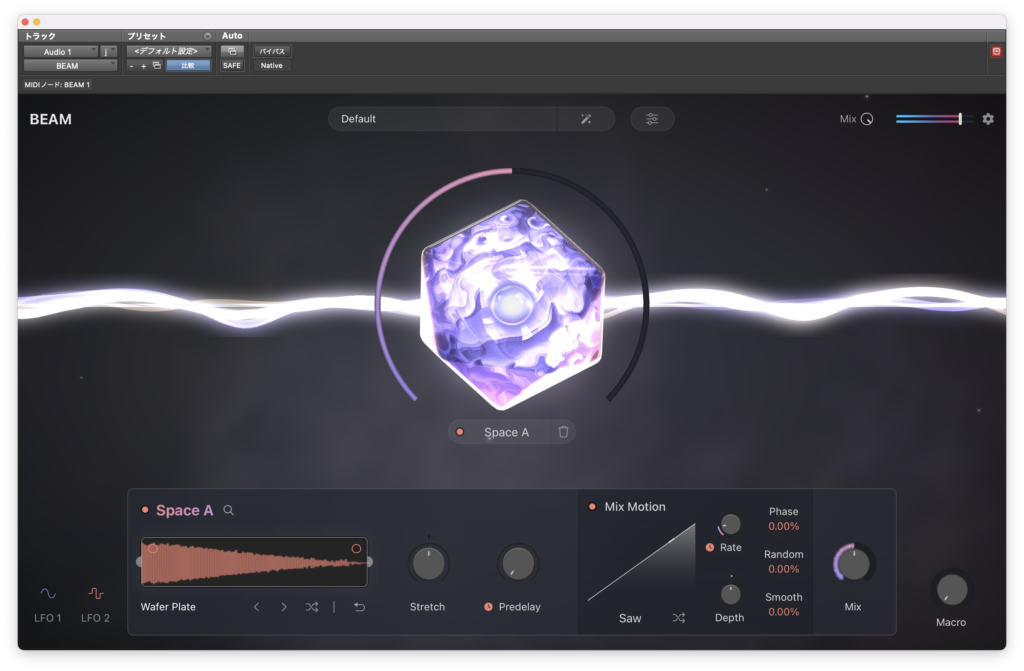
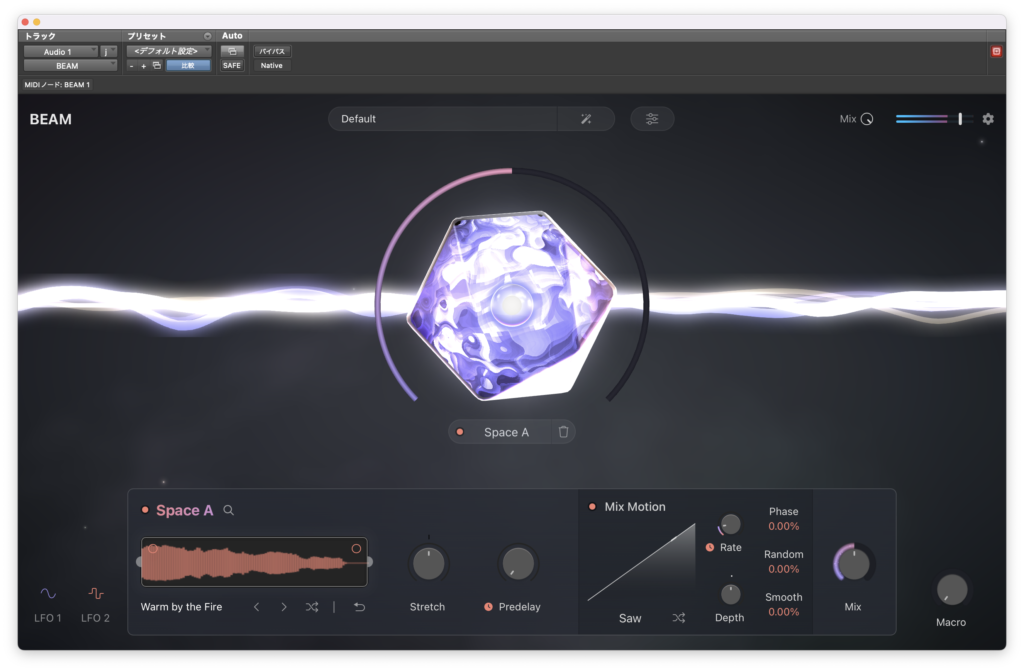
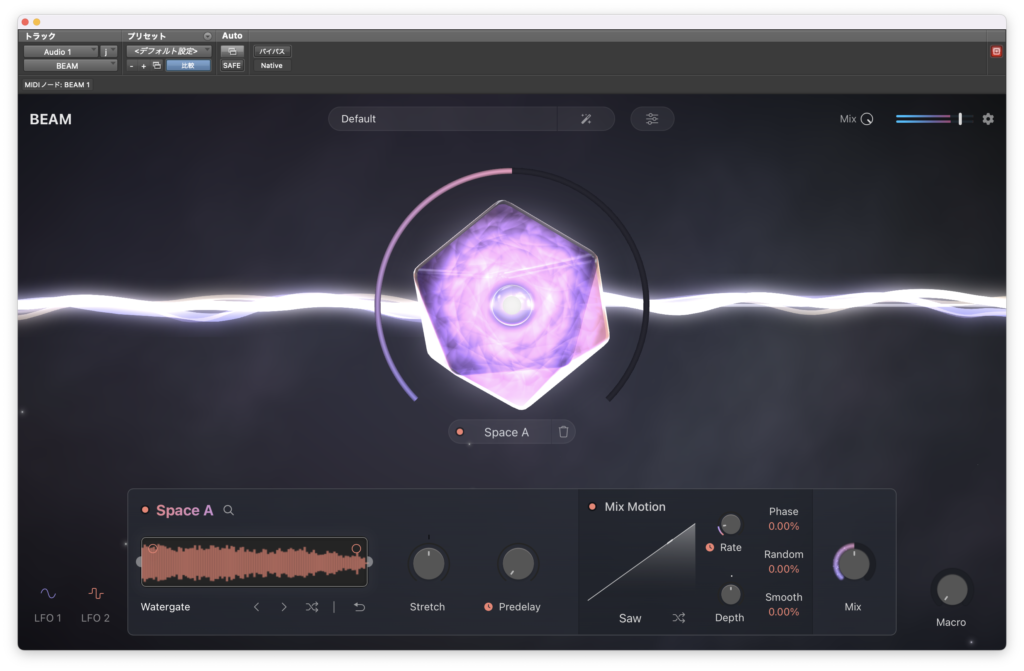
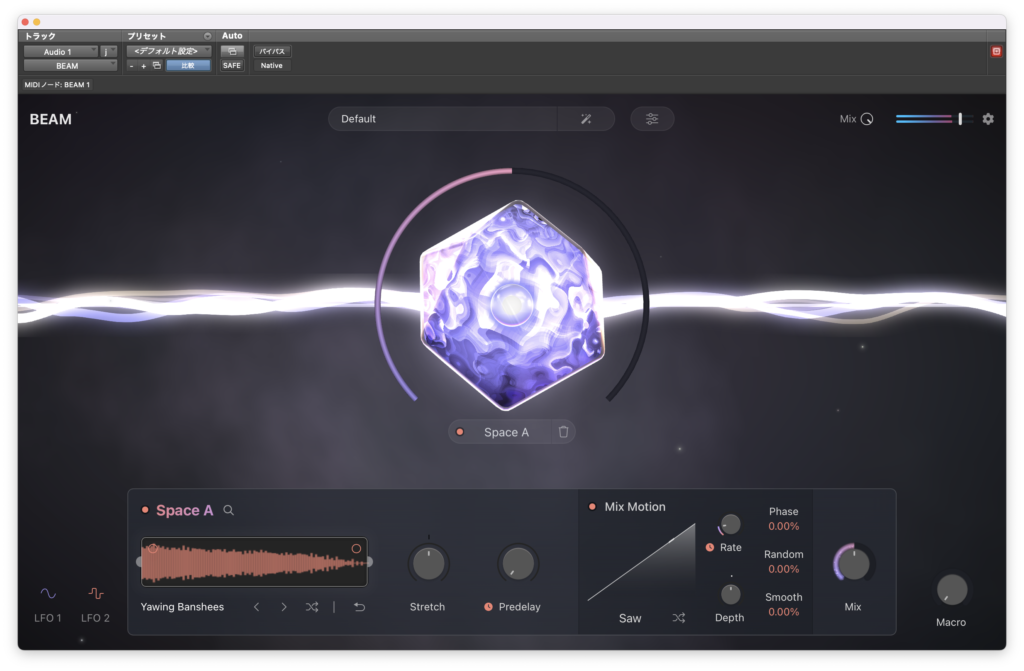

Stretchは再生速度を変更しサンプルし直します。


Predelayは音が入力されてからリバーブ音が発生するまでのタイムラグの調整です。
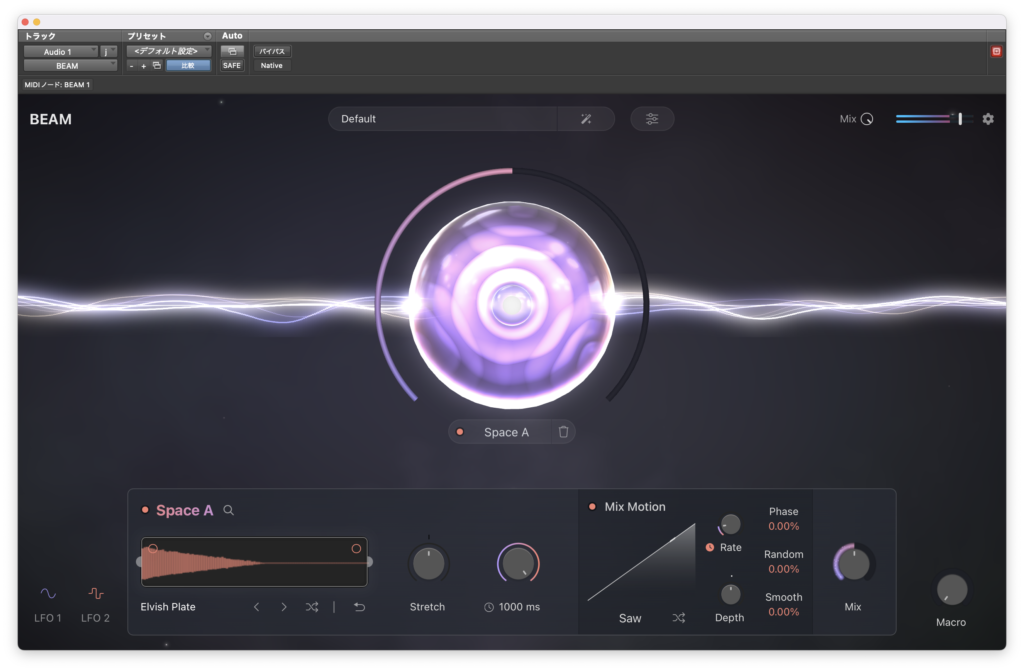
右のMix MotionはWet/Dryの比を右のMixで決めているのですが、これをLFOで動かせるようになっています。



まず、DepthでLFOの動く量を決めます。
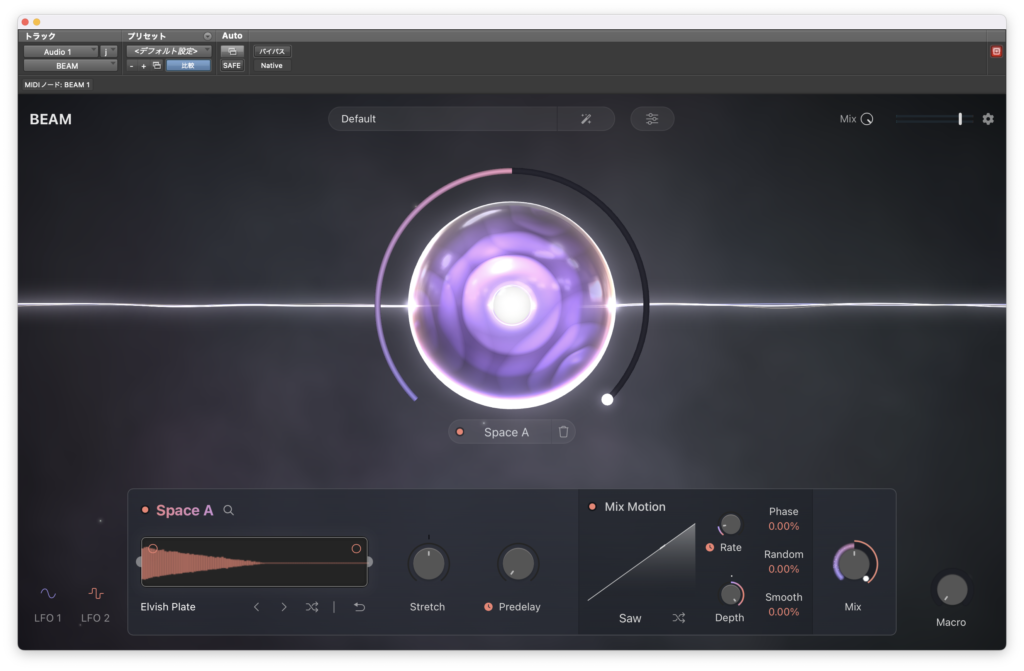
Rateで動く速さを決めます。
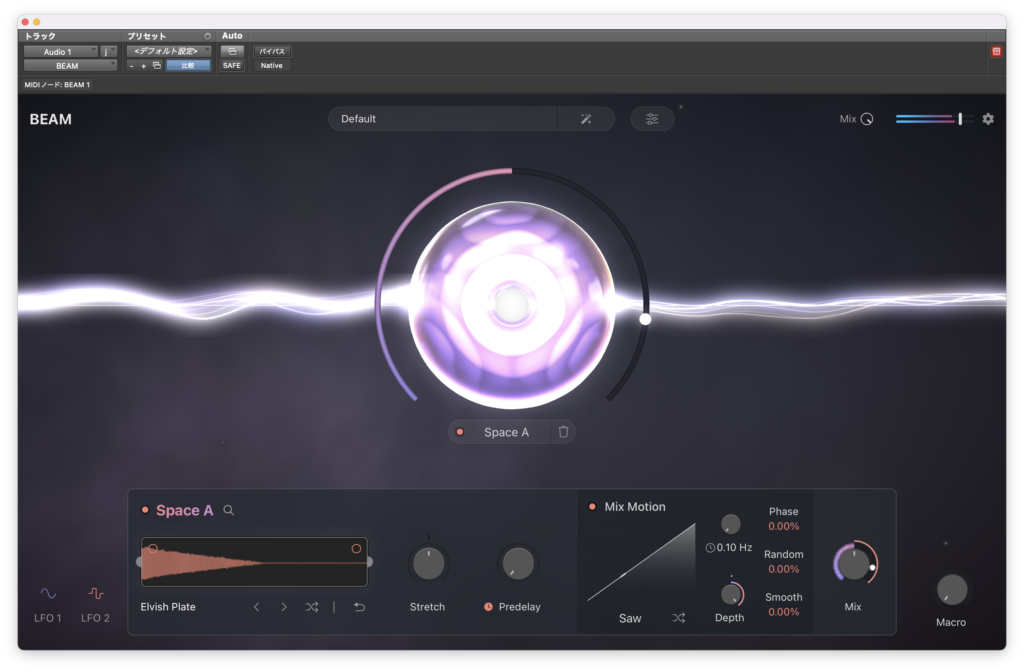
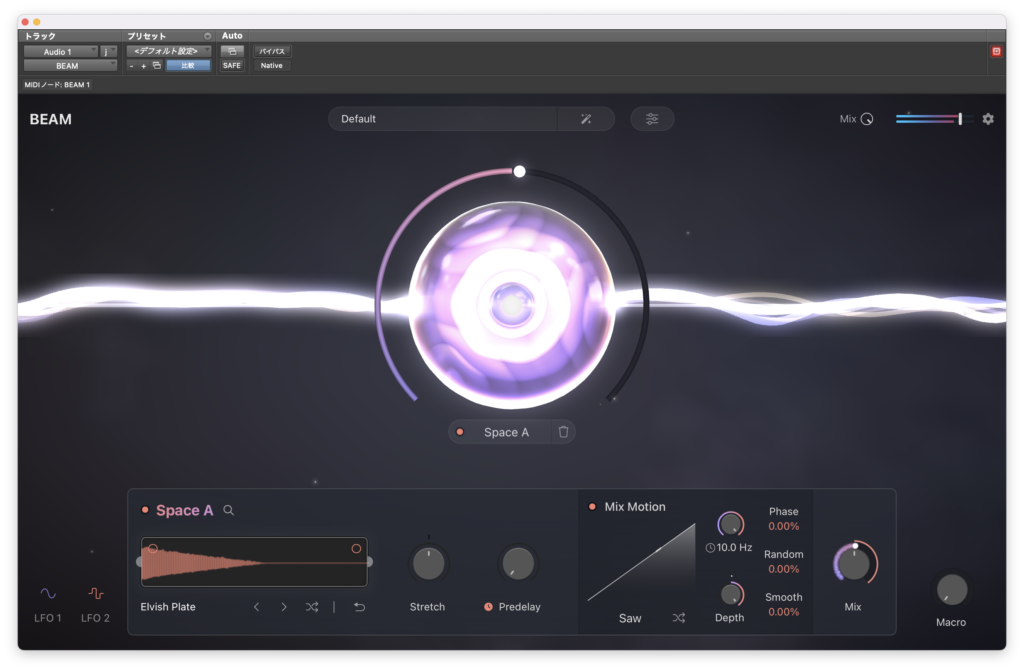
PhaseはLFOの開始位置を動かすパラメーターです。

RandomはLFOの動きに不規則性を加えるパラメーターです。
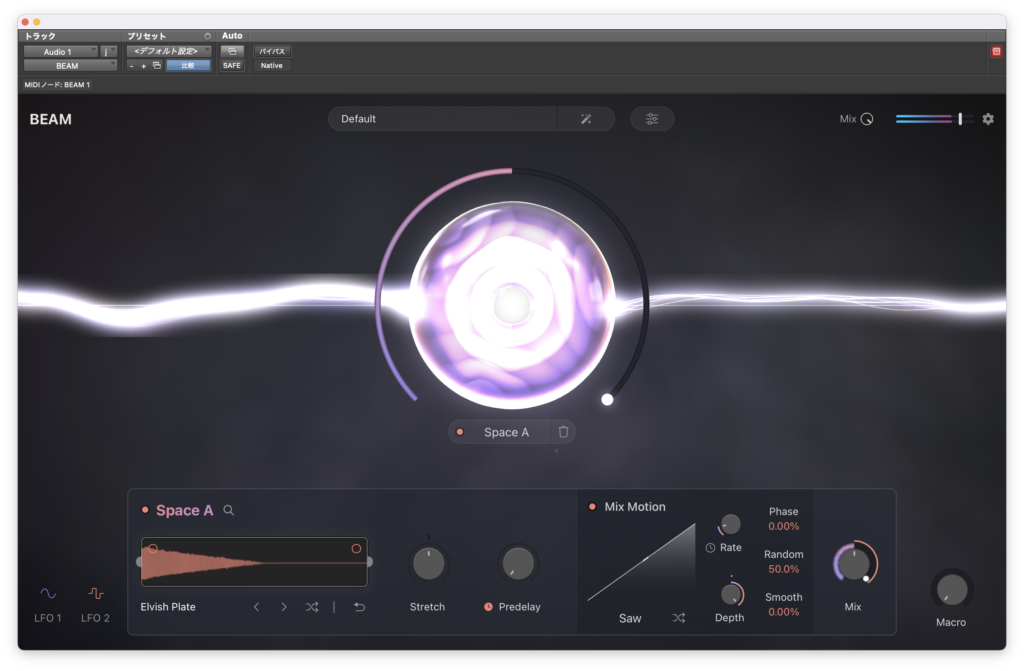

SmoothでLFOの動きの角が滑らかになります。


Grains
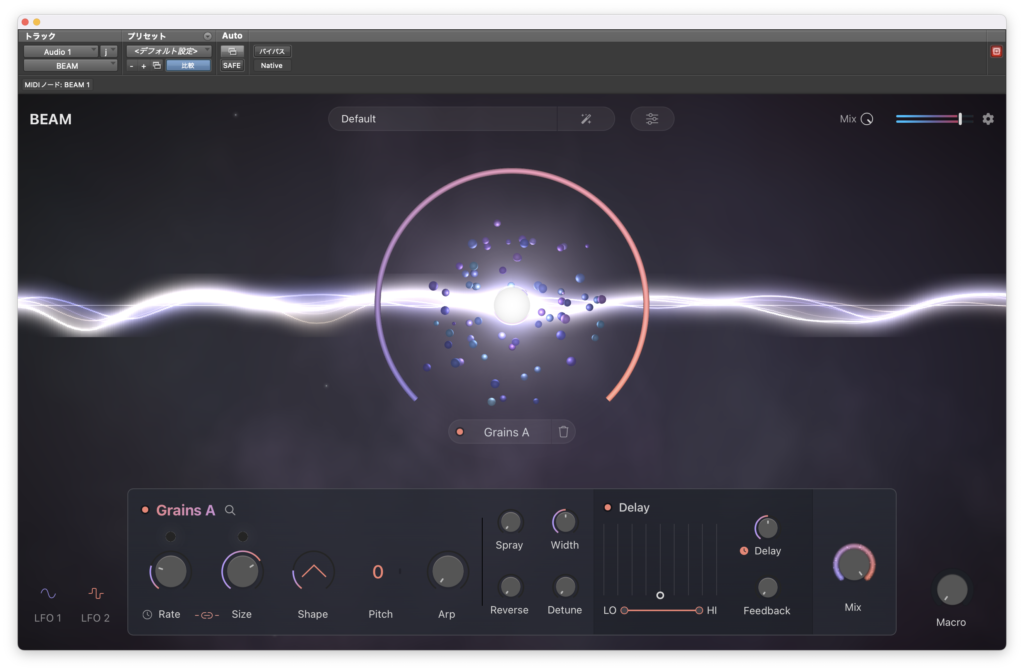
特殊なディレイのモジュールです。
Rateはディレイのフィードバック量とディレイタイムを調整しているようです。
パラメーターを上げるとディレイの音数が増え、ディレイタイムが短くなります。(音の密度が上がったようになります)
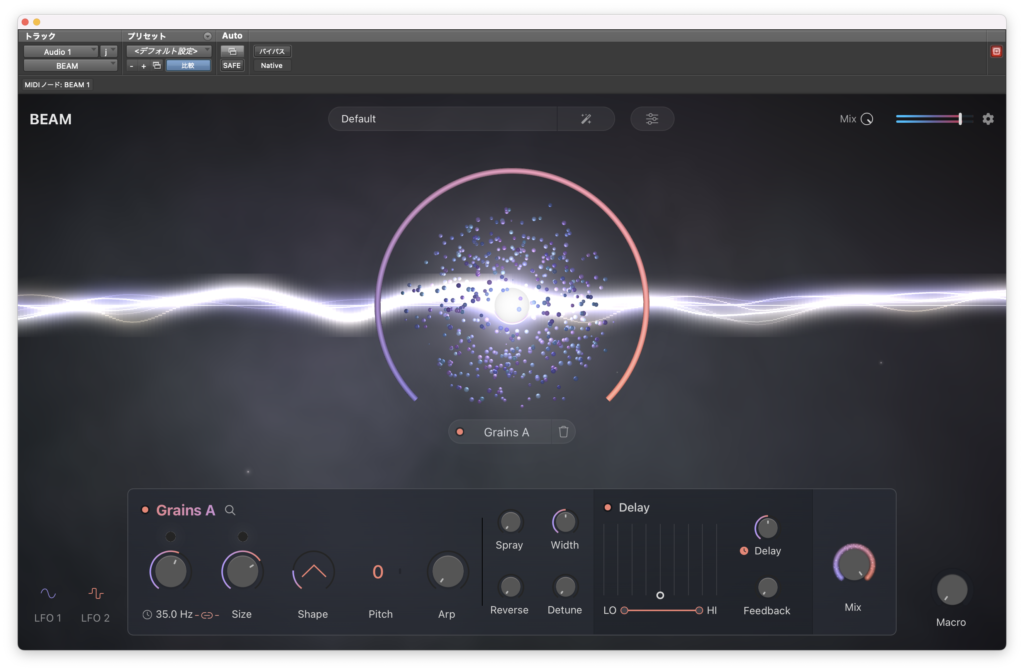
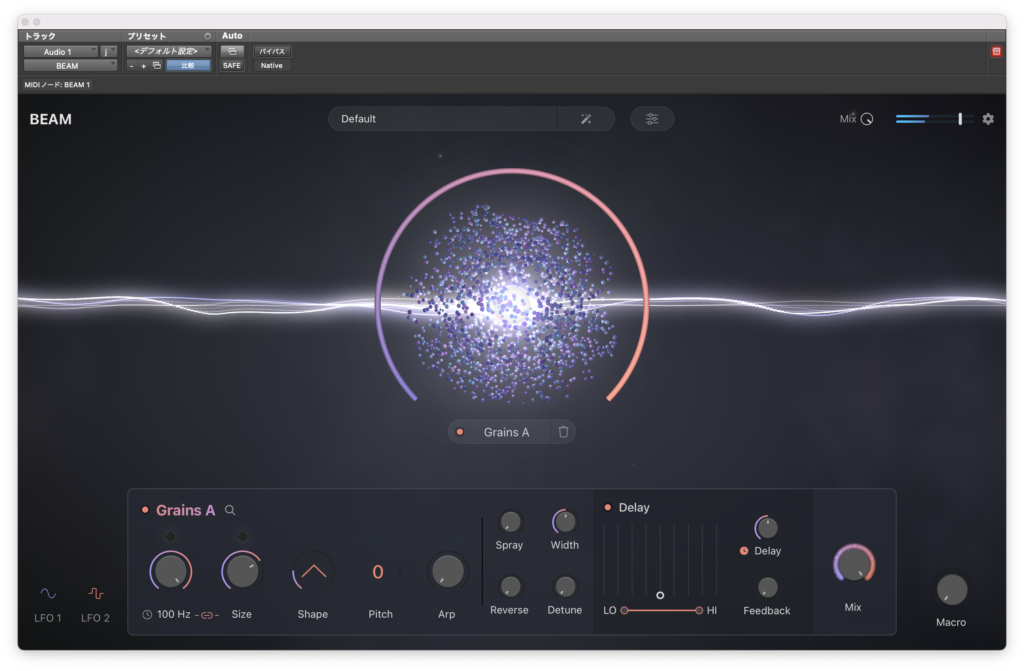
すぐ上にRandというパラメーターをランダム化するものがあります。
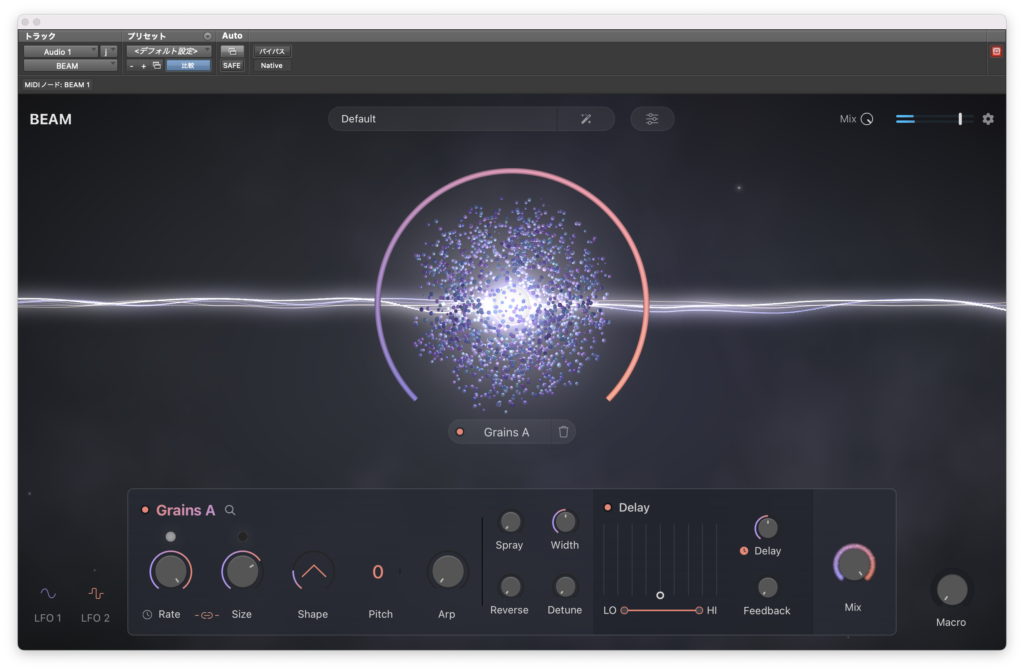
右にあるSizeはディレイ音の粒の大きさを指定するもので、小さくすると音が途中でぶつ切りになります。
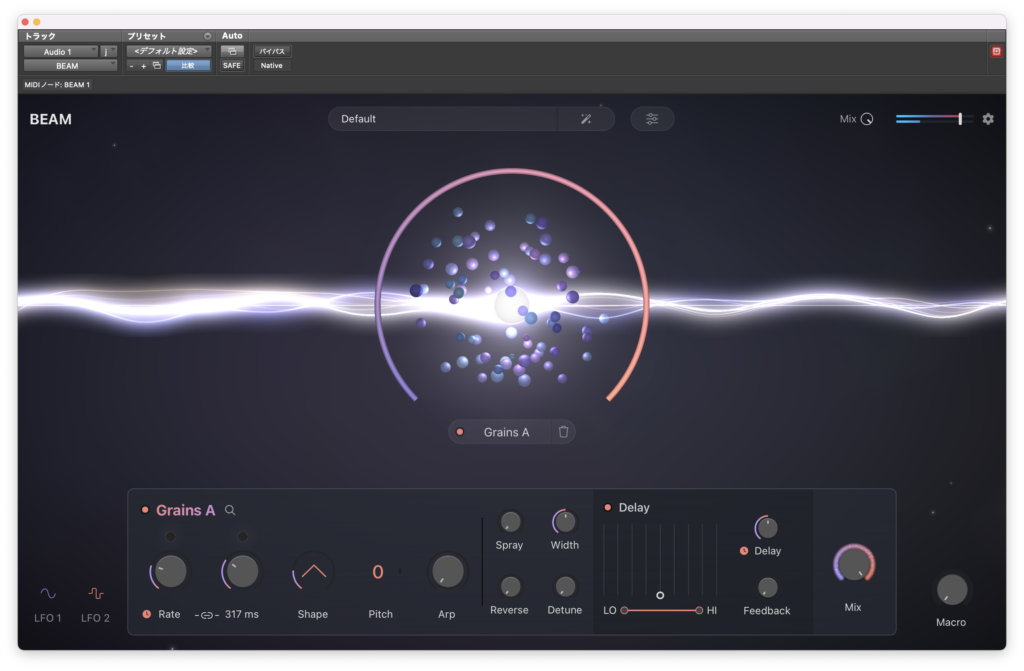
こちらもRandというランダム化するパラメーターがついています。

Shapeはエフェクト音にかかるVCAのカーブだそうです。
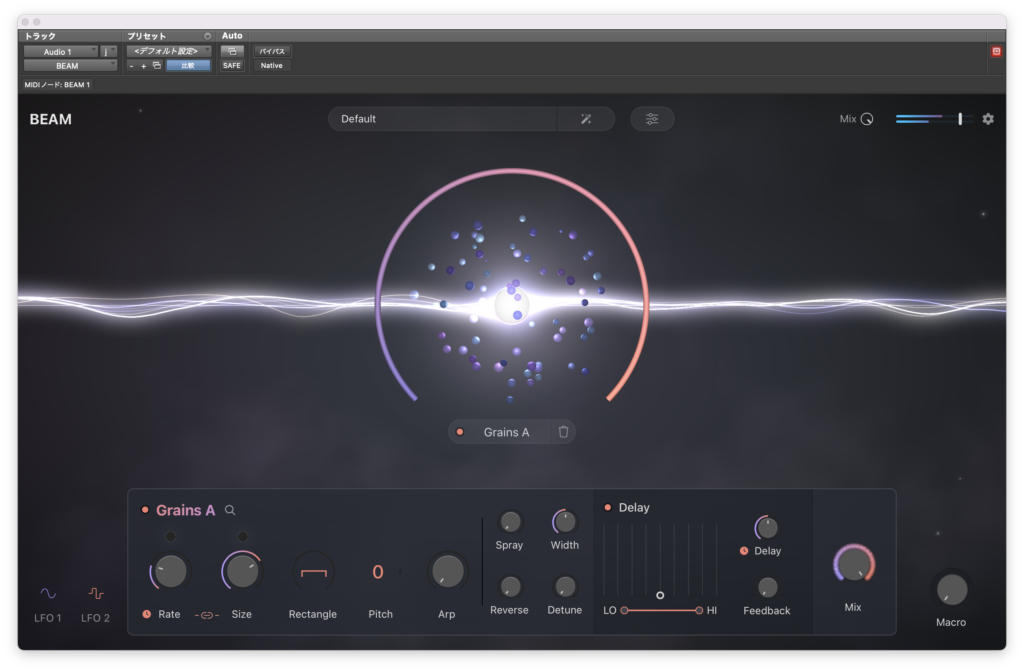
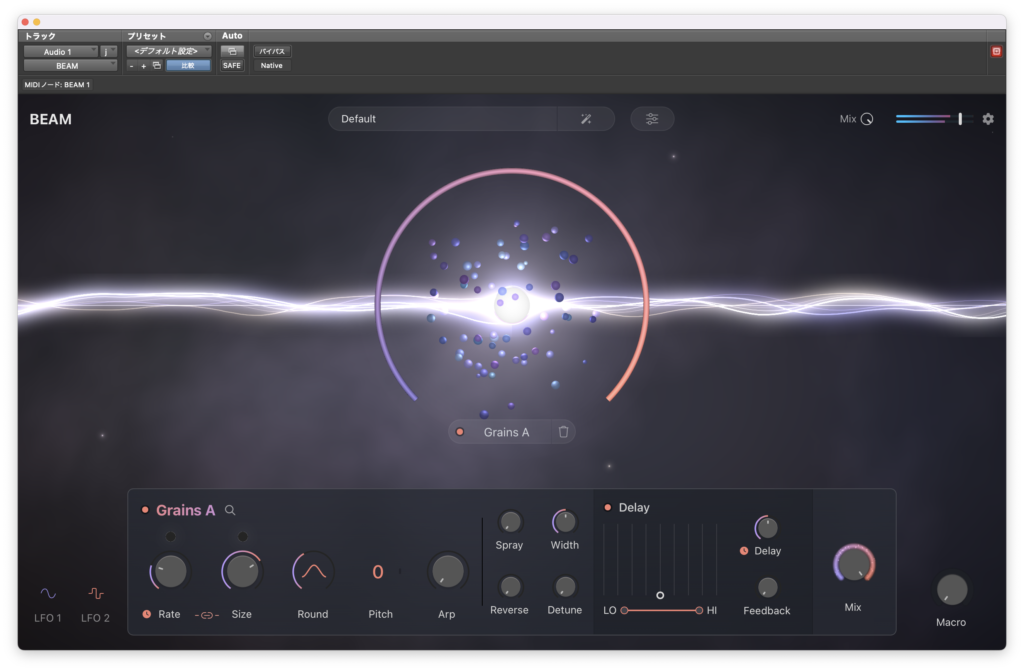
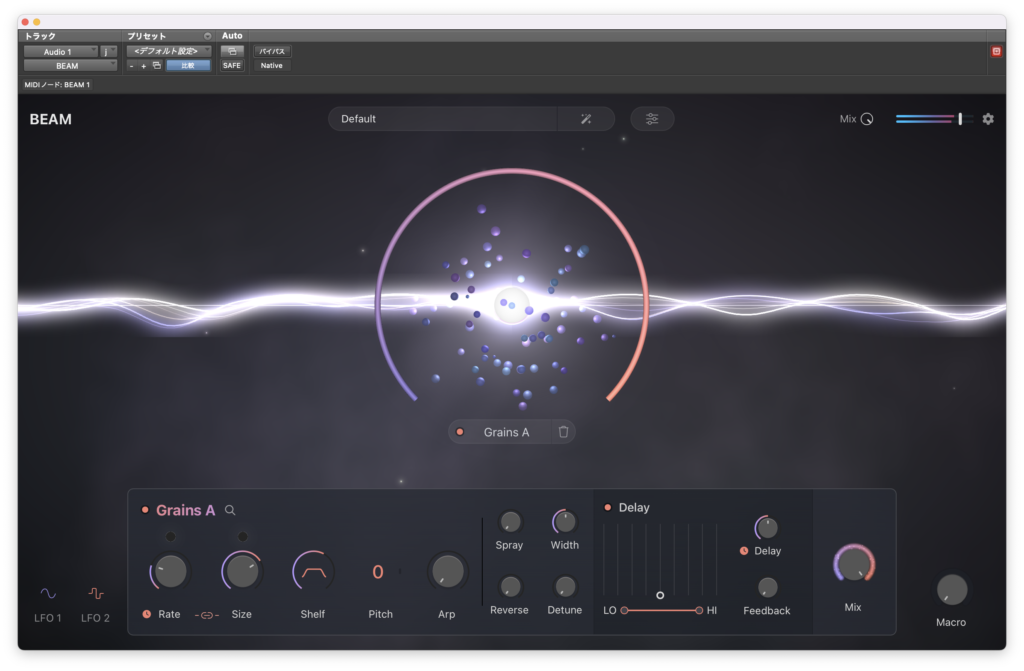
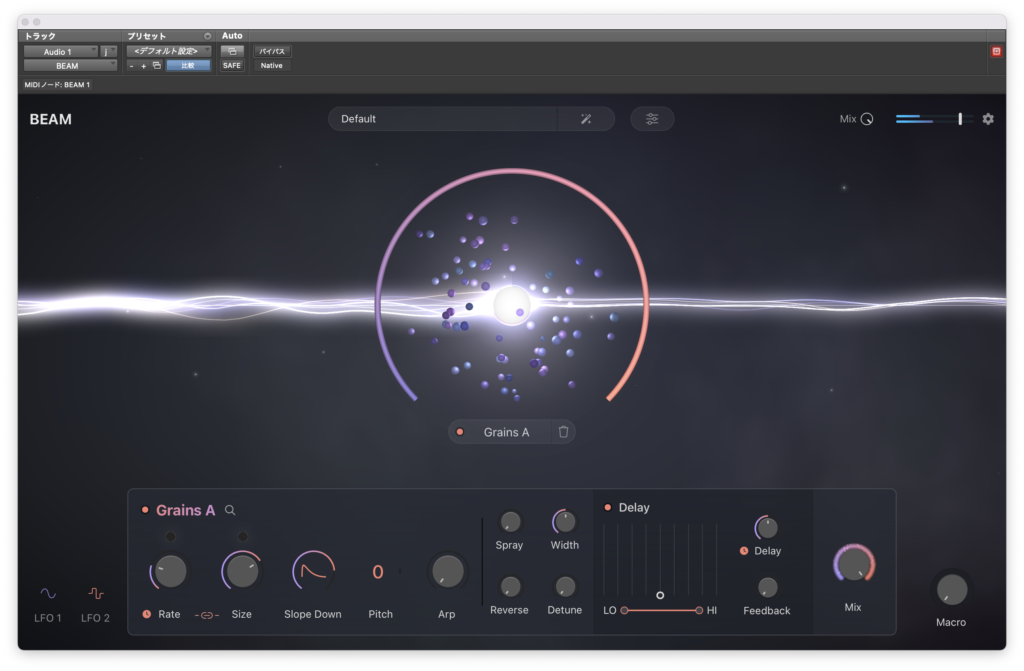

Pitchにより半音間隔でピッチシフトさせることができます。

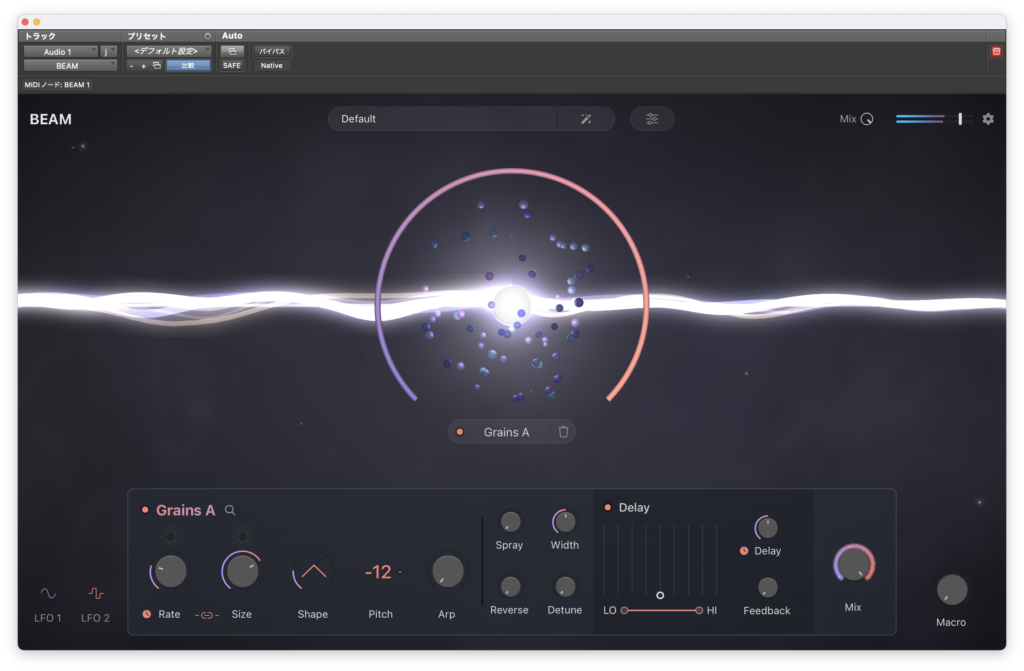
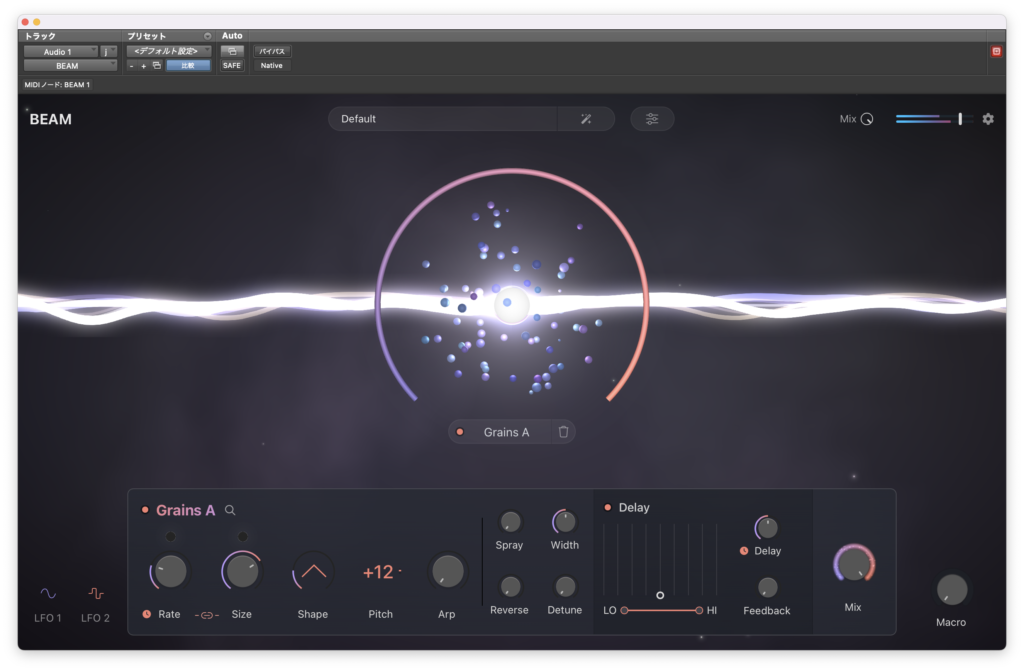
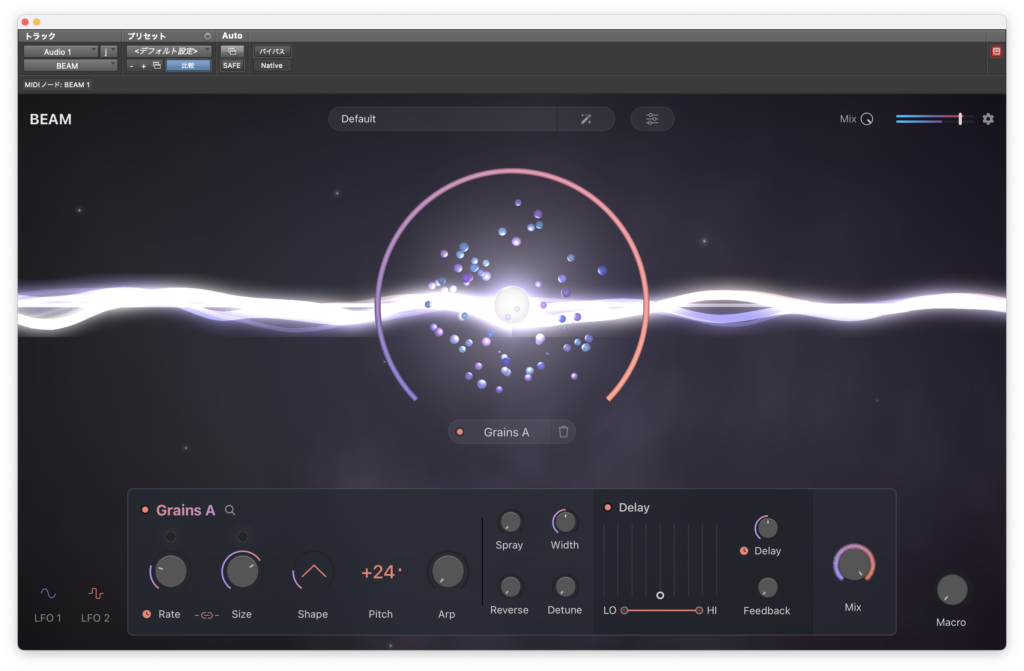
Arpではアルペジエーターのように音程を段階的に変化させることができます。
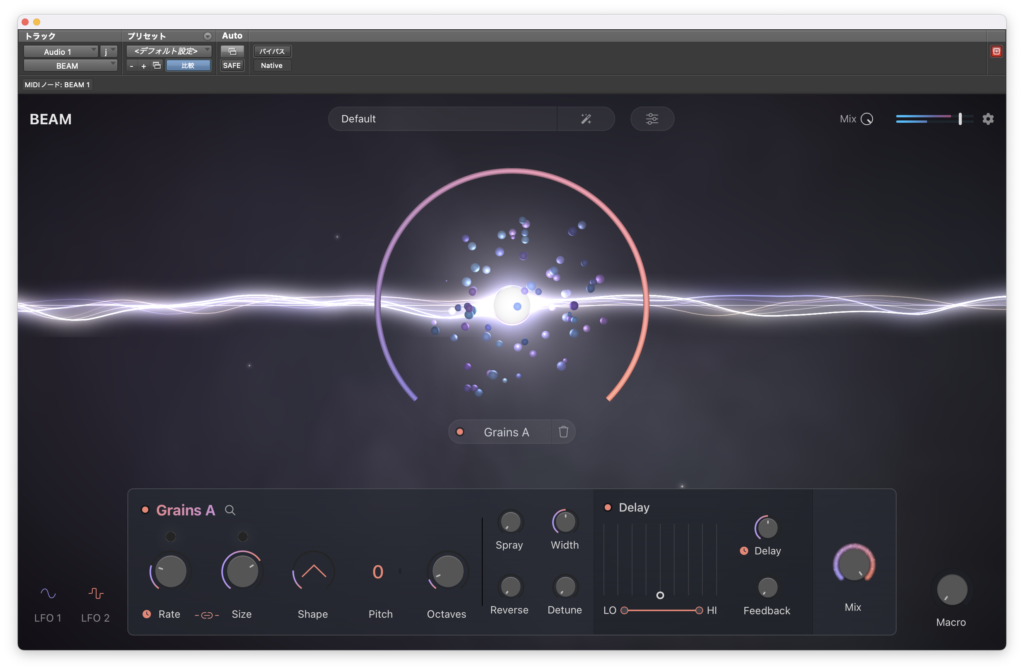
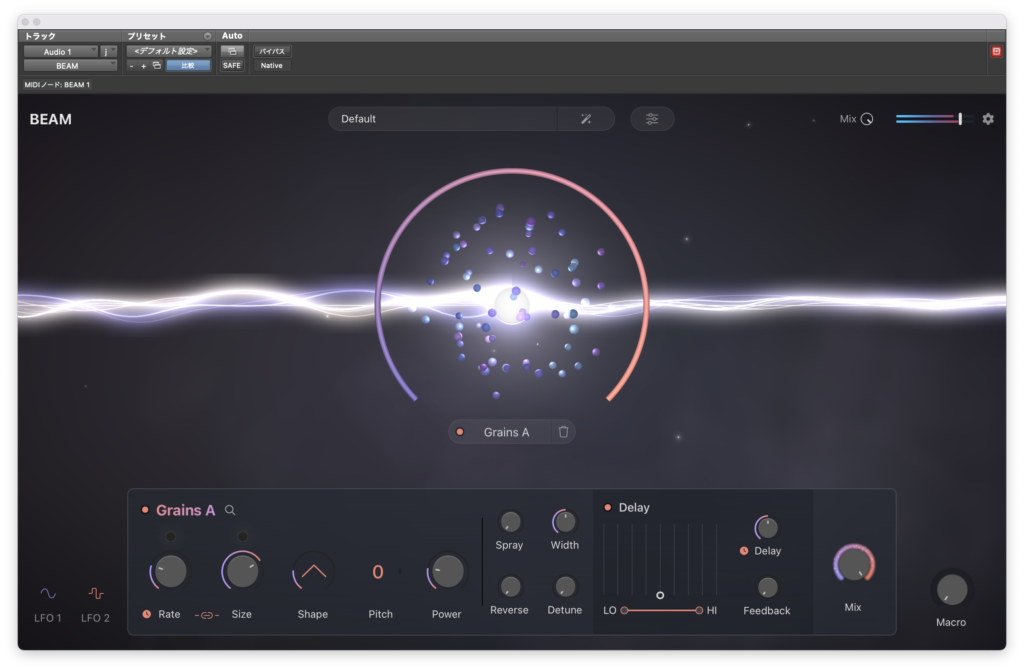
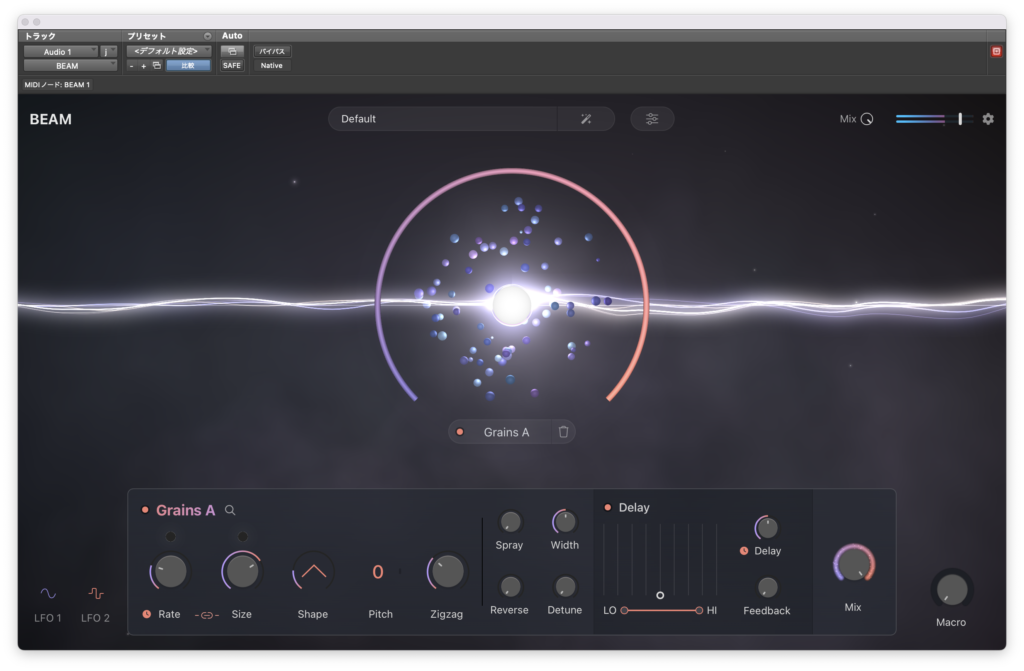
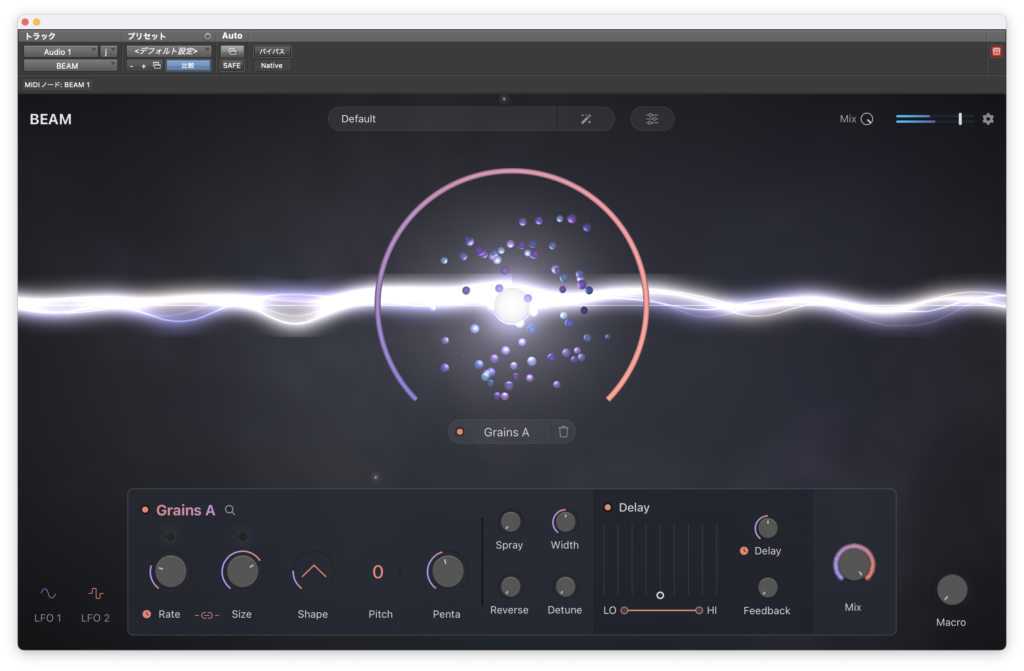

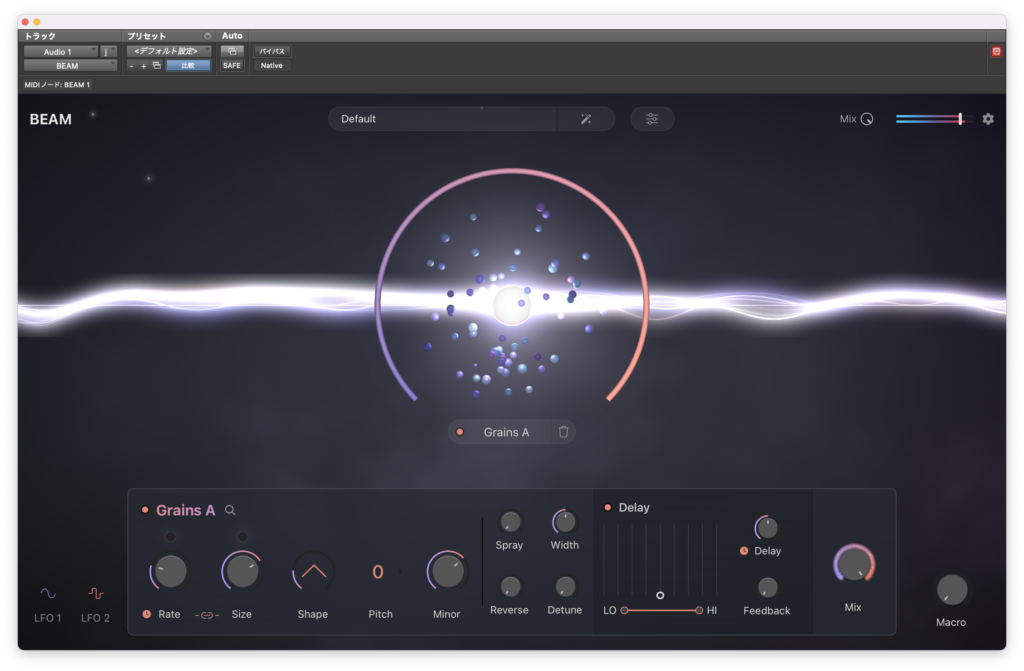

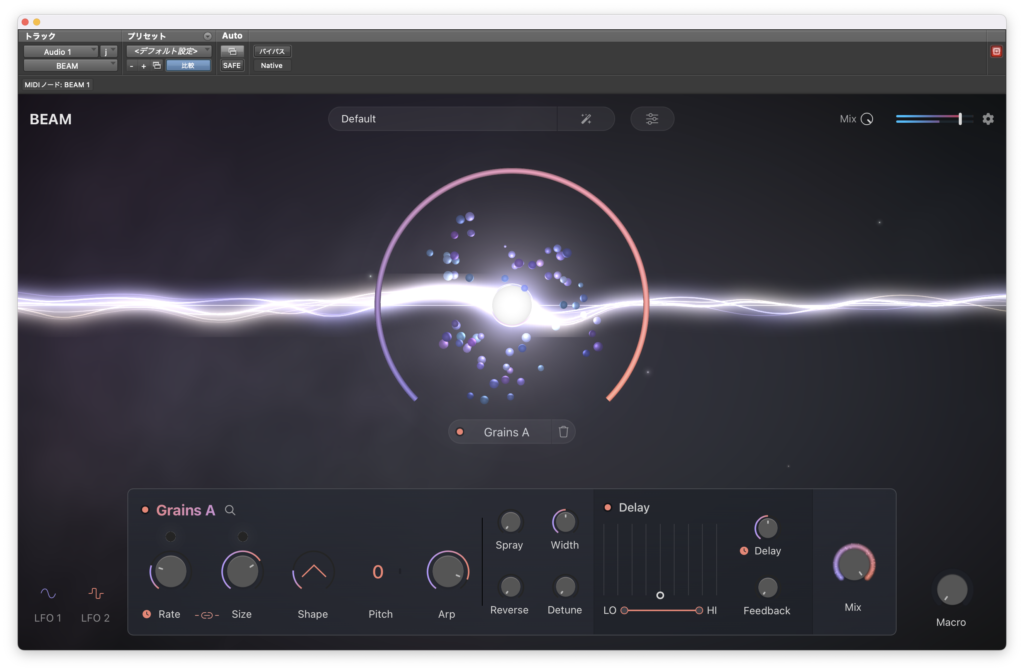
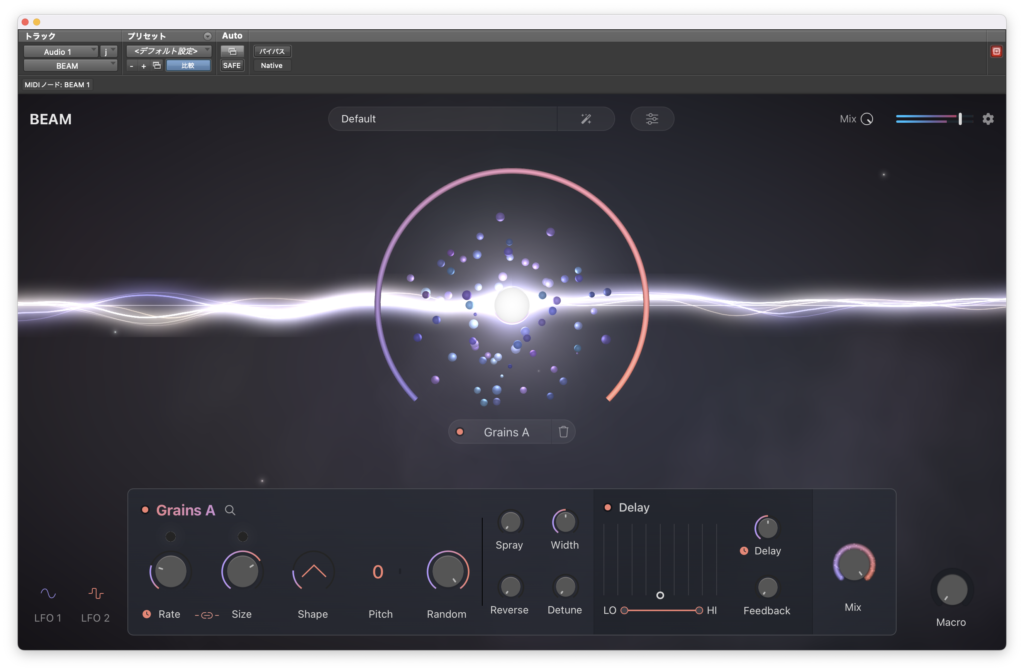
中央にあるSprayはエフェクト音の現れるタイミングにランダム性を加えます。

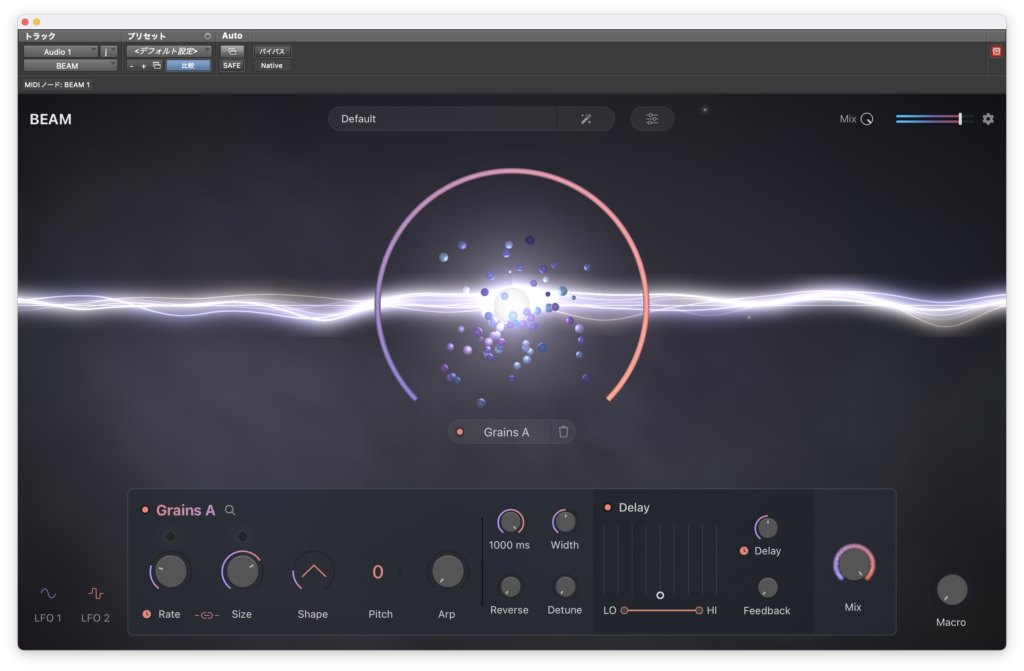
Widthはエフェクト音が現れるLR幅の範囲を決めます。
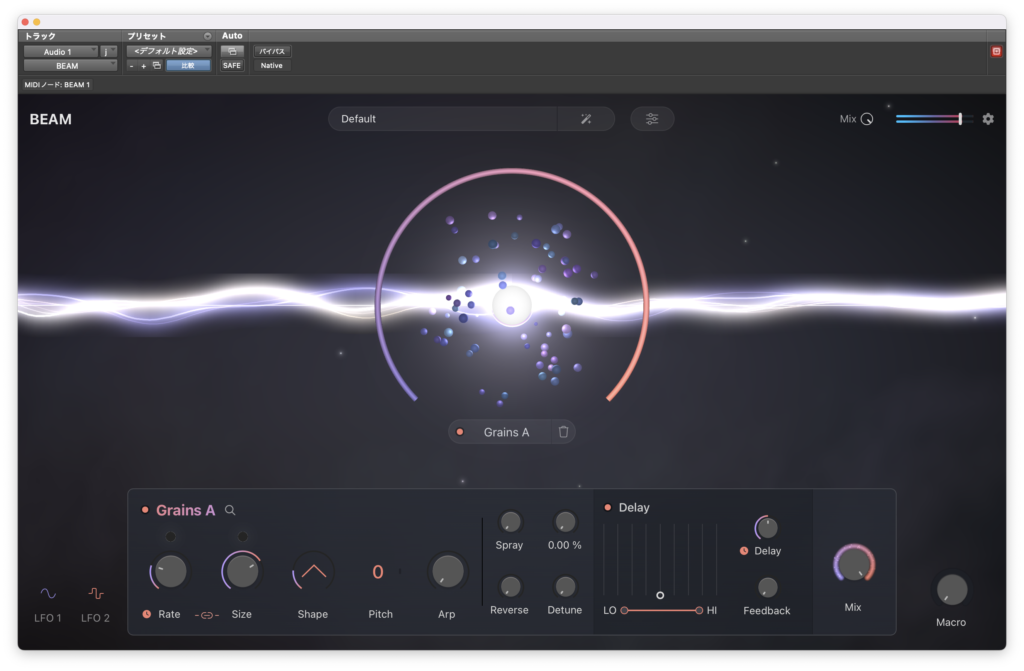
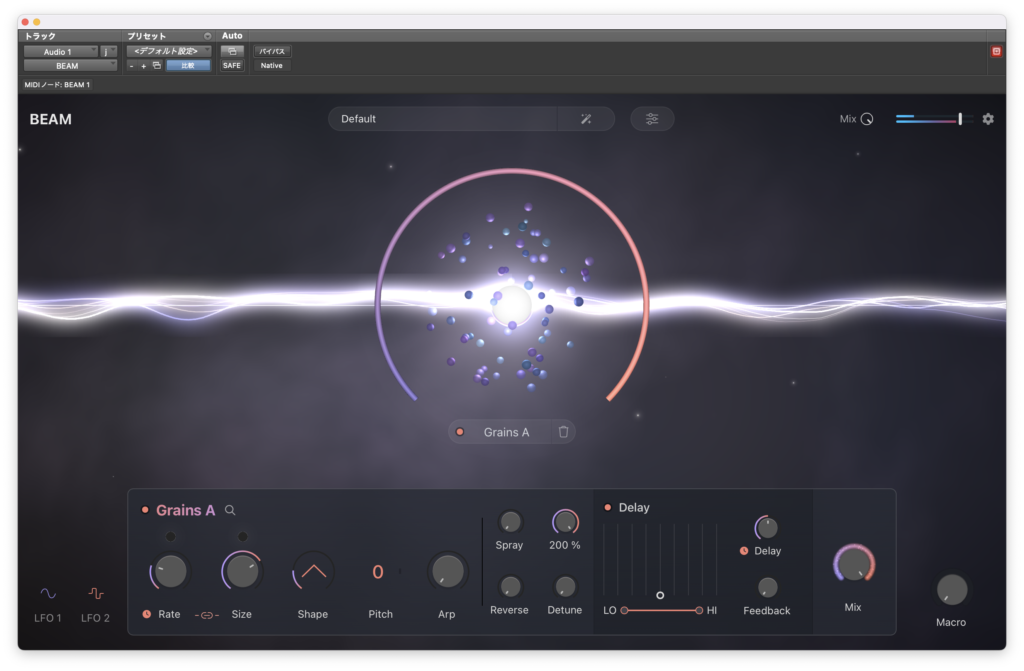
Reverseでエフェクト音を逆再生させる割合を決めます。
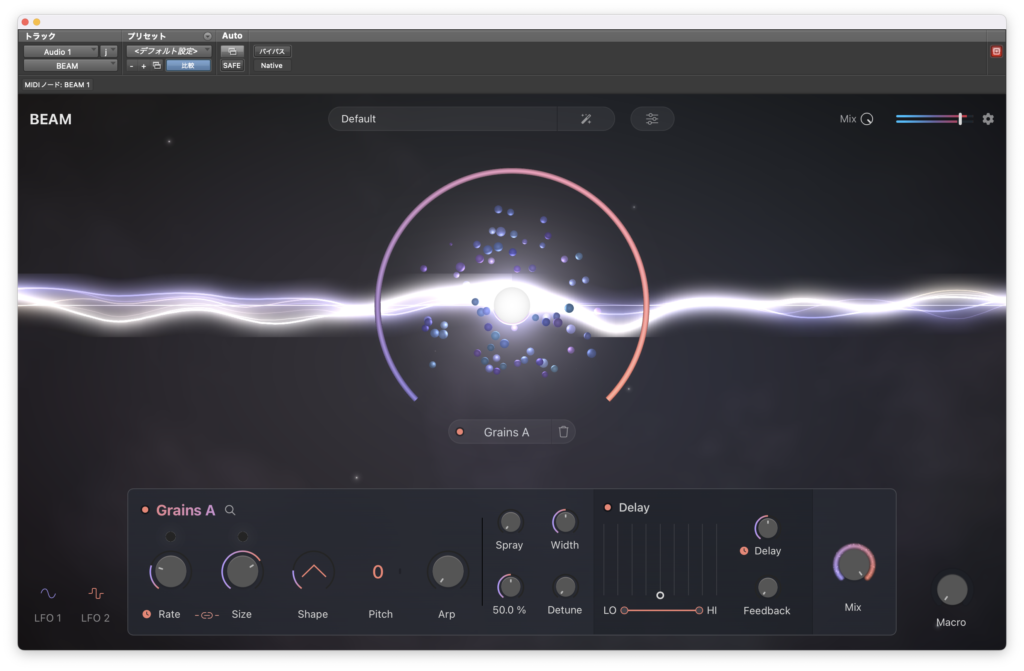
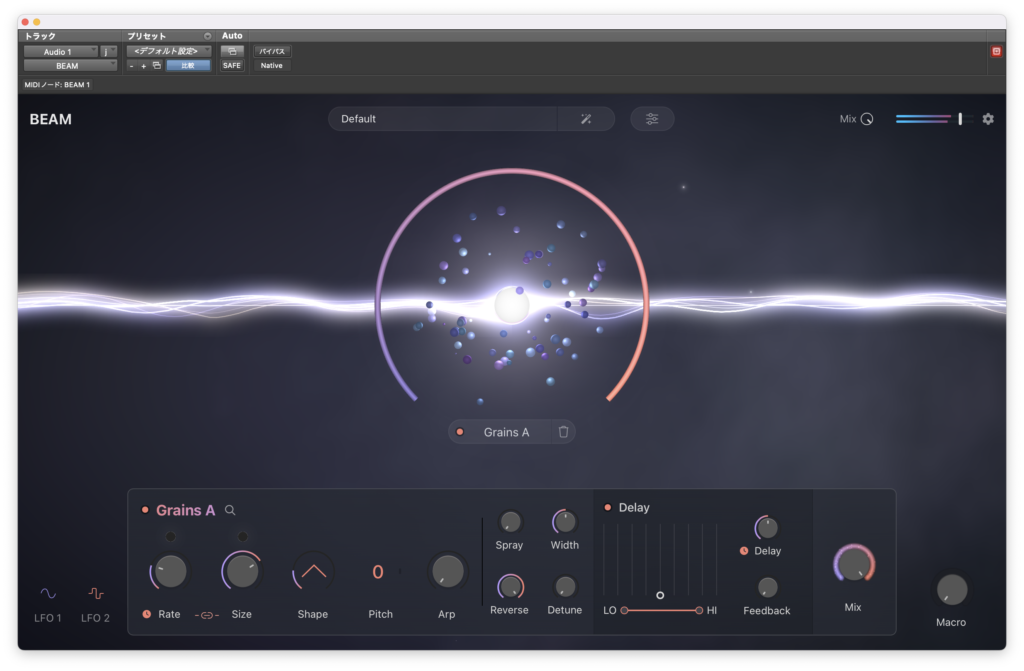
Detuneでエフェクト音のピッチを揺らします。
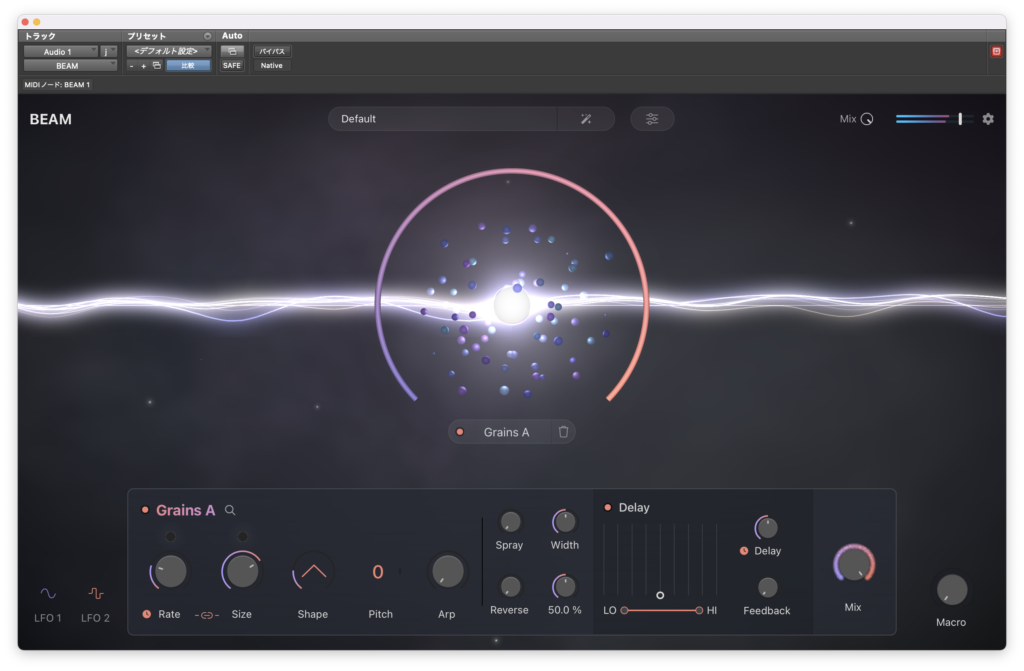
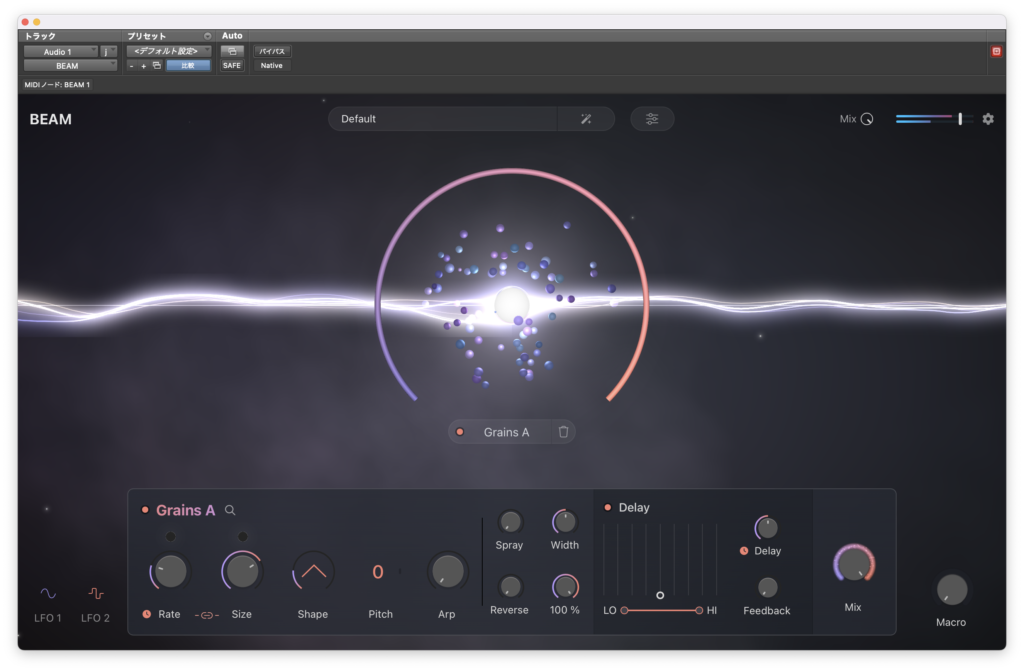
右側にはDelayがあります。
Delayでディレイタイムを操作、Feedbackで返ってくる音の量を調整します。
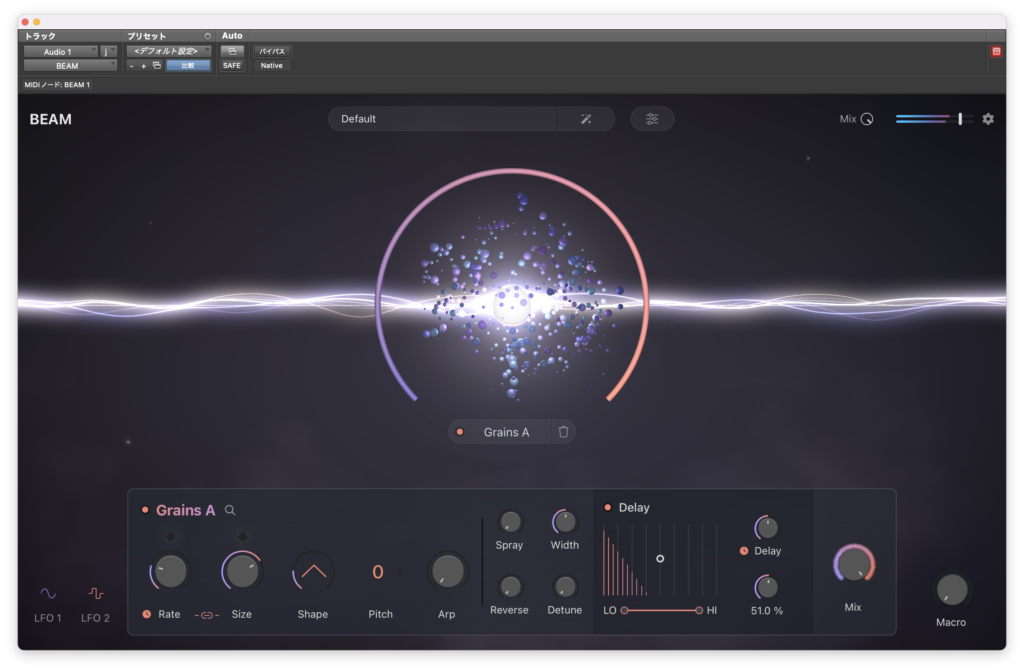
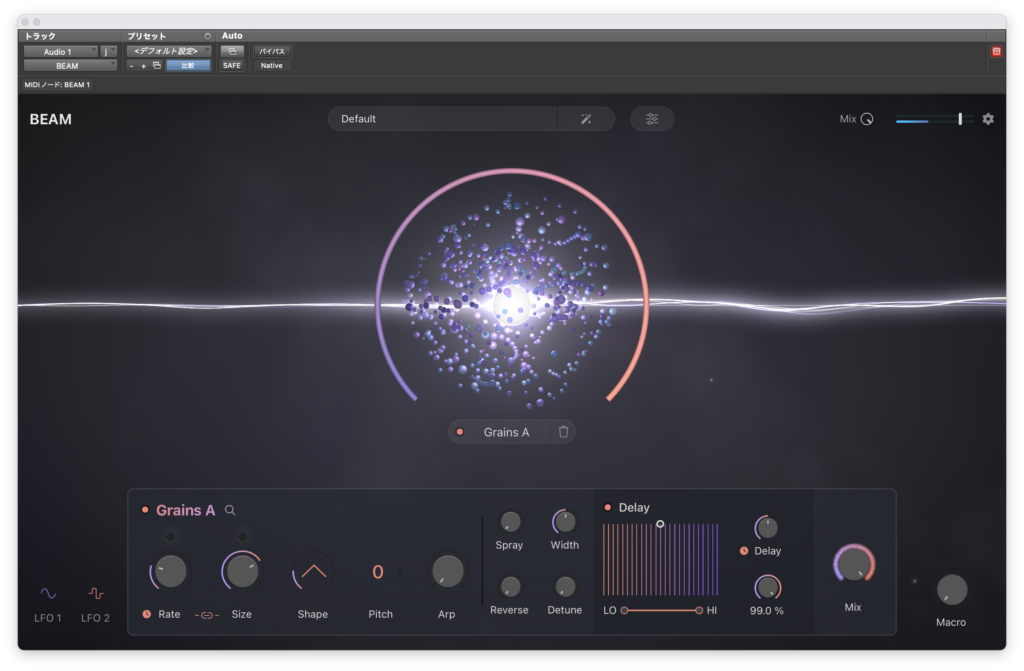
ローパスフィルターとハイパスフィルターもついています。
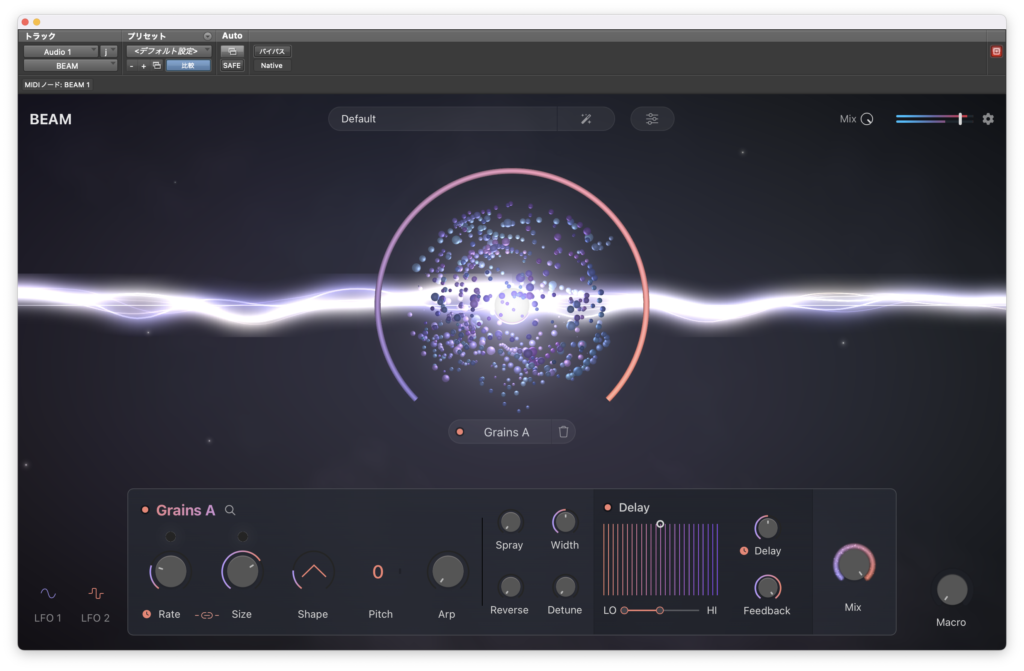
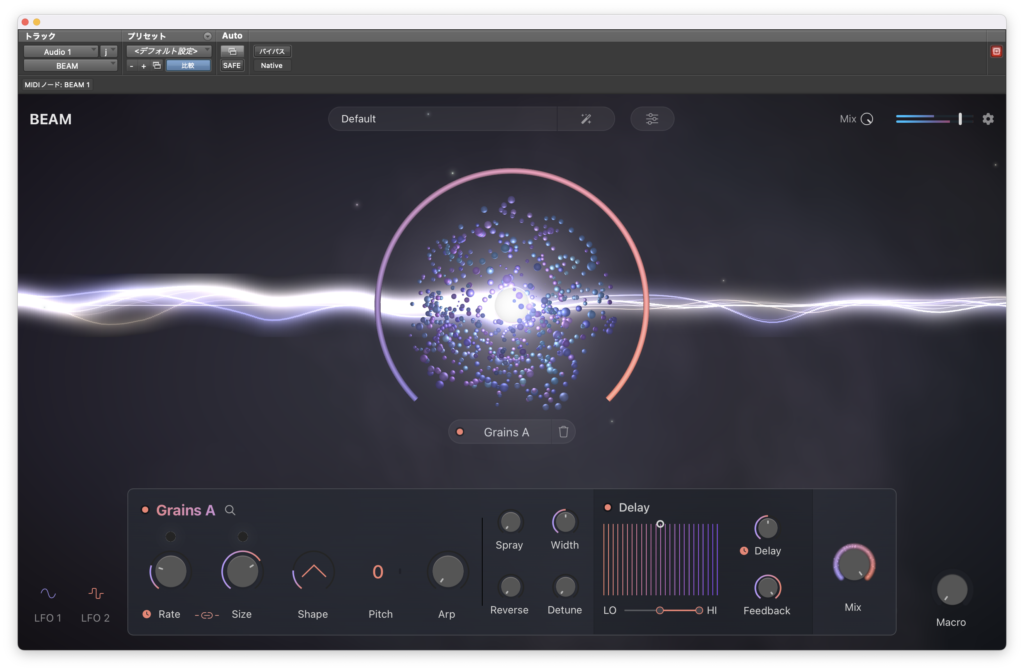
Filter
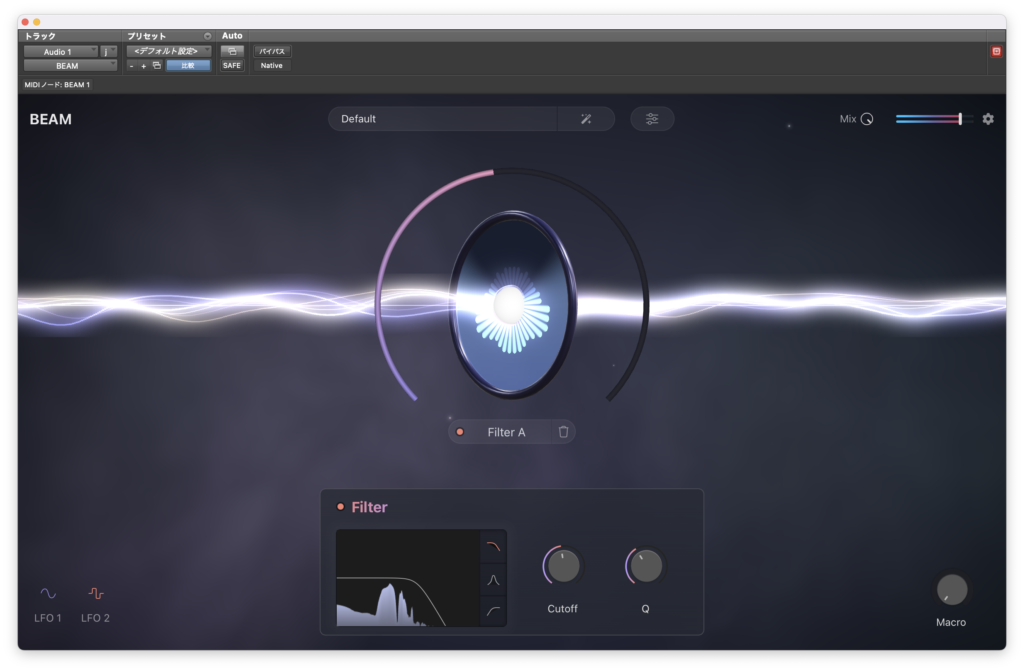
Filter部は比較的シンプルでローパス、バンドパス、ハイパスの3つのカーブがあるのみとなっています。
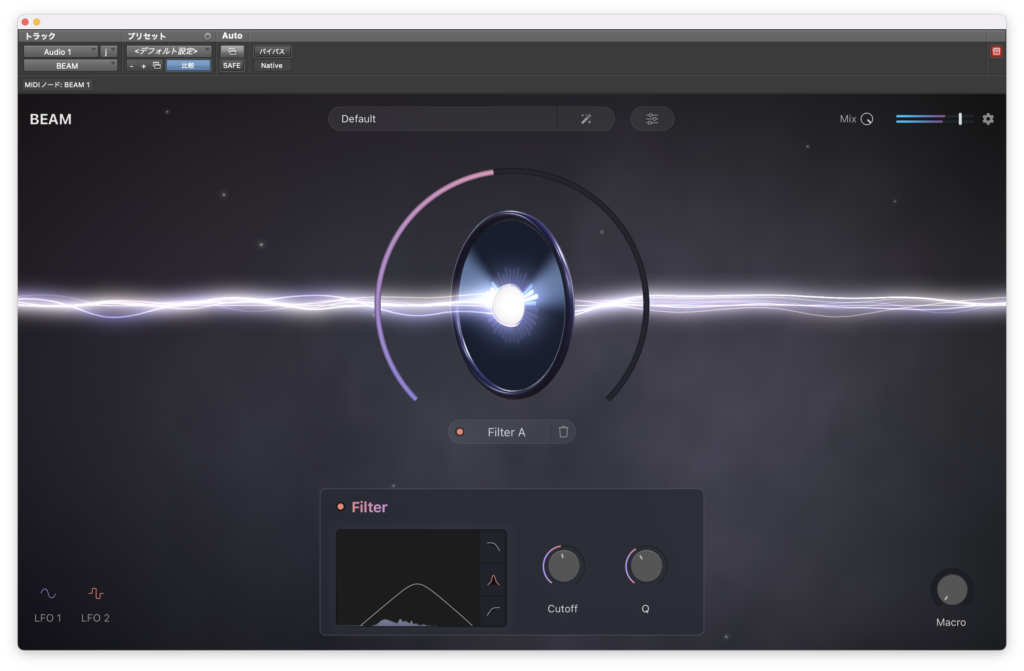
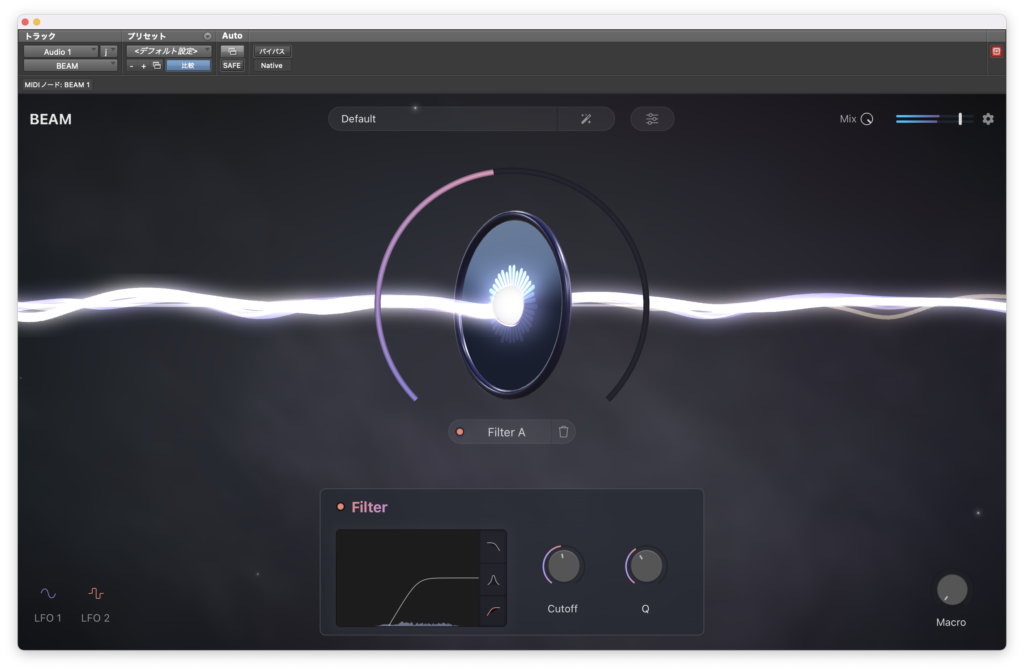
Cutoffで帯域を、Qでカーブの勾配(というかほぼレゾナンス)を調整します。
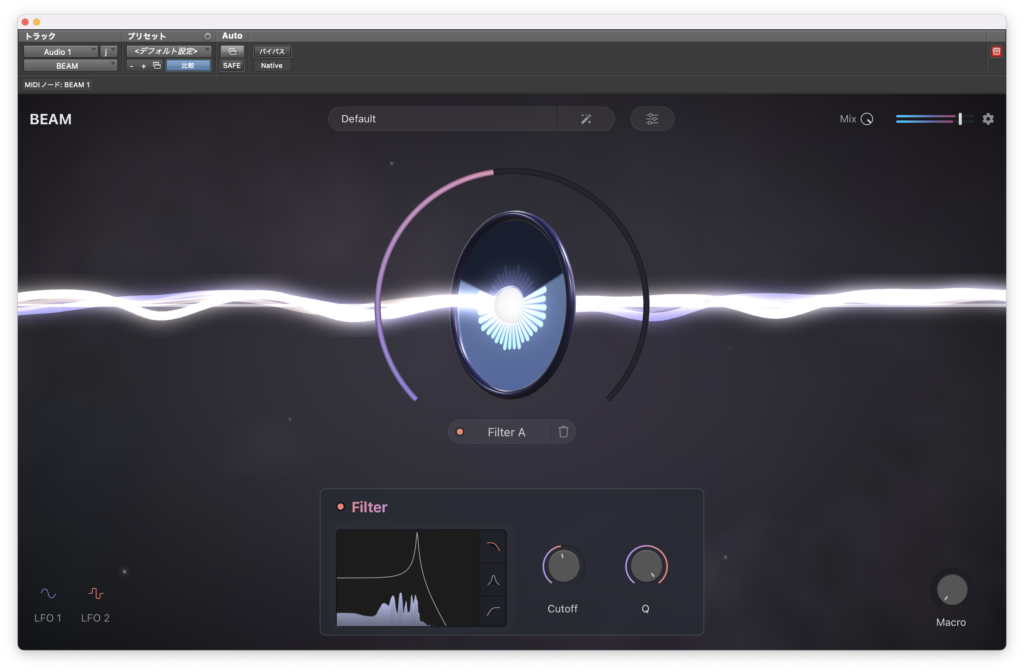
Path
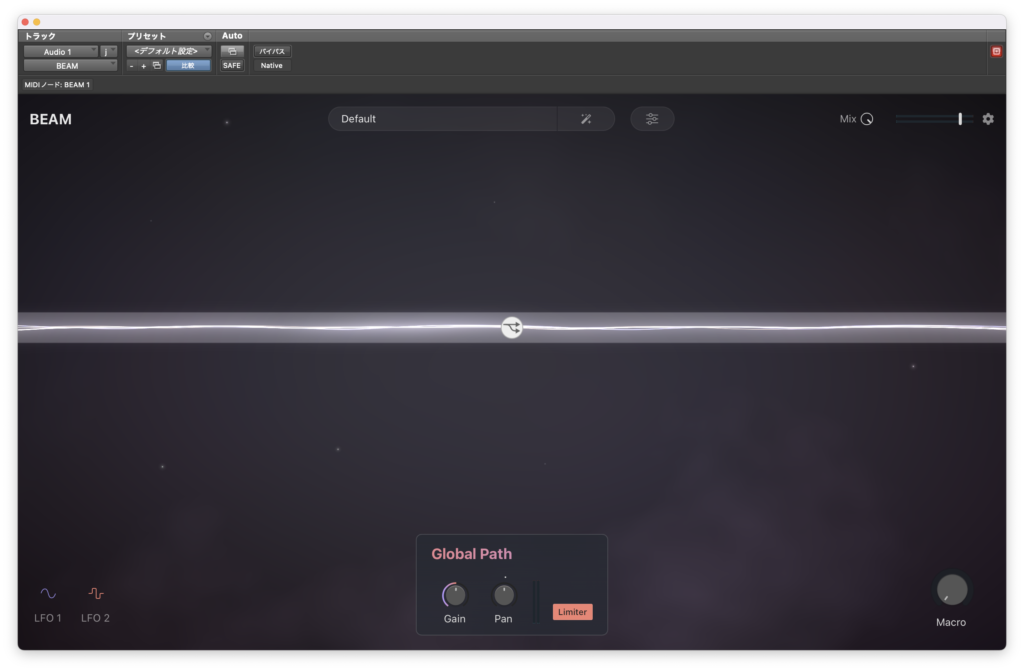
何もないところにはGainとPanを設定することができます。
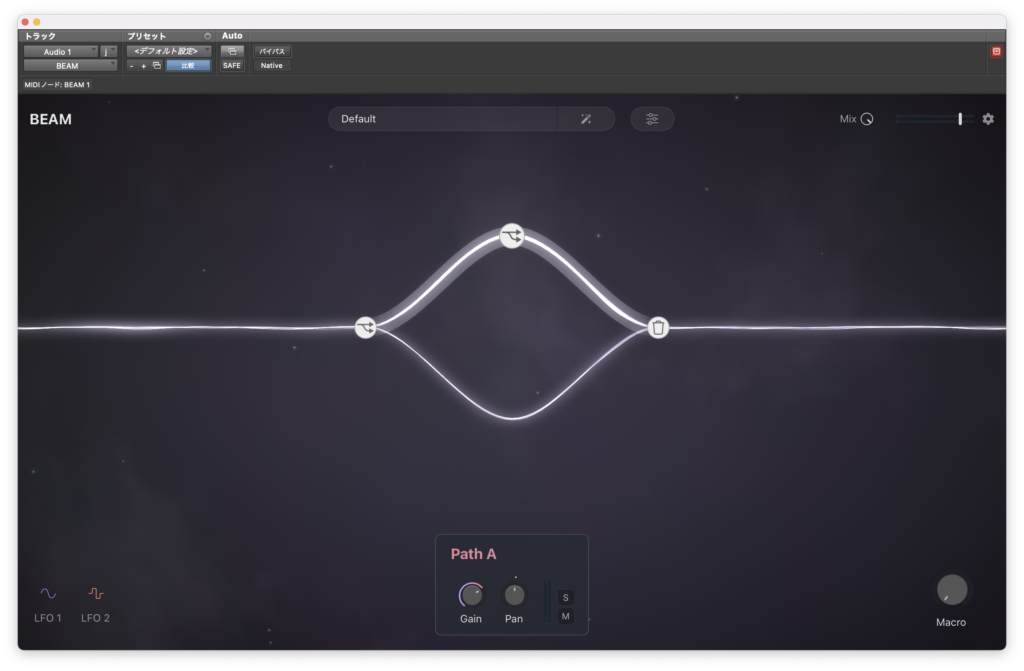
分岐を作るとPath Aのように文字が割り振られます。
LFO

LFOが二つ用意されており、48種類のカーブが選べるほか、Phase、Random、Smoothによる調整ができるようになっています。
プリセット
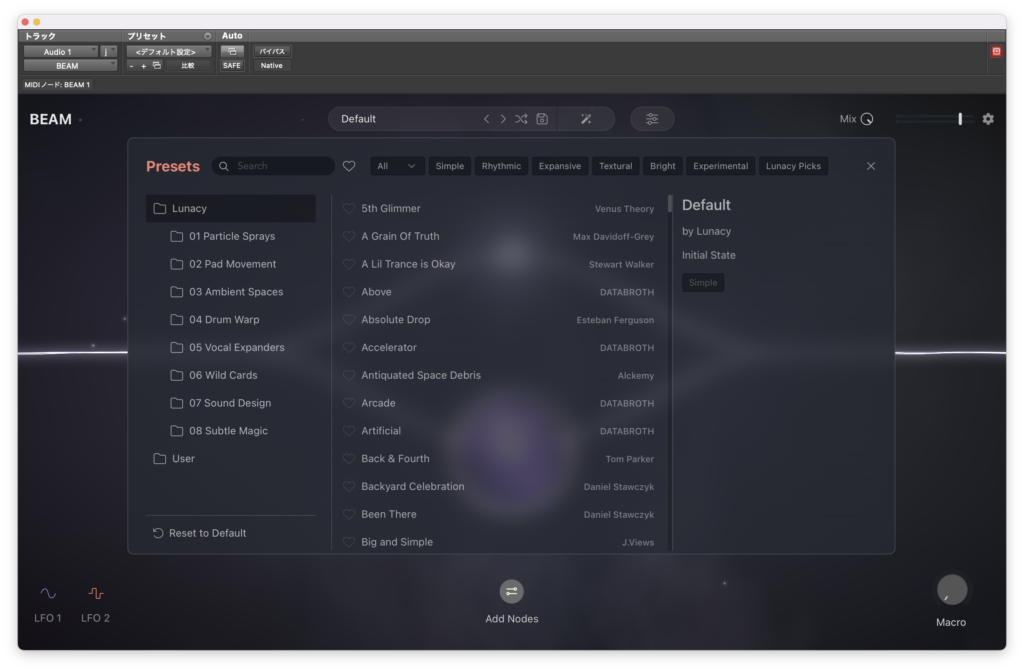
ここからはプリセットを試していこうと思います。
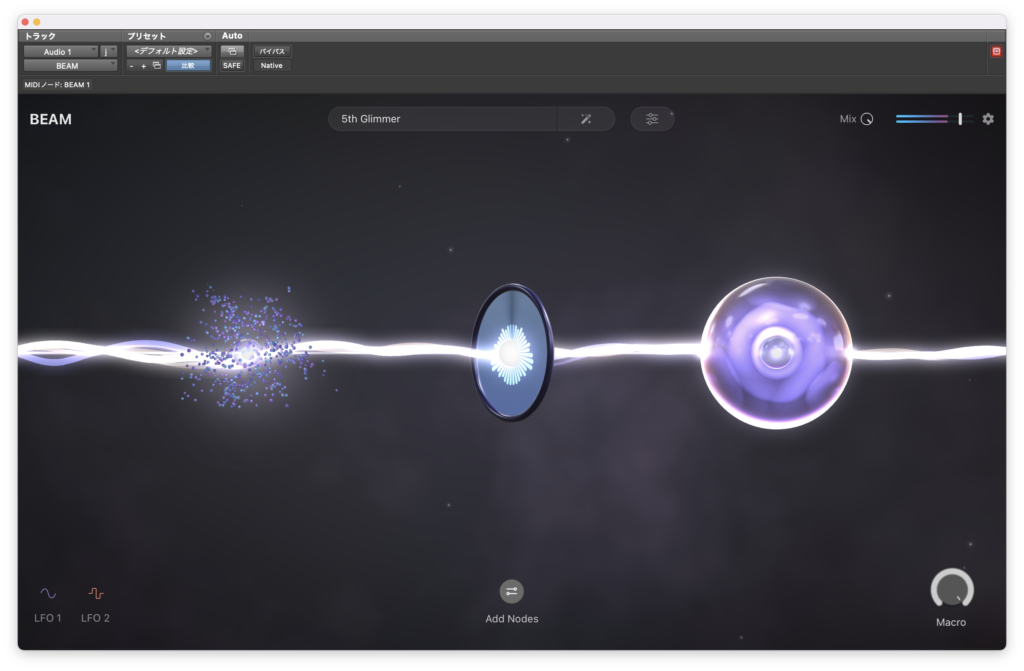
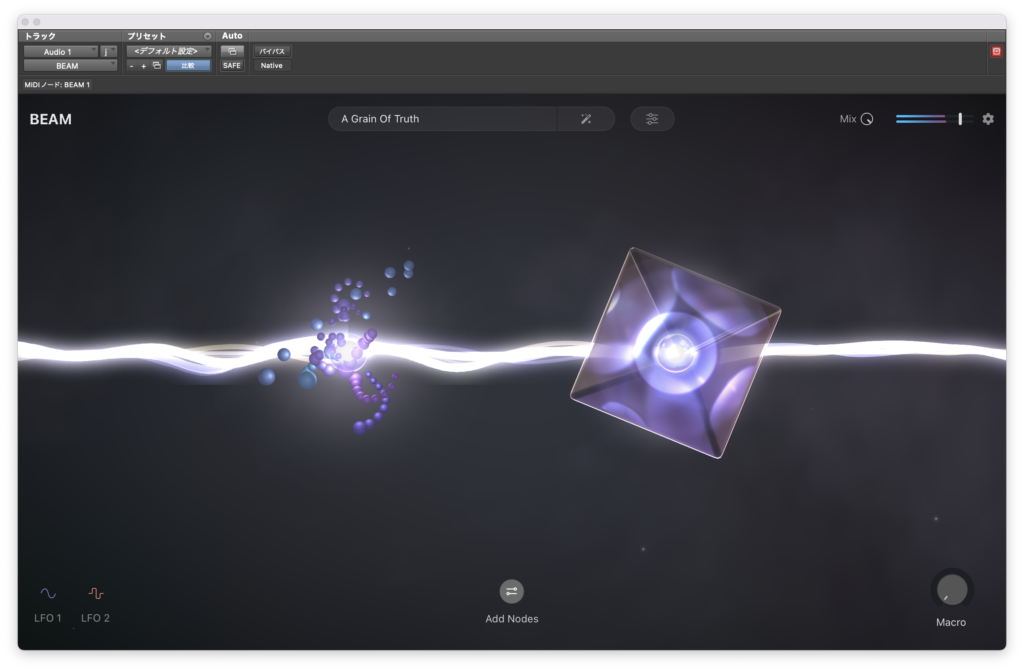
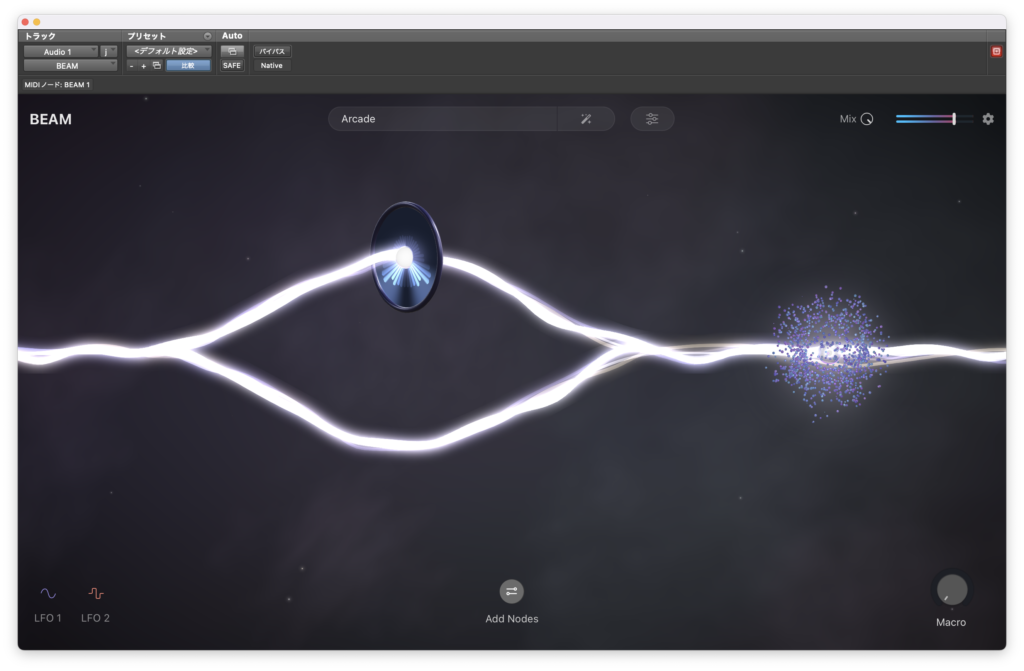
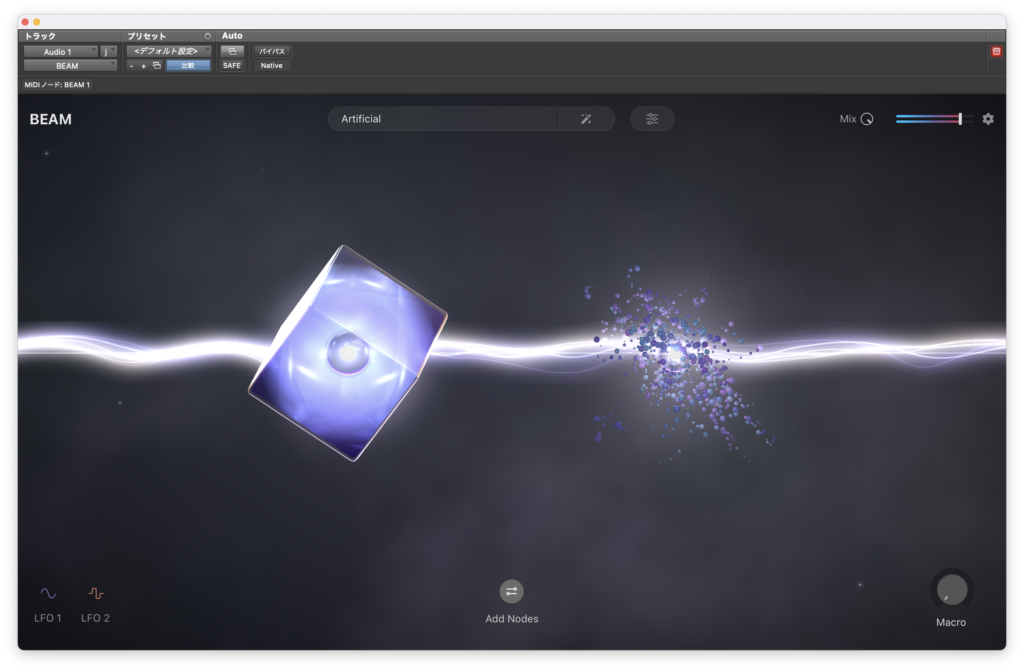
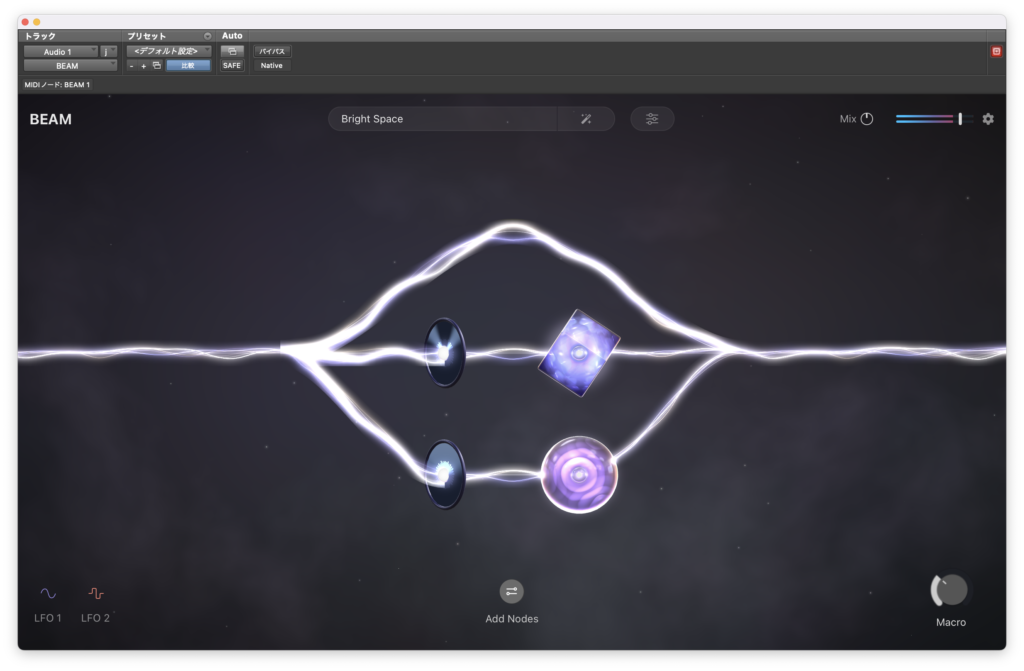
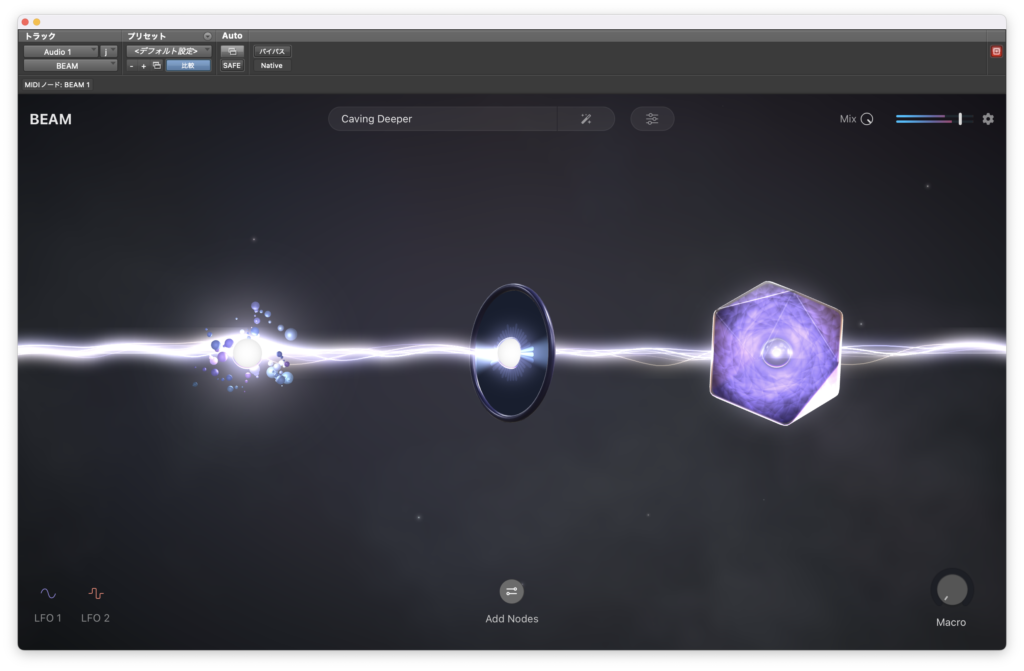
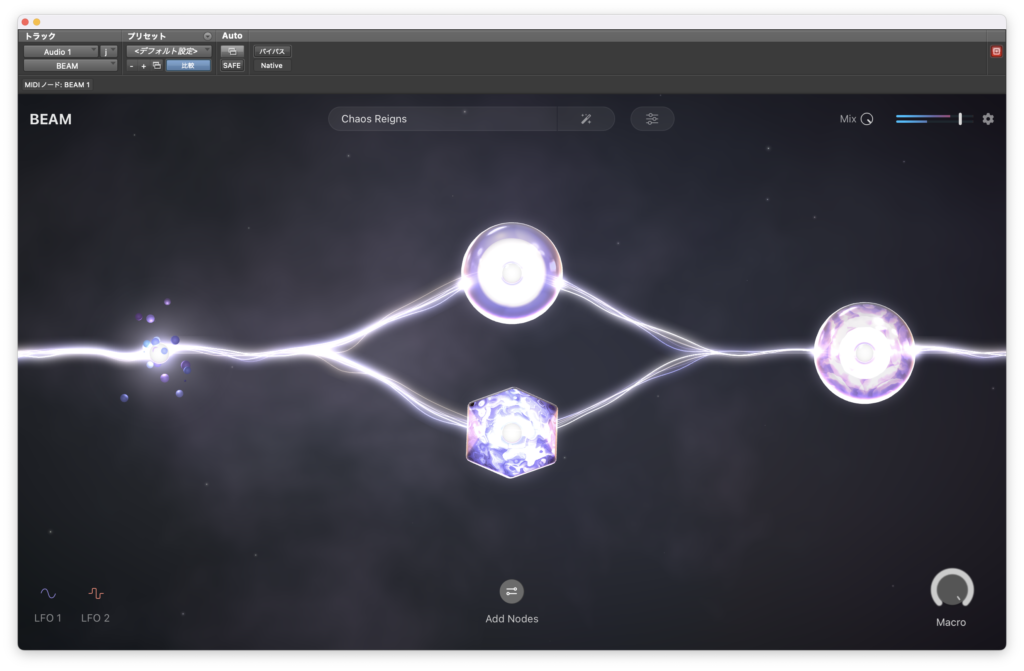
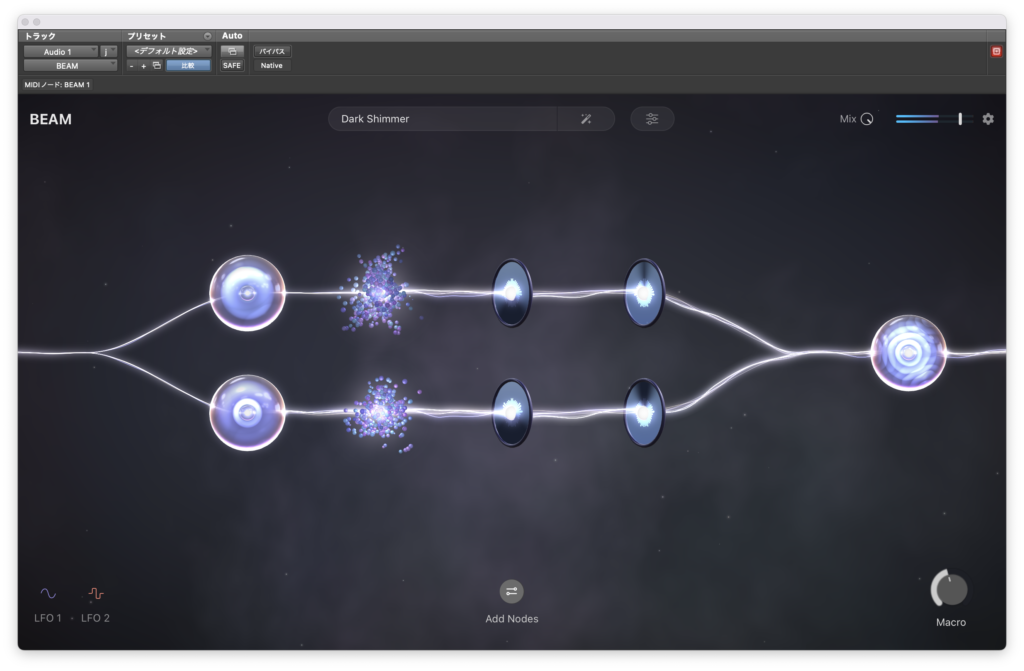
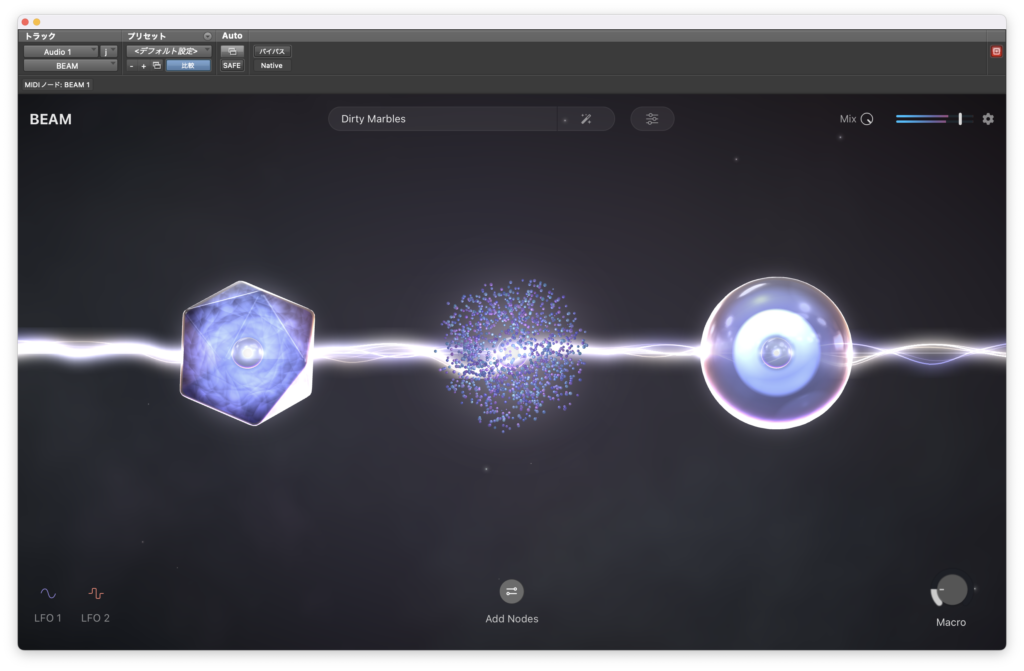
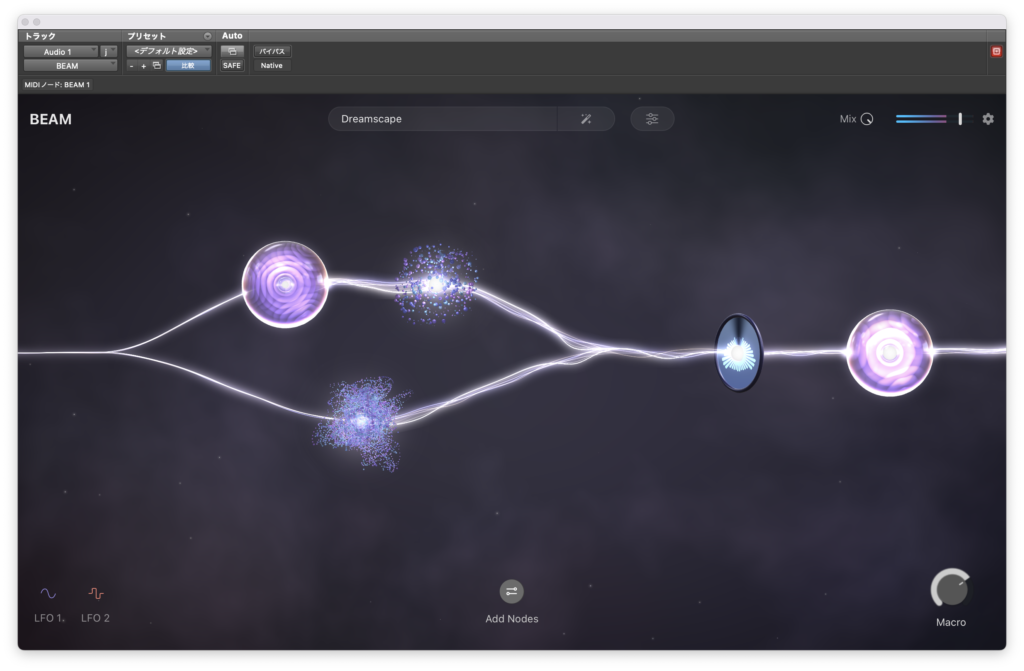
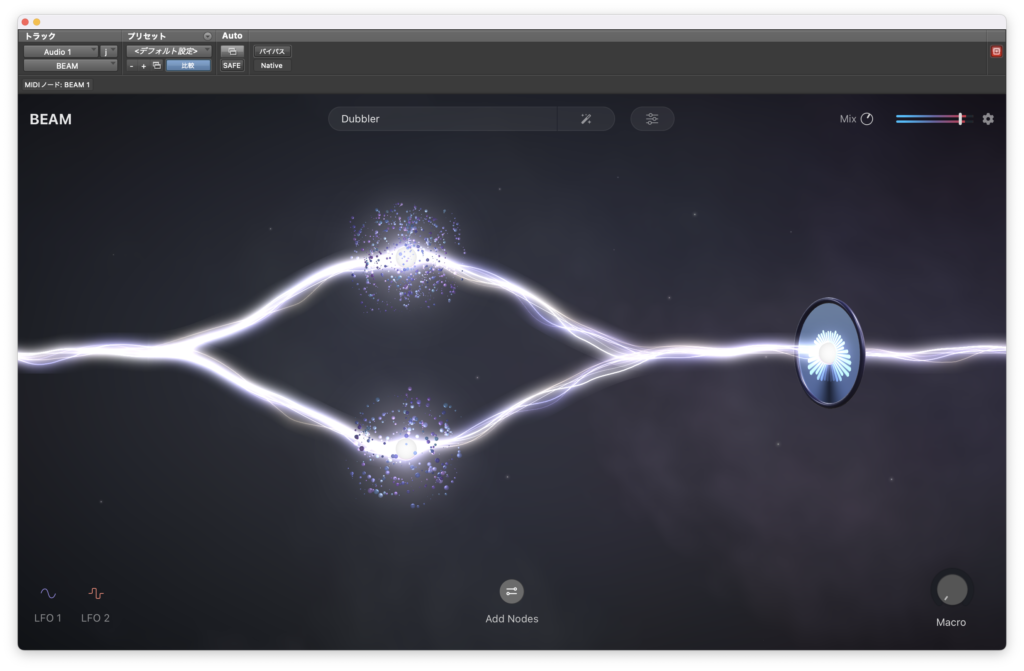
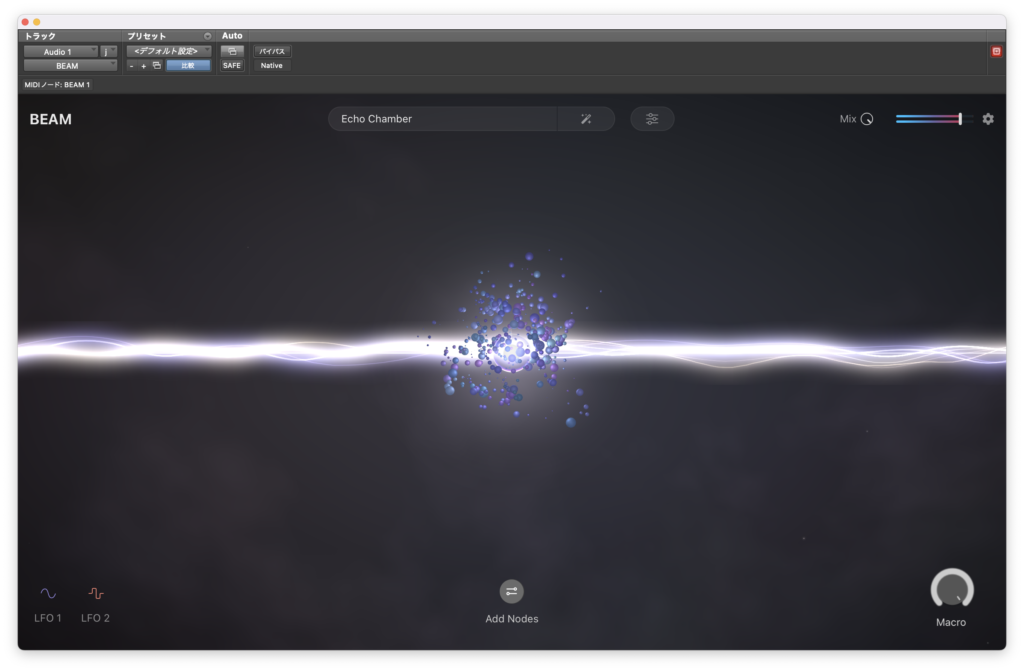
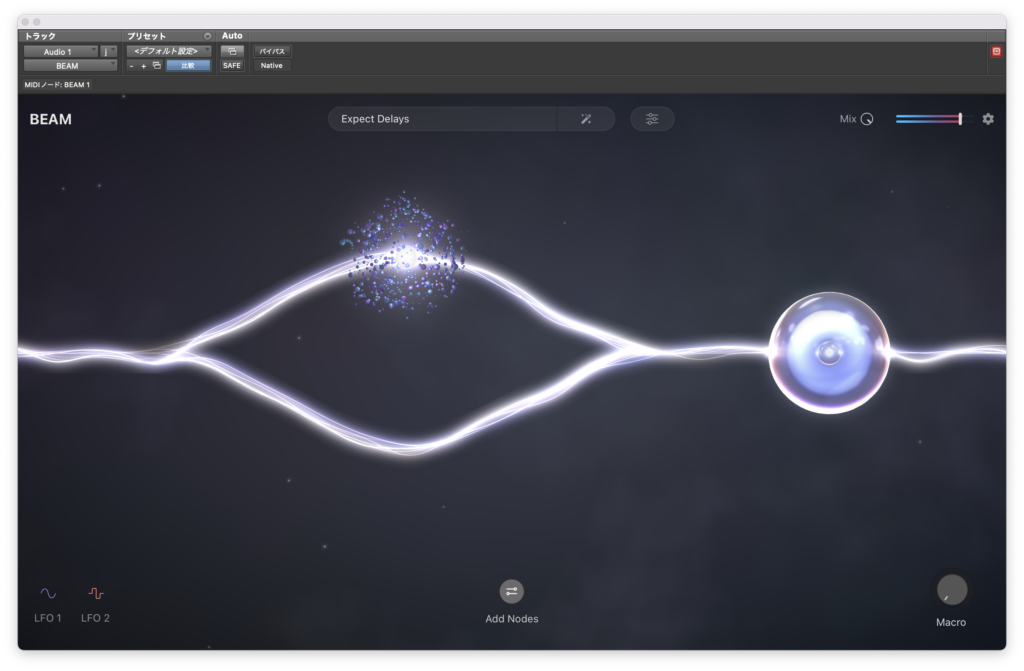
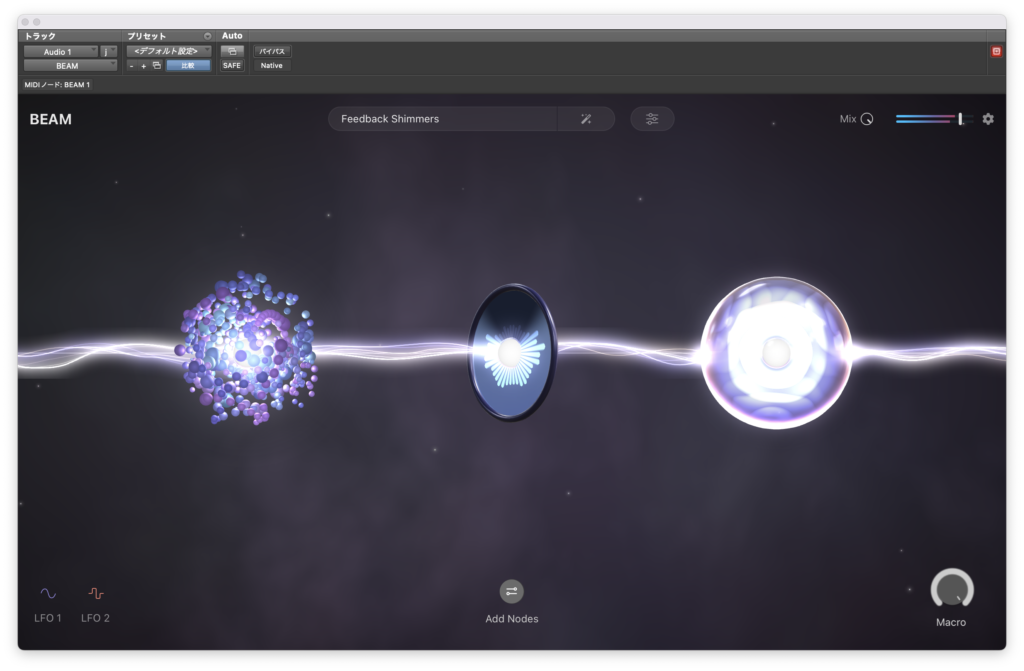
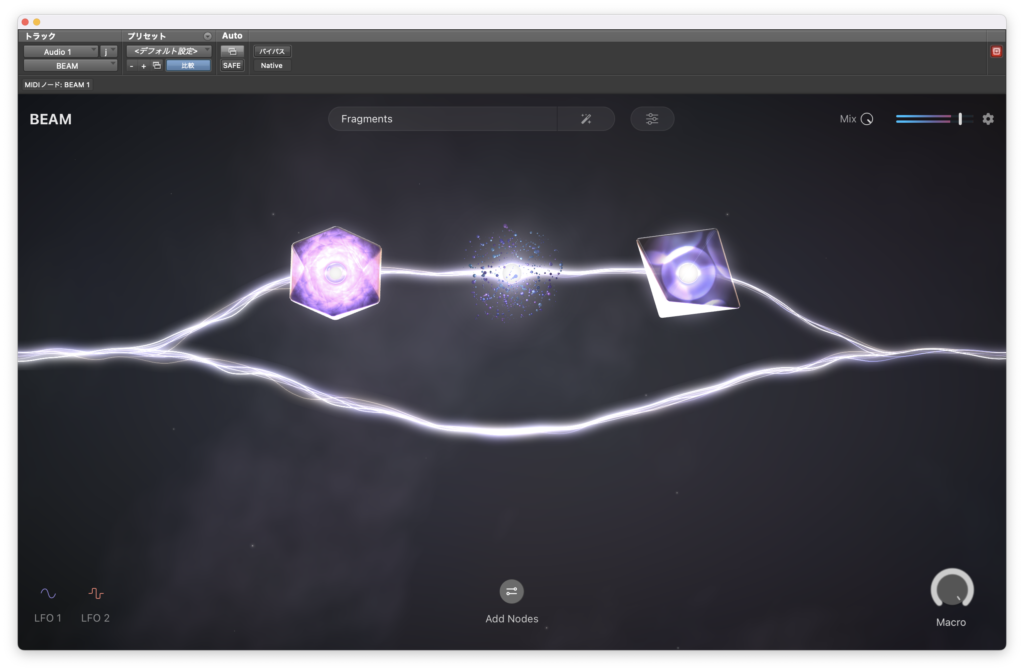
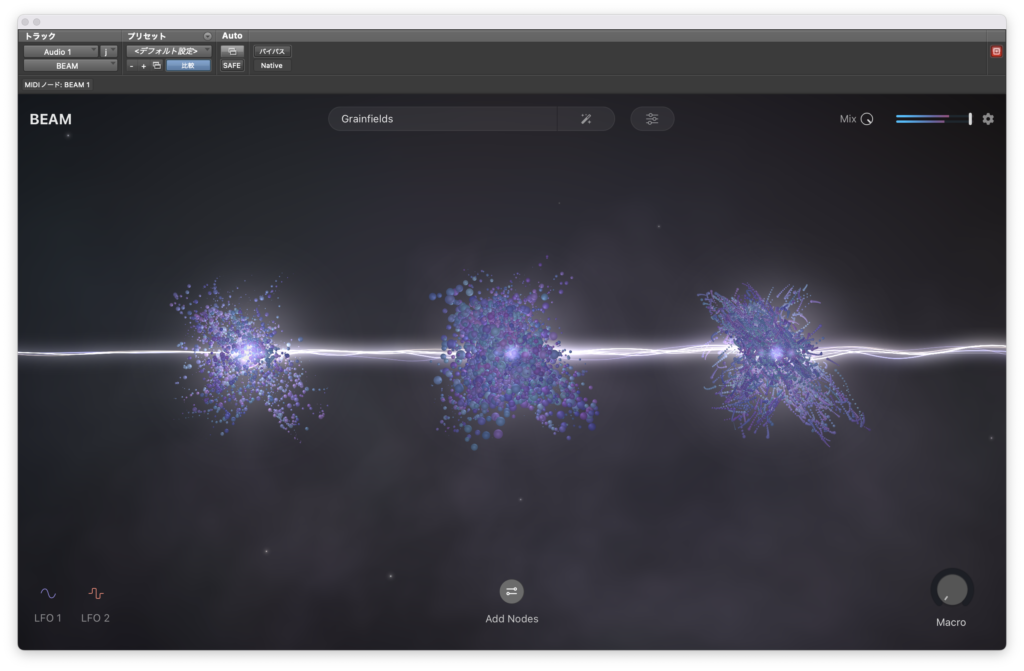
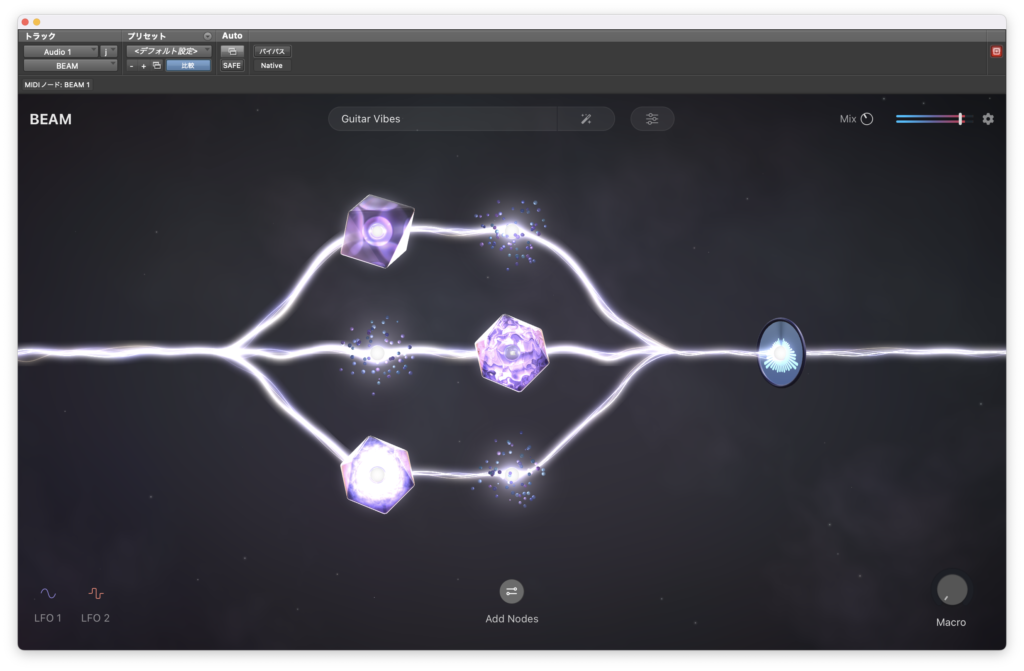
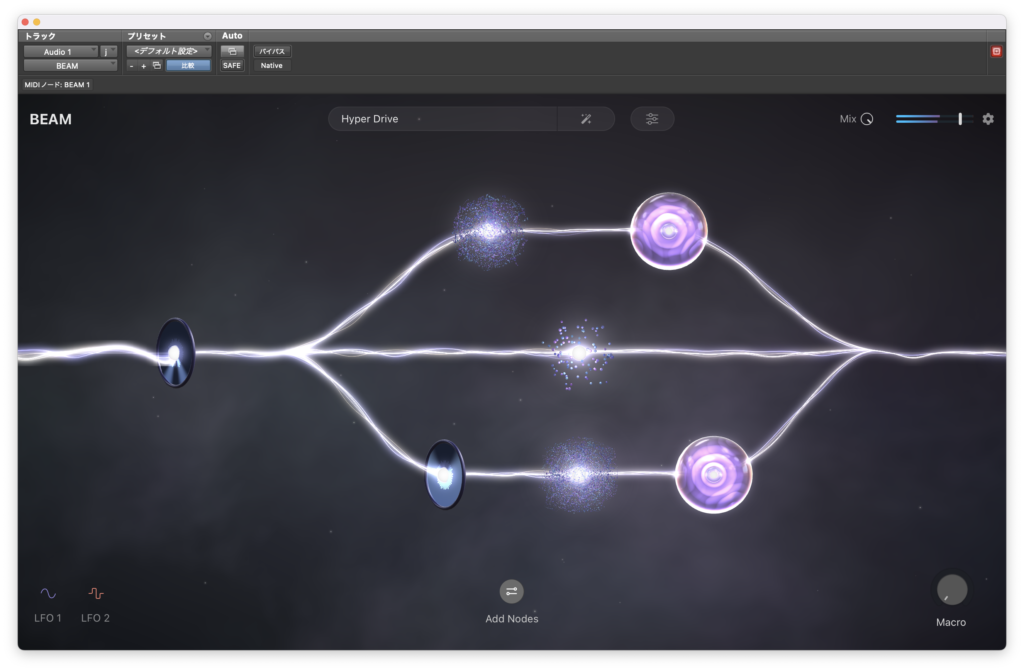
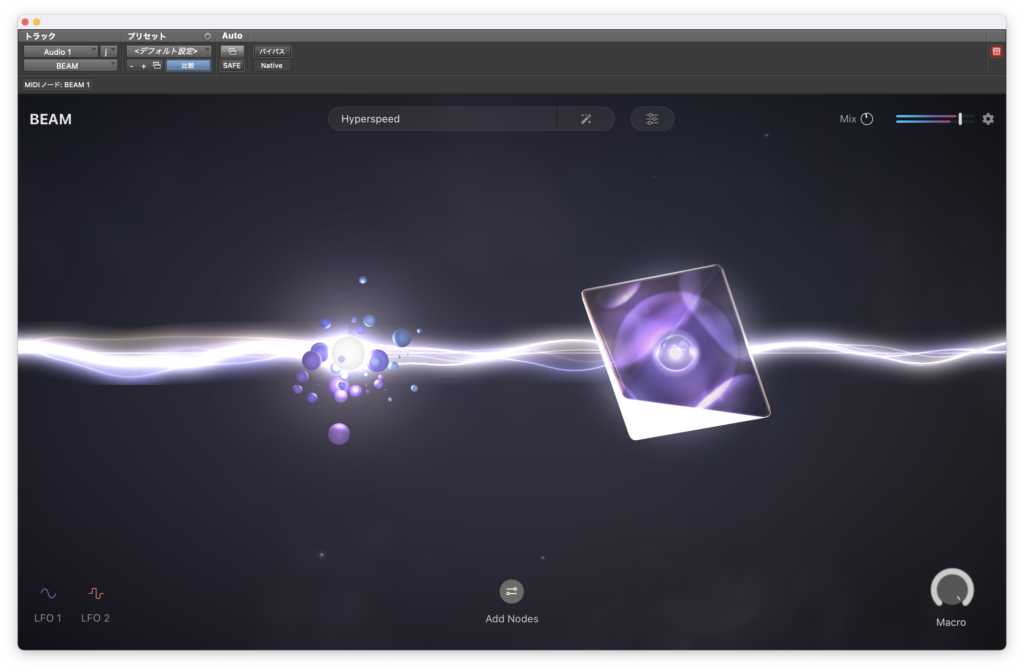

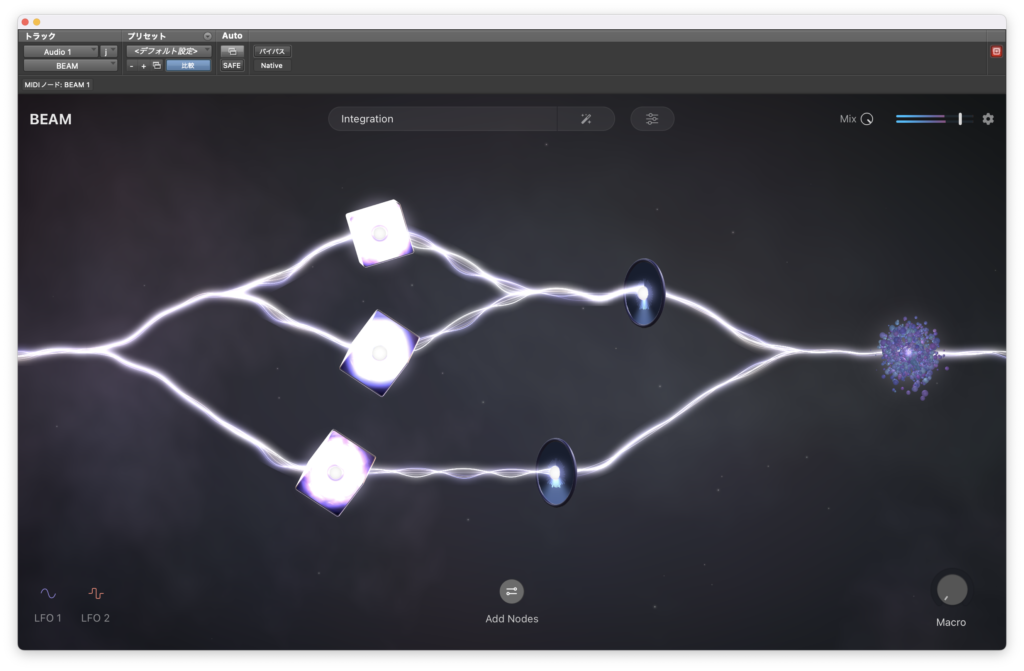
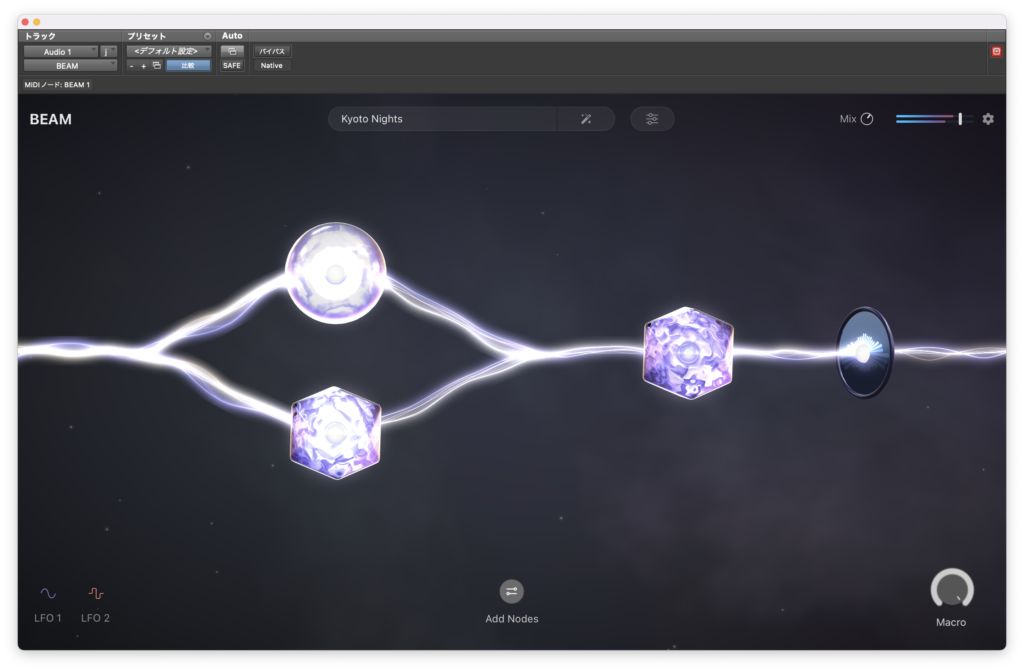
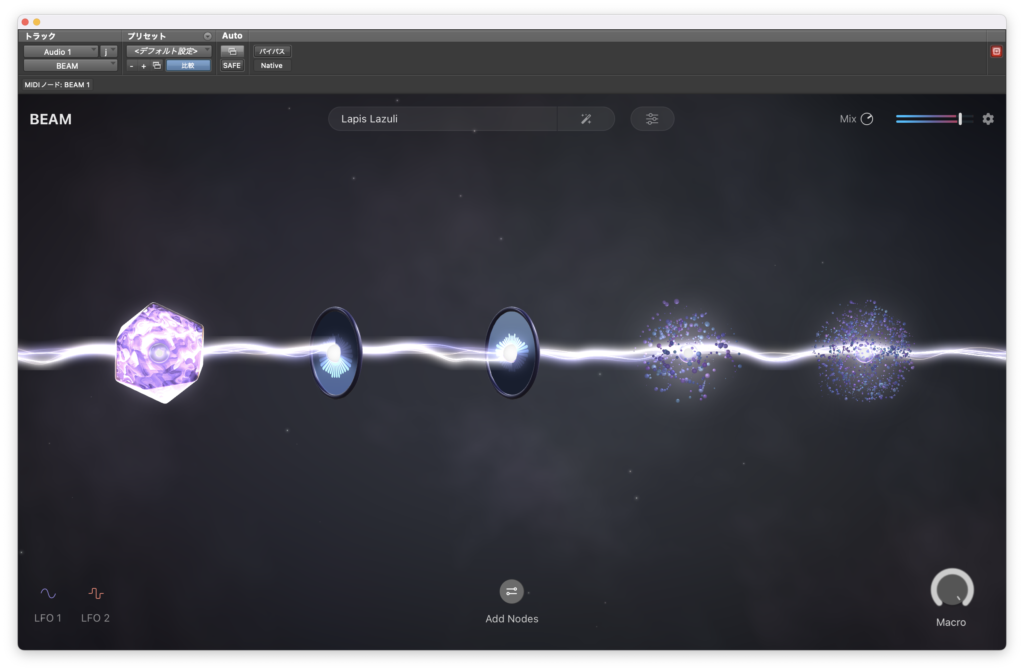
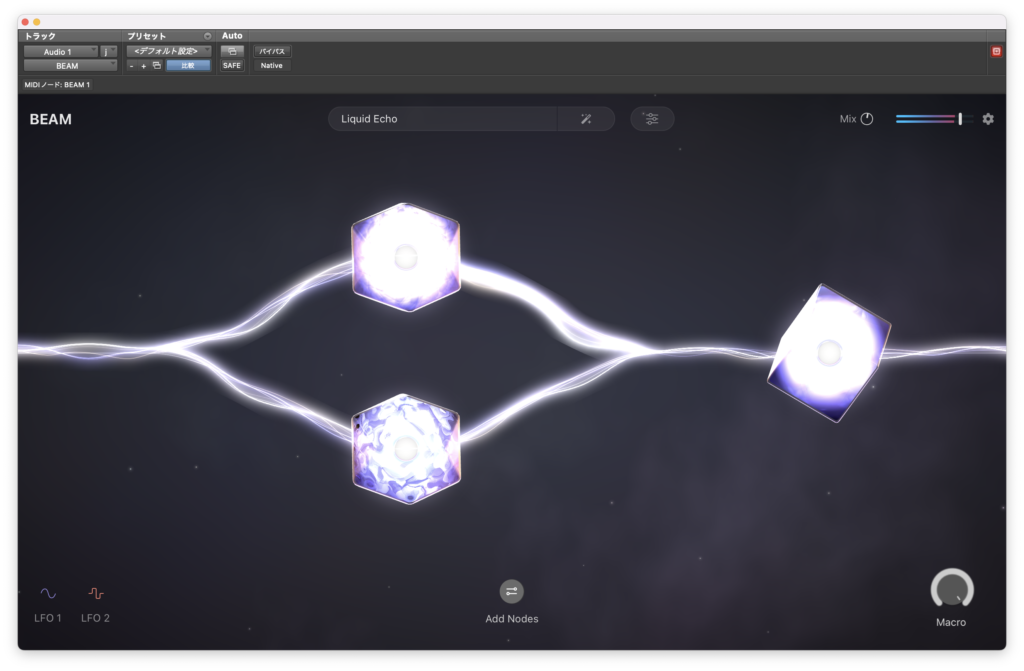
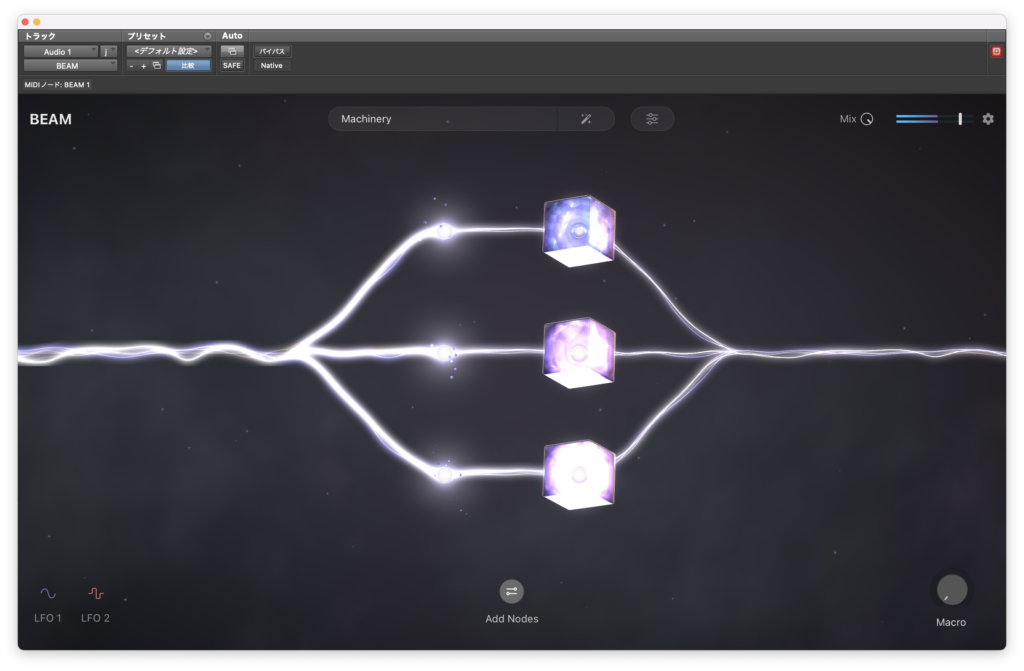
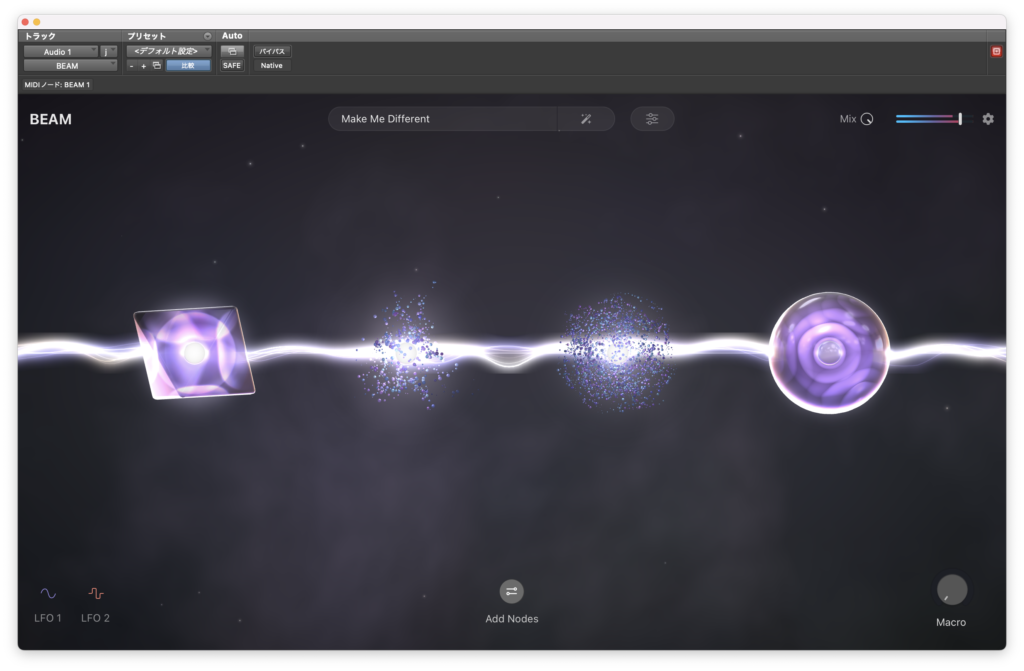
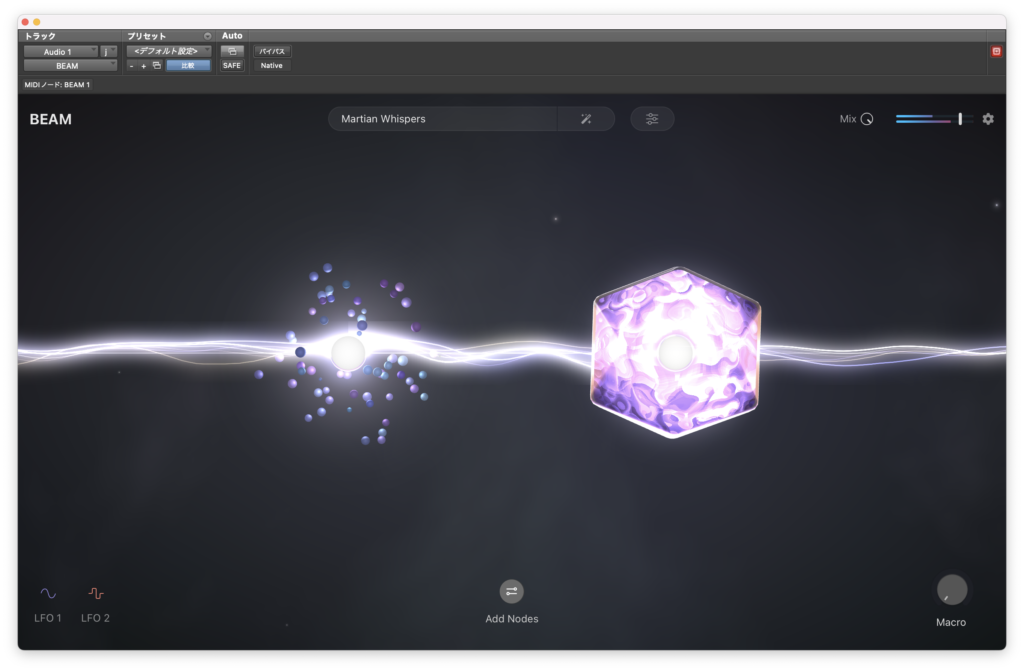
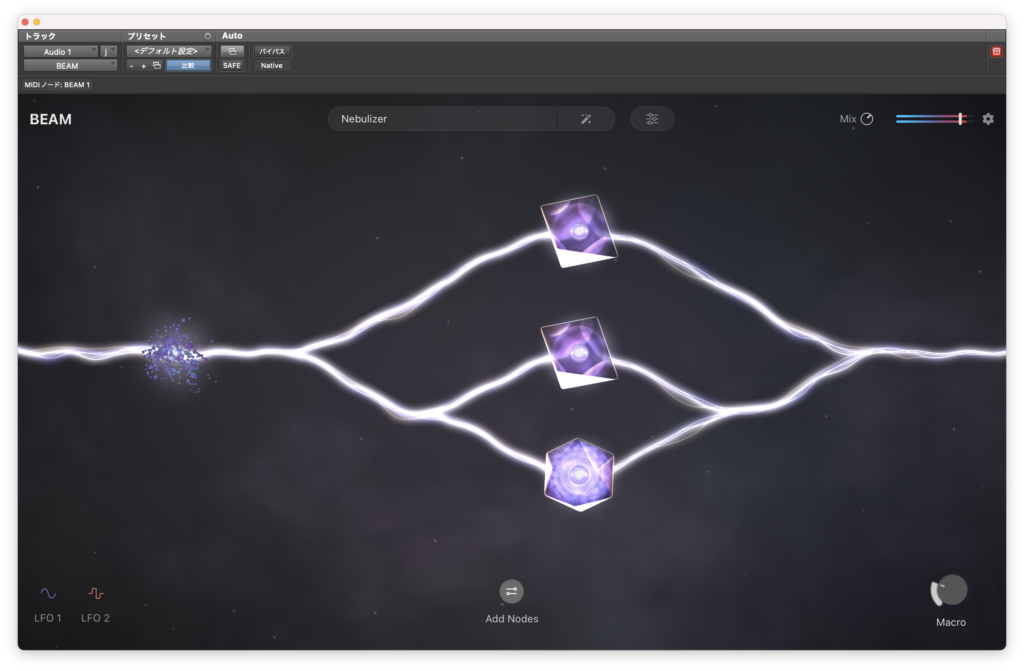
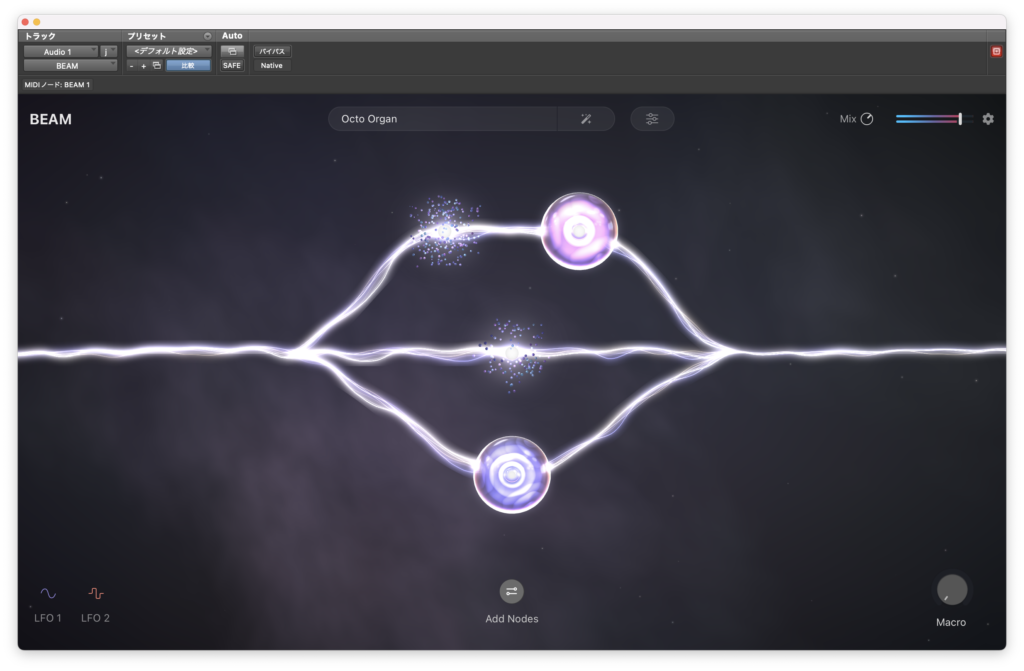
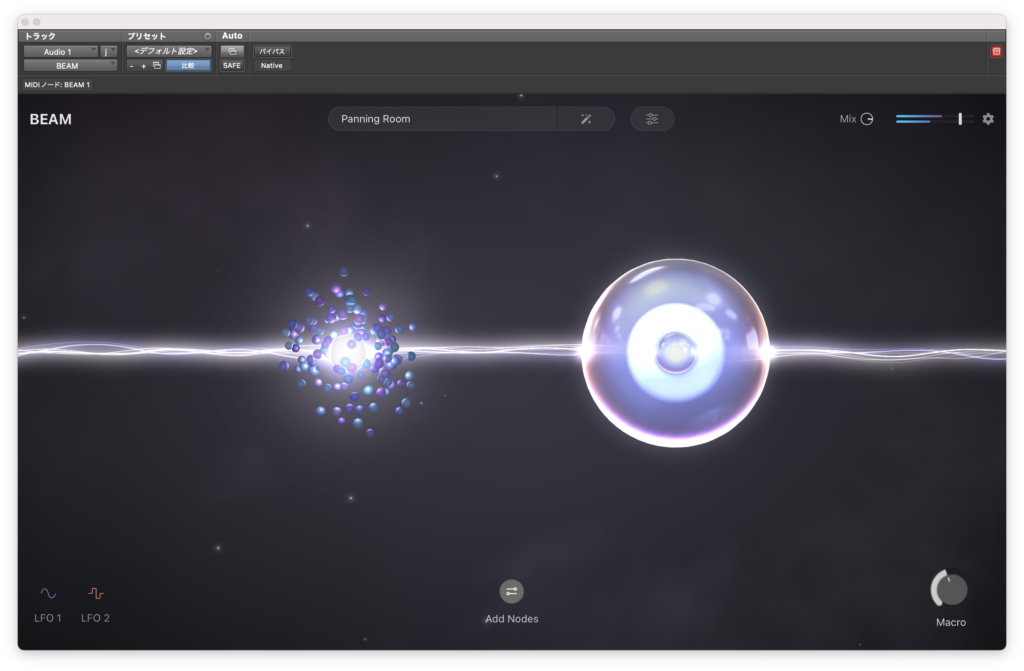
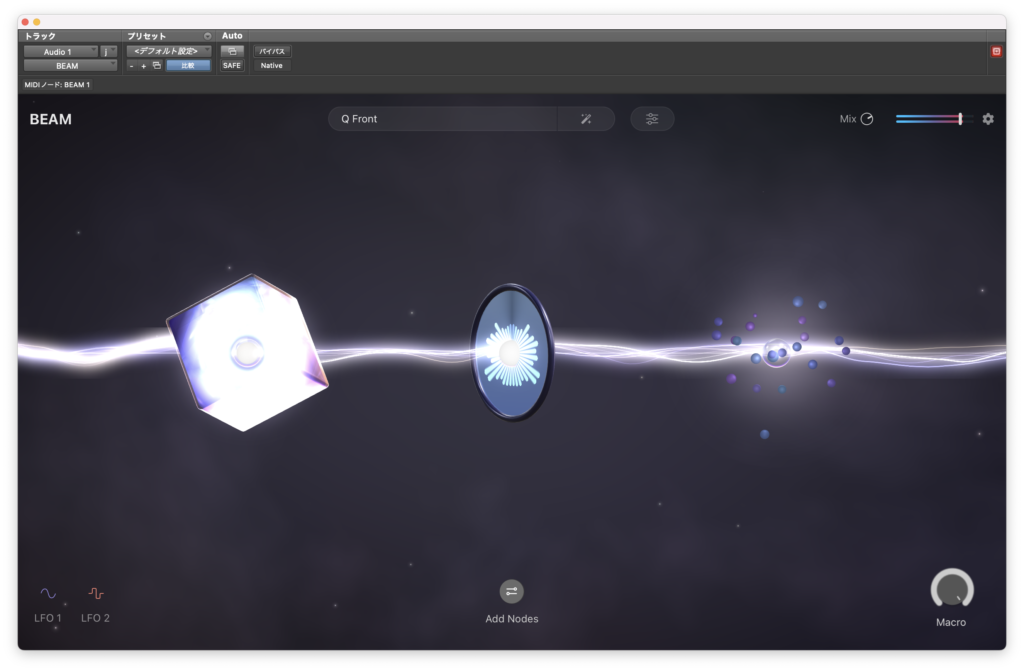
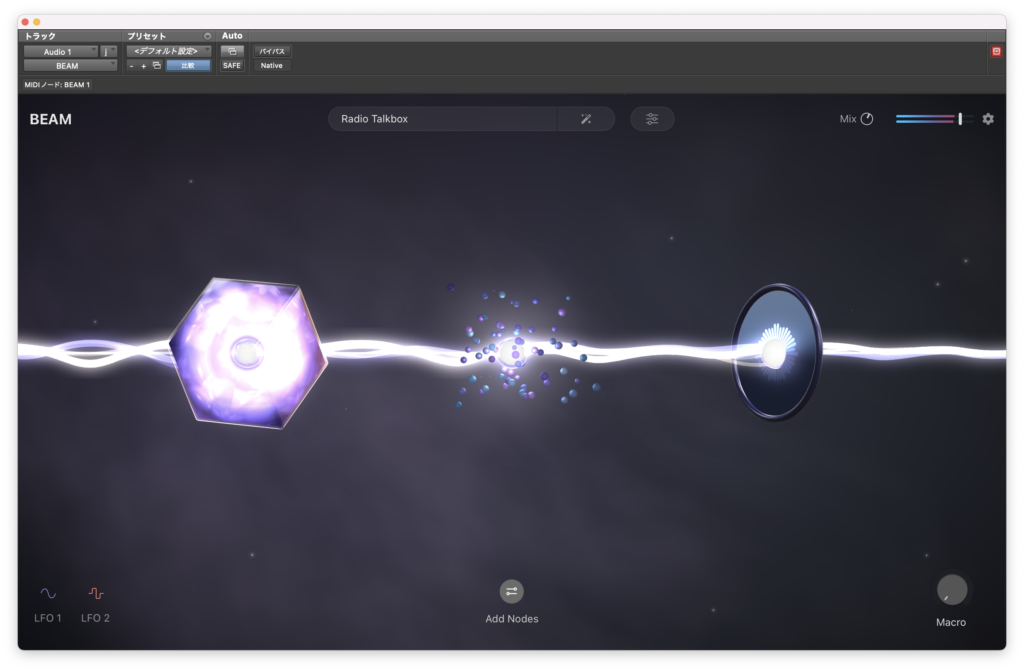
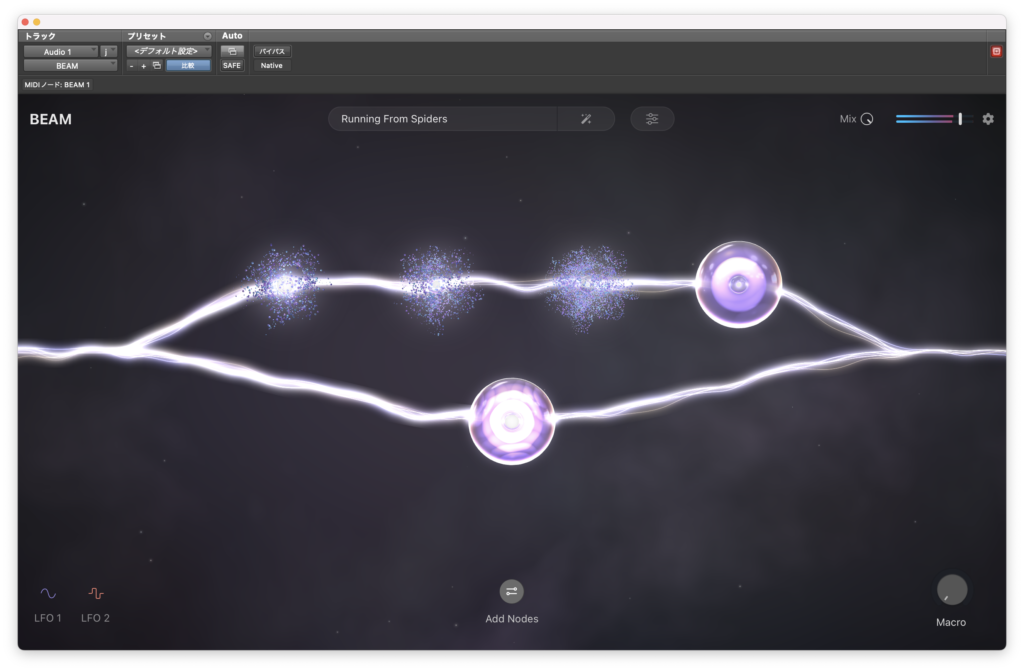
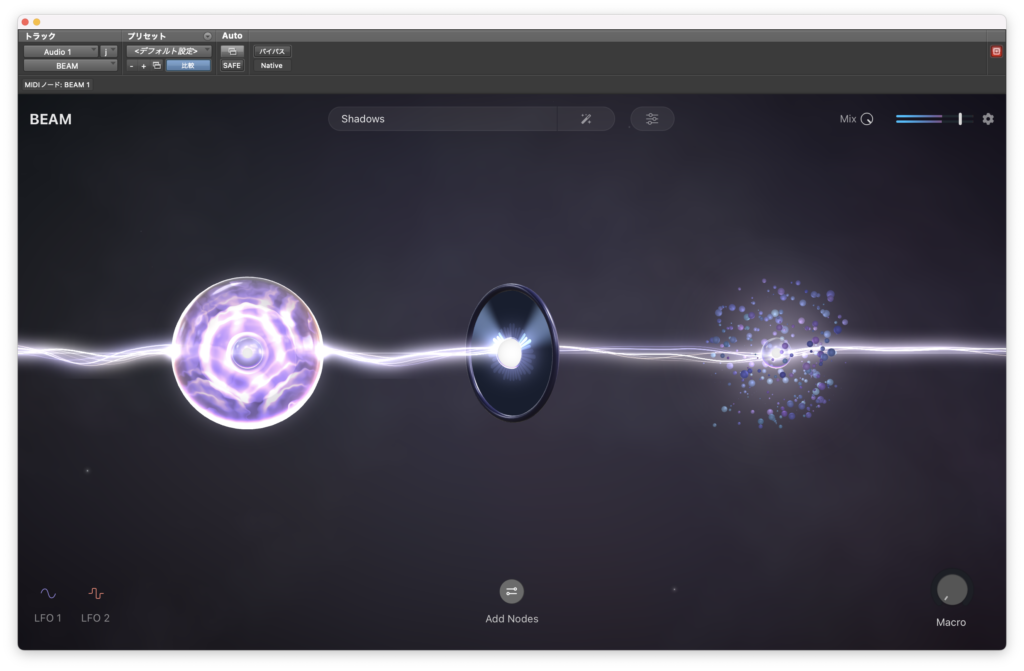
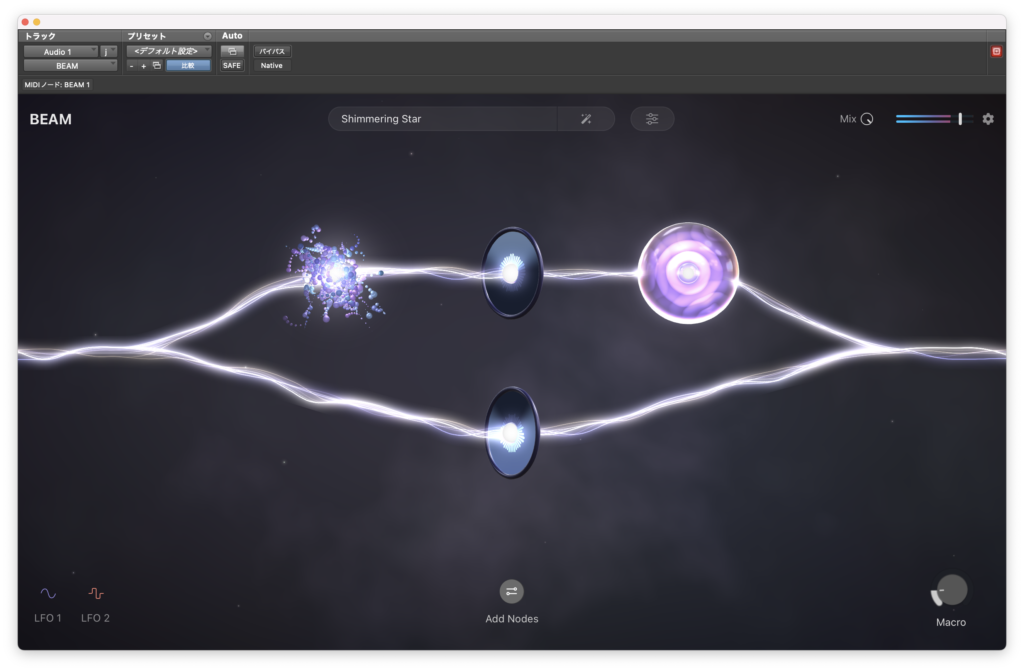
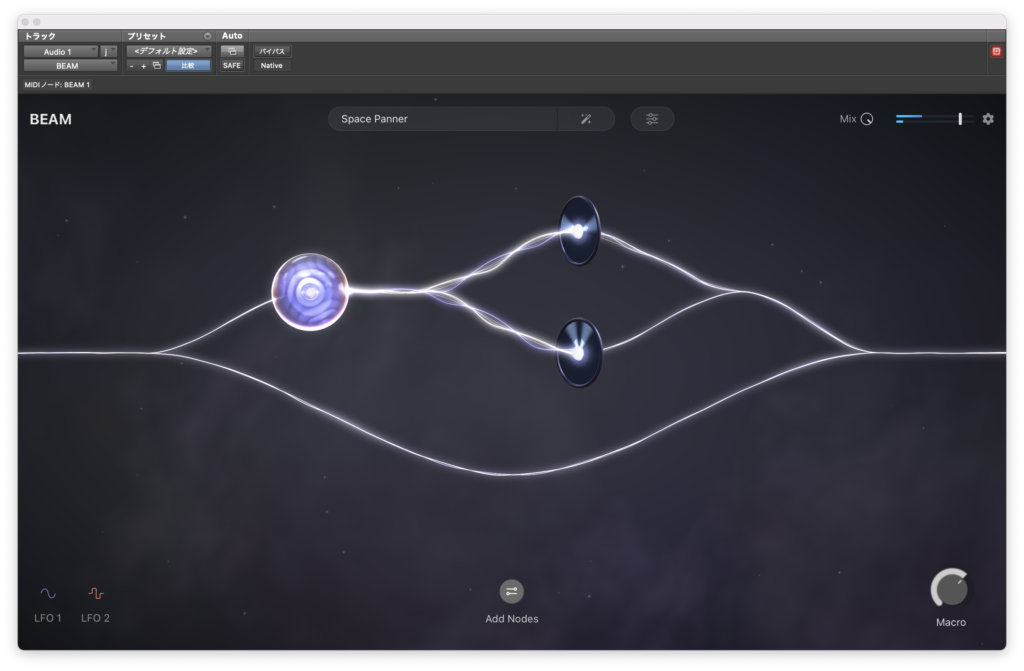
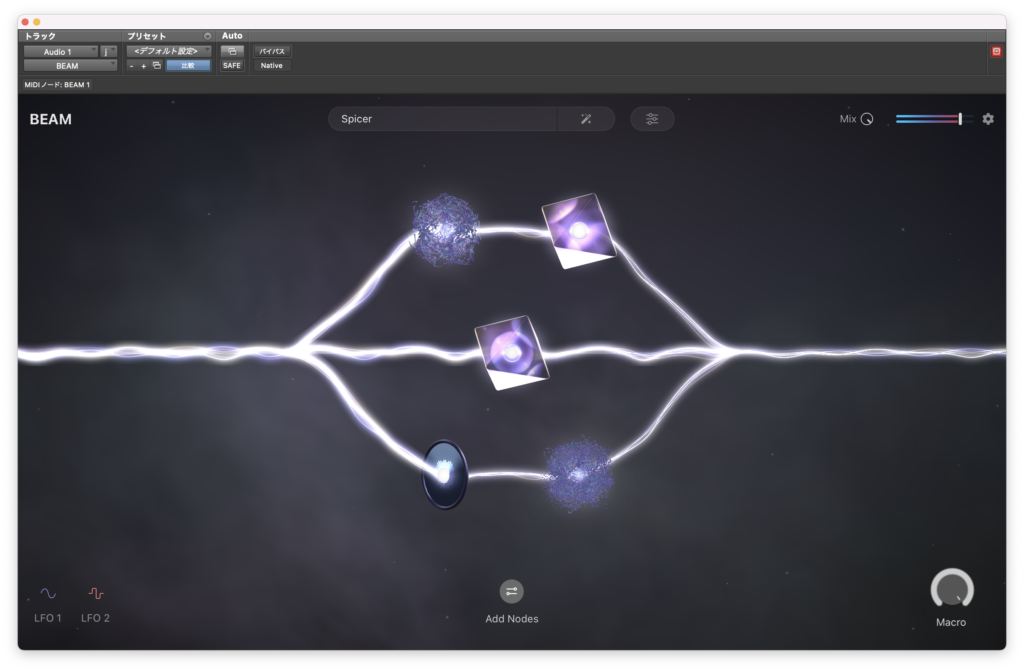
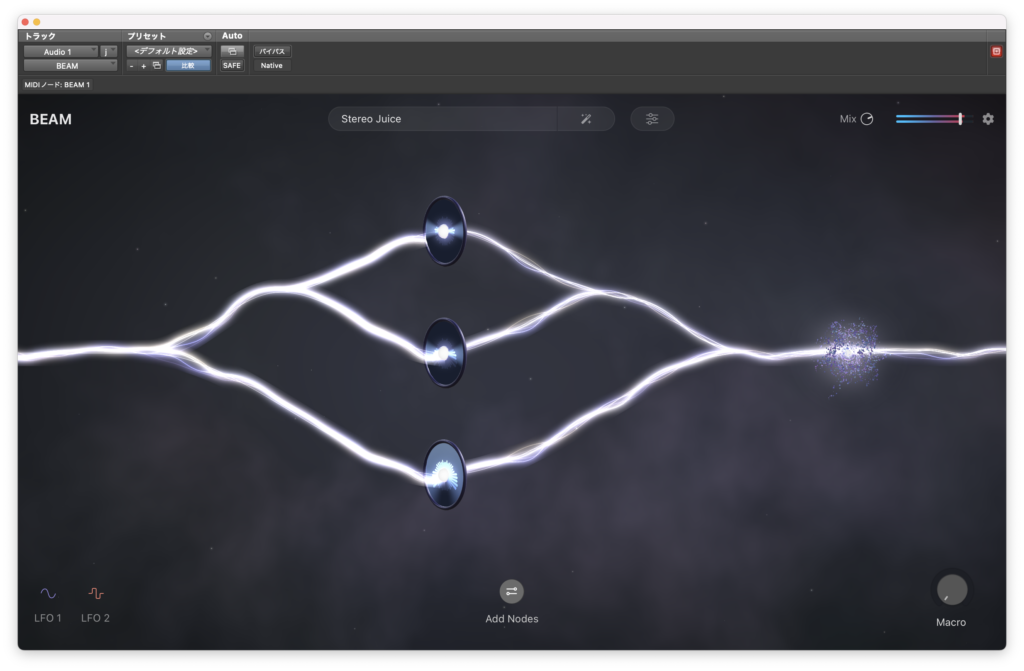
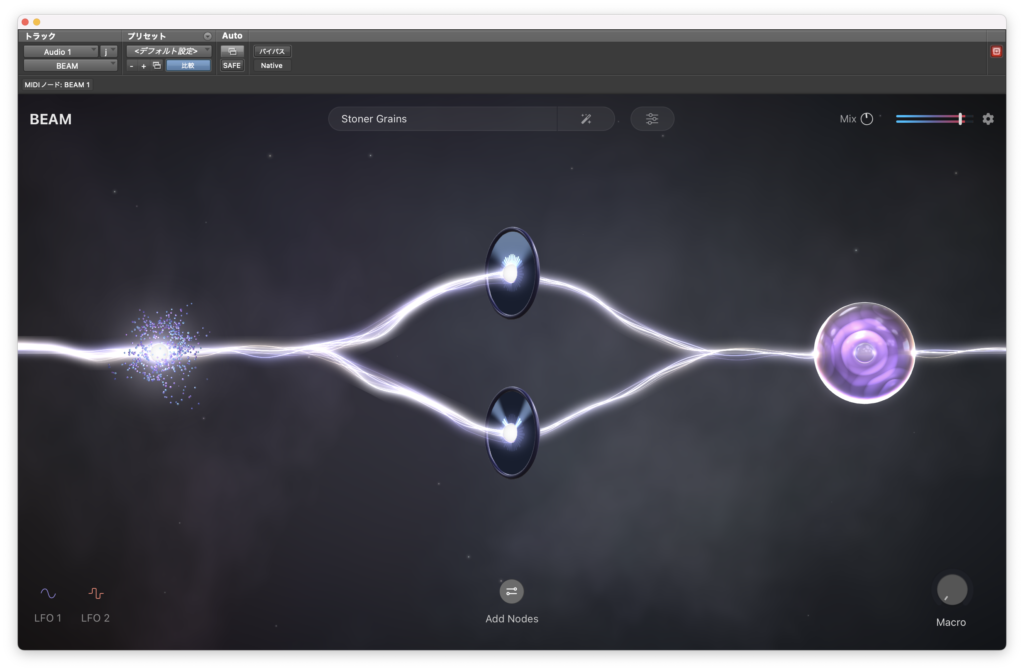
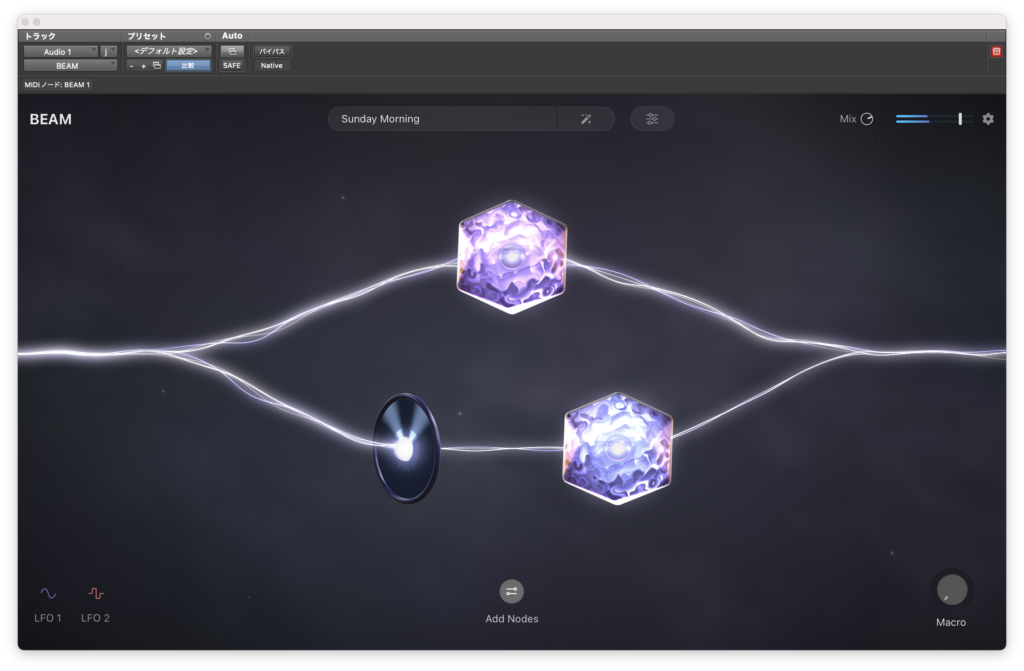
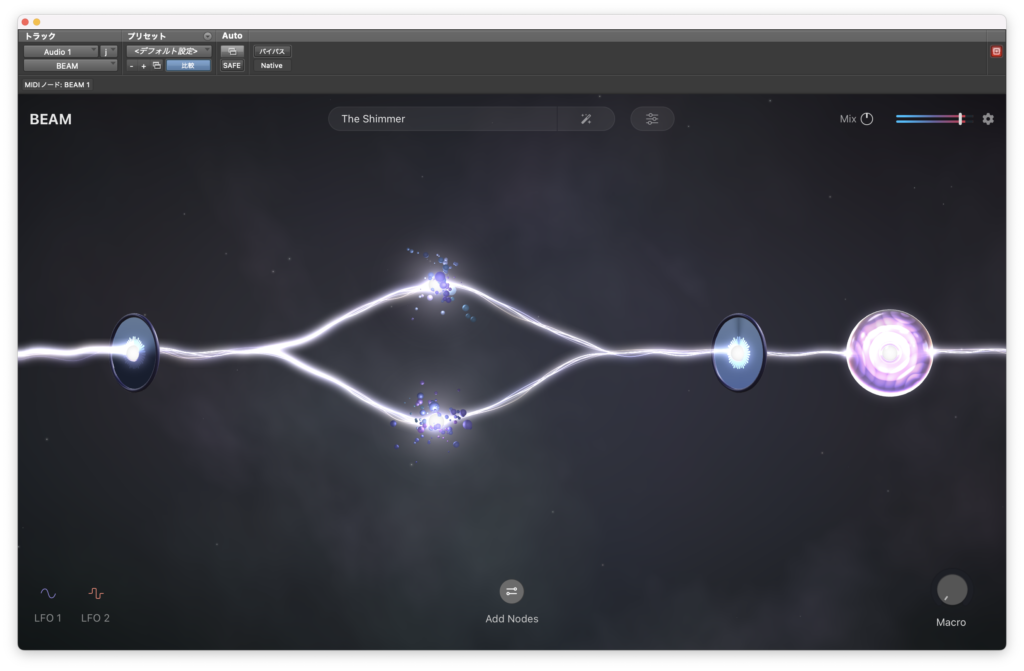
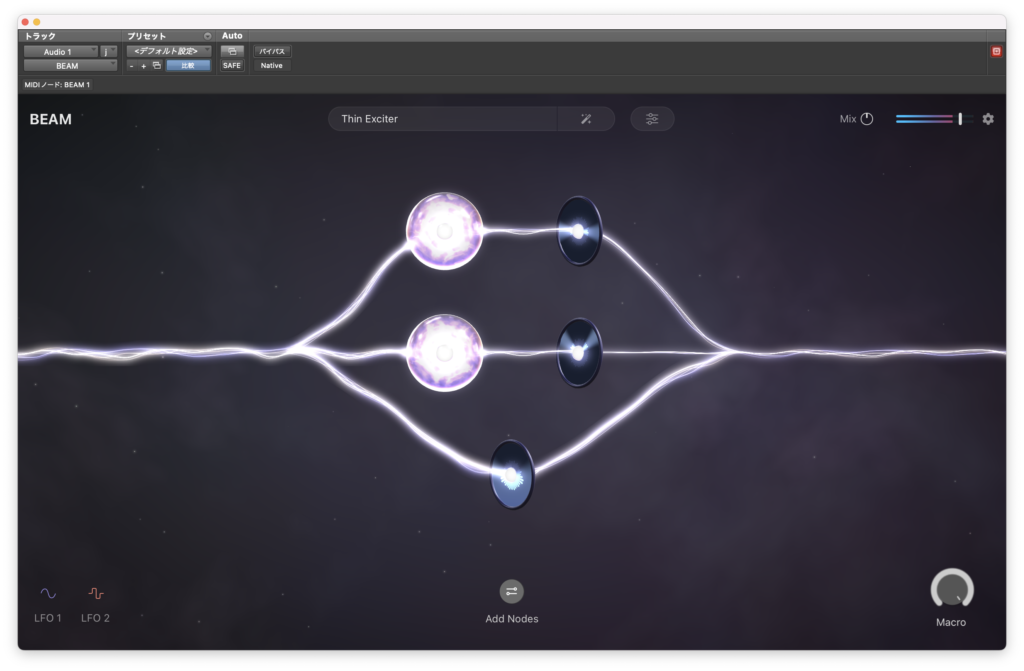
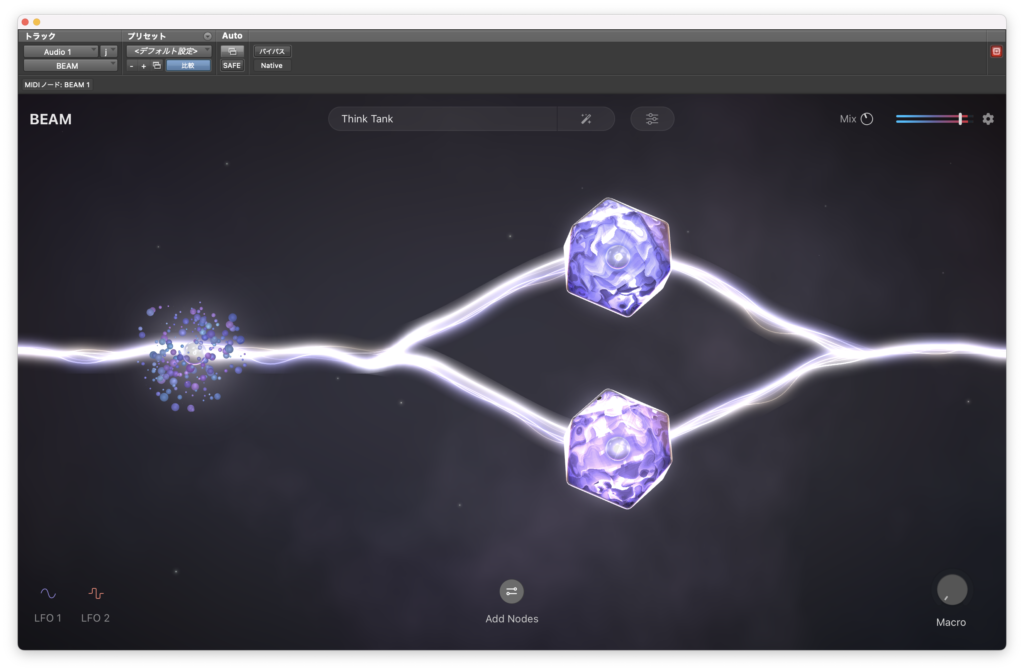
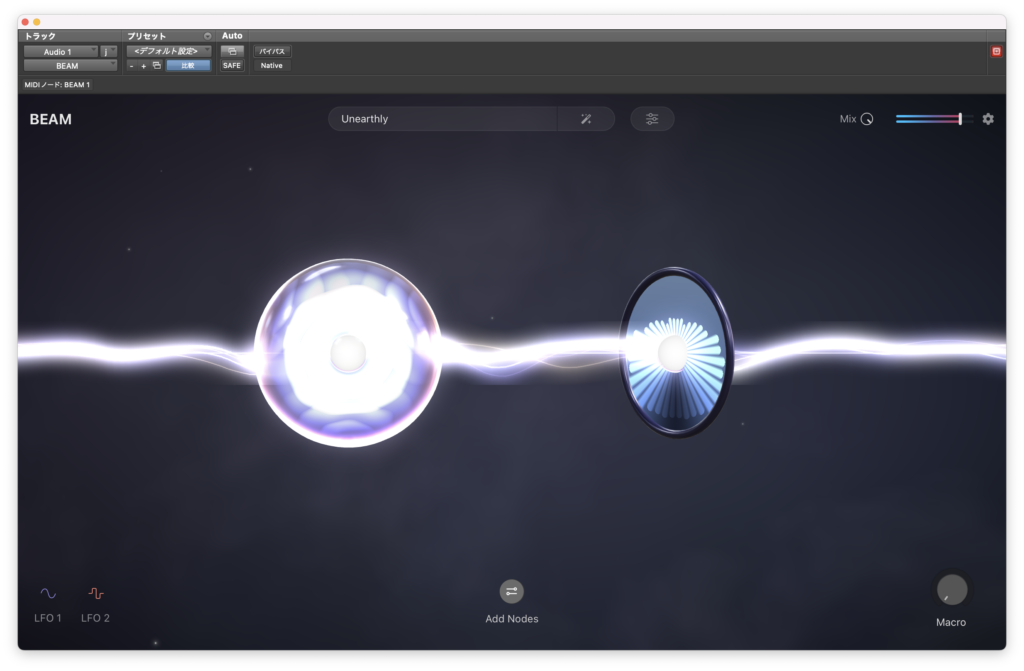
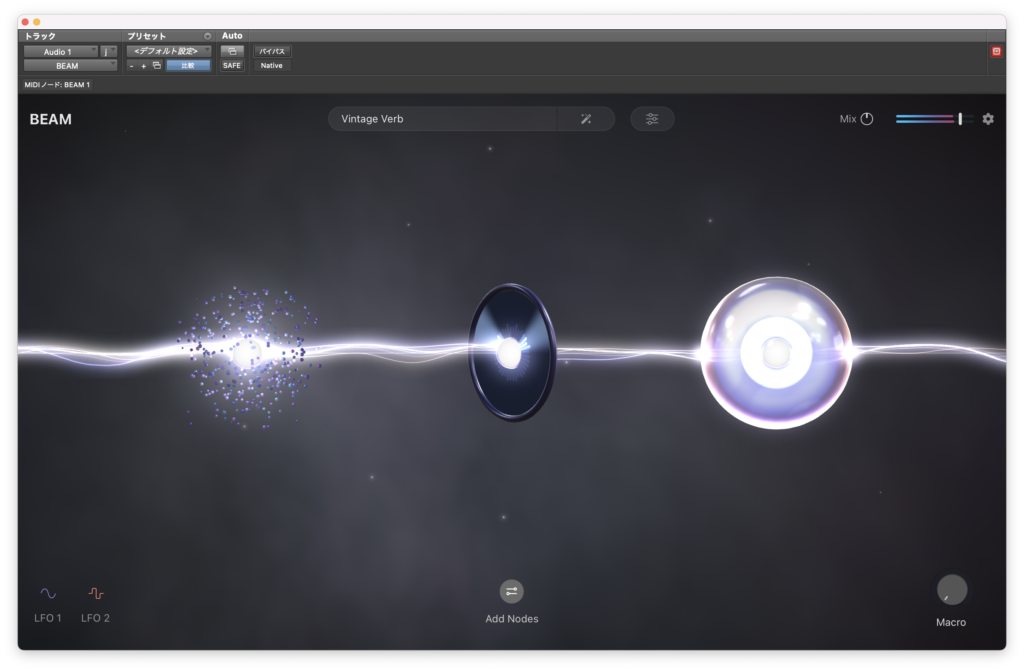
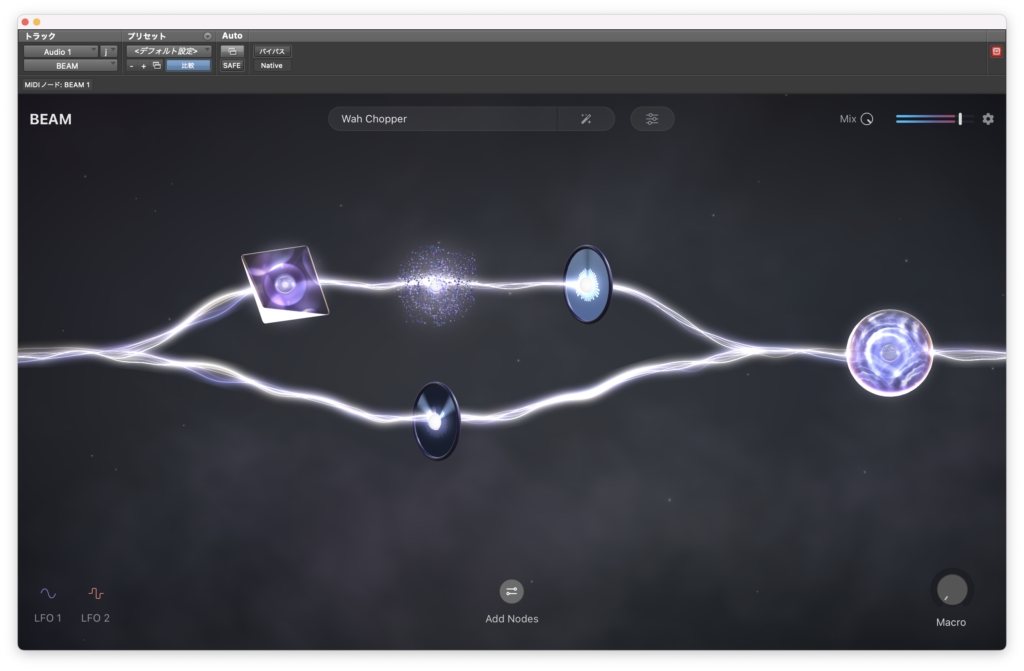
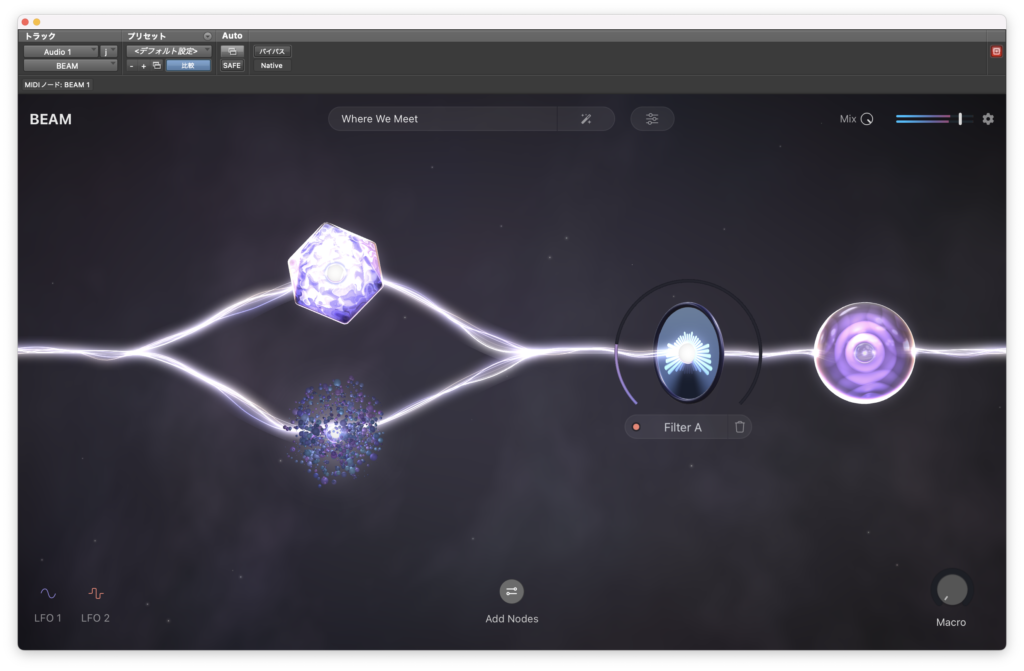
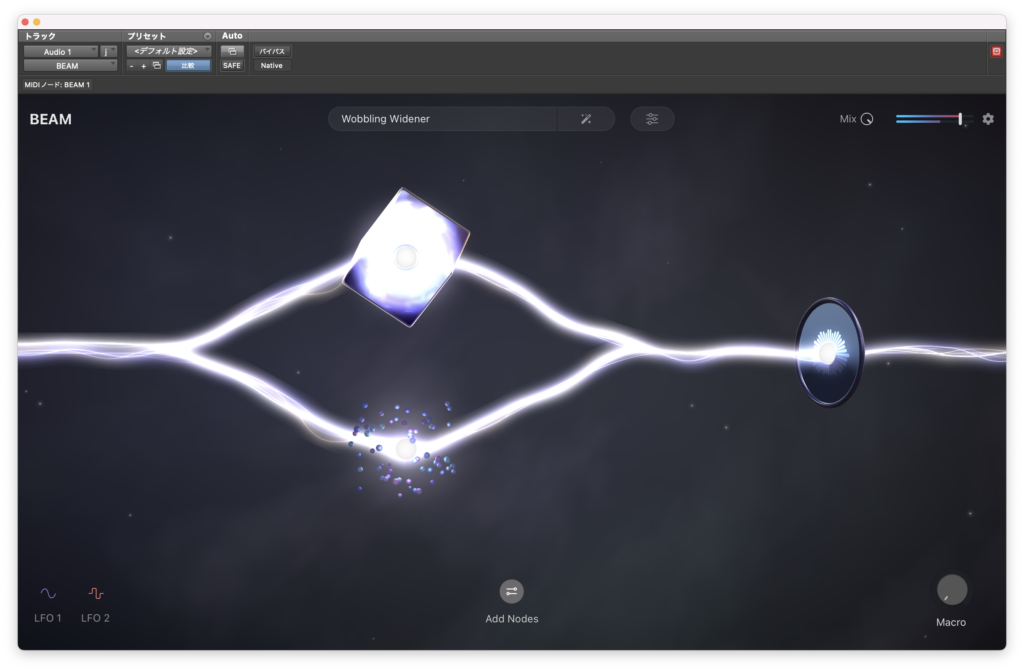
アコギ
アコギでも試してみます。まずバイパス↓
デフォルトだとこんな感じ↓
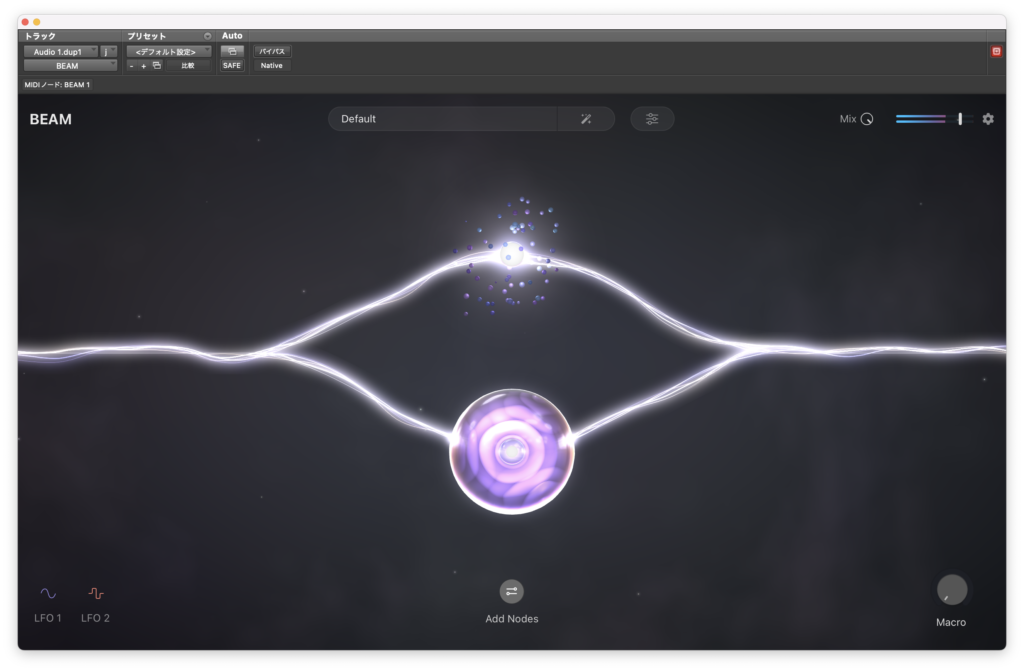
プリセットから試していきます。
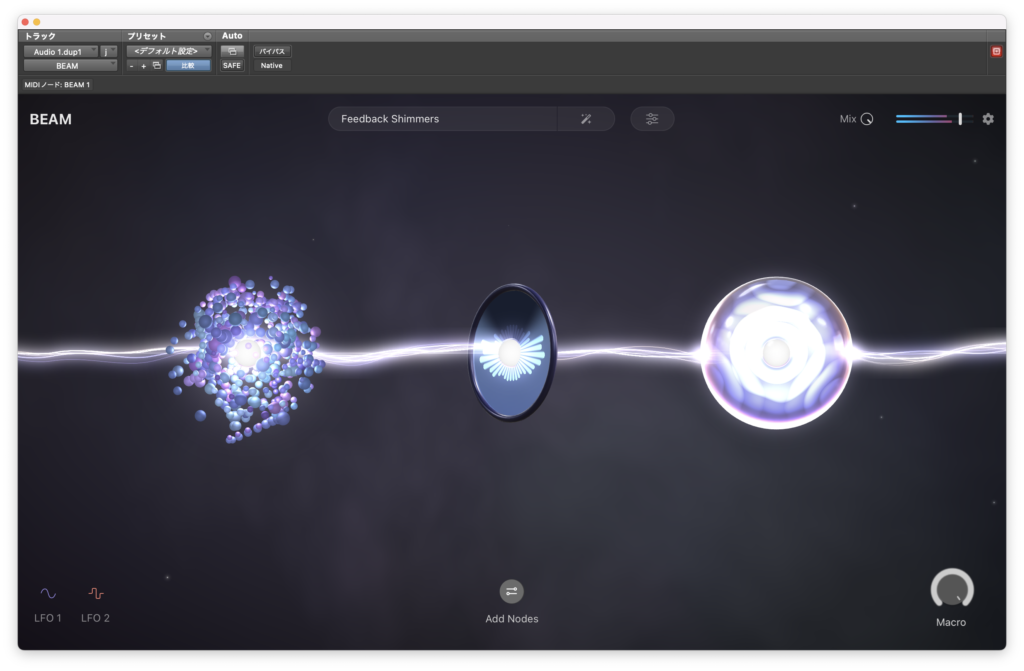
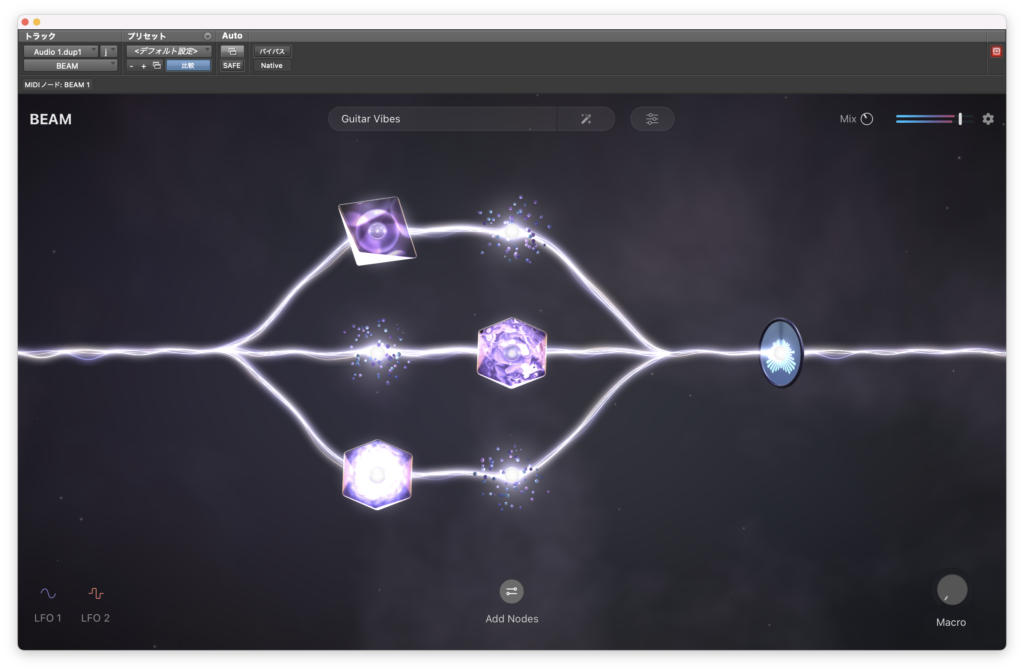
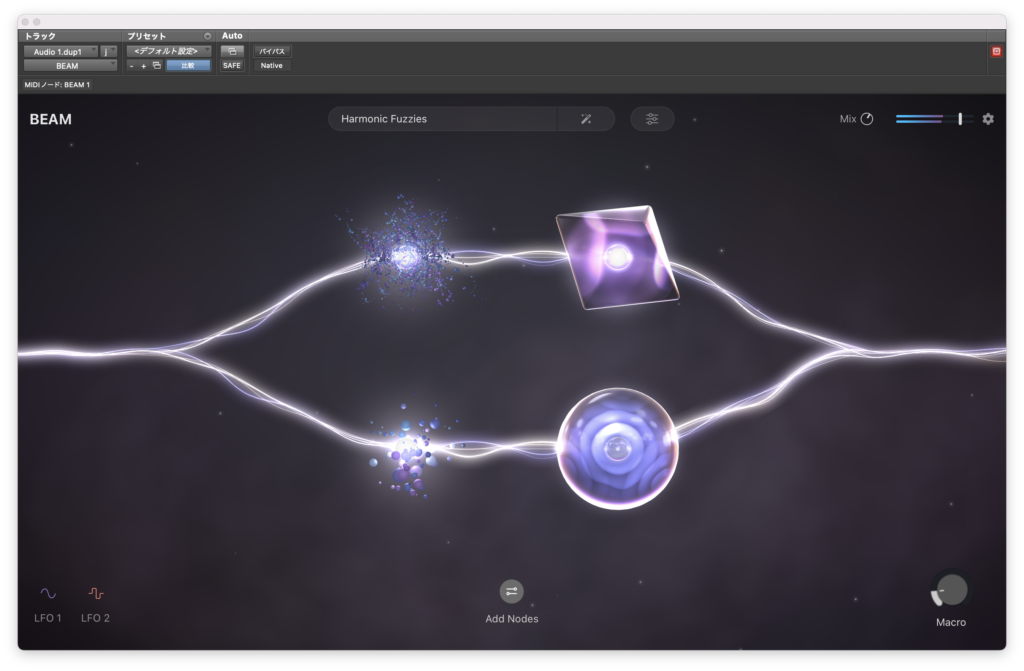
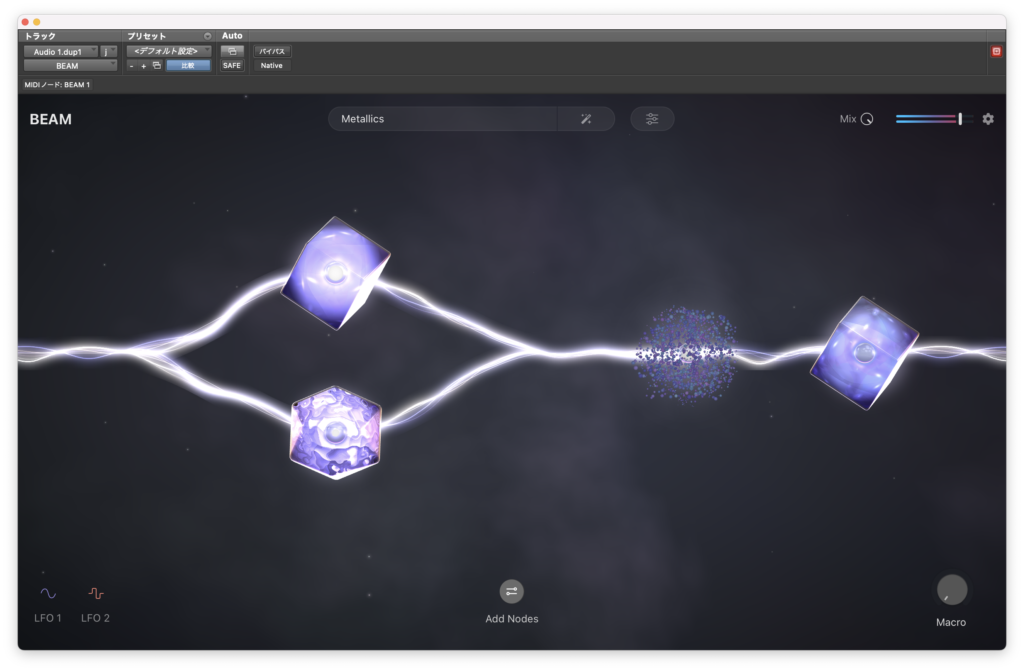
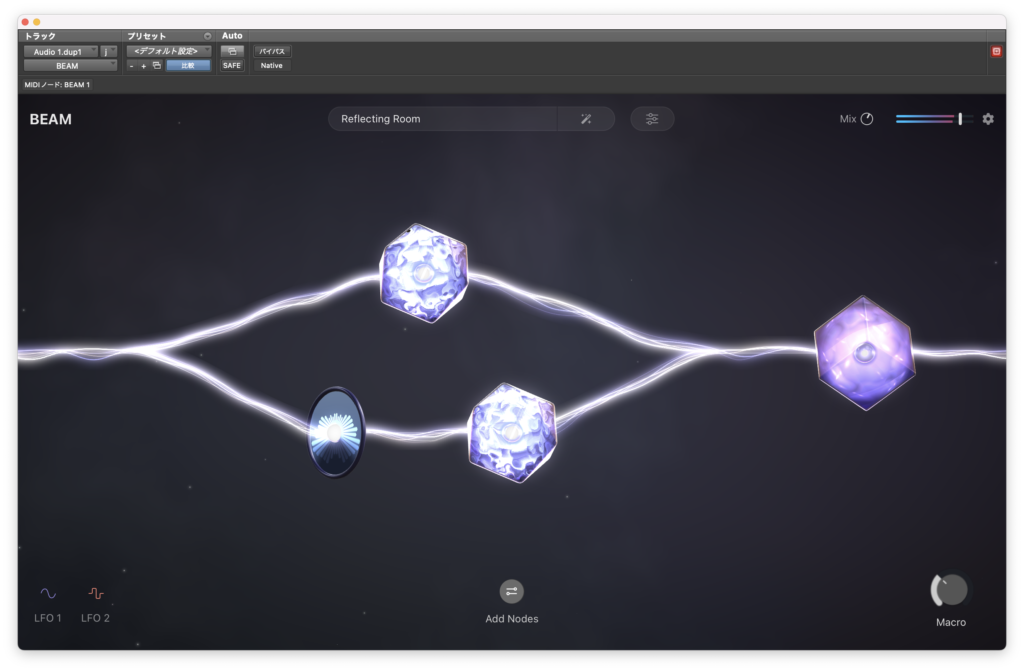
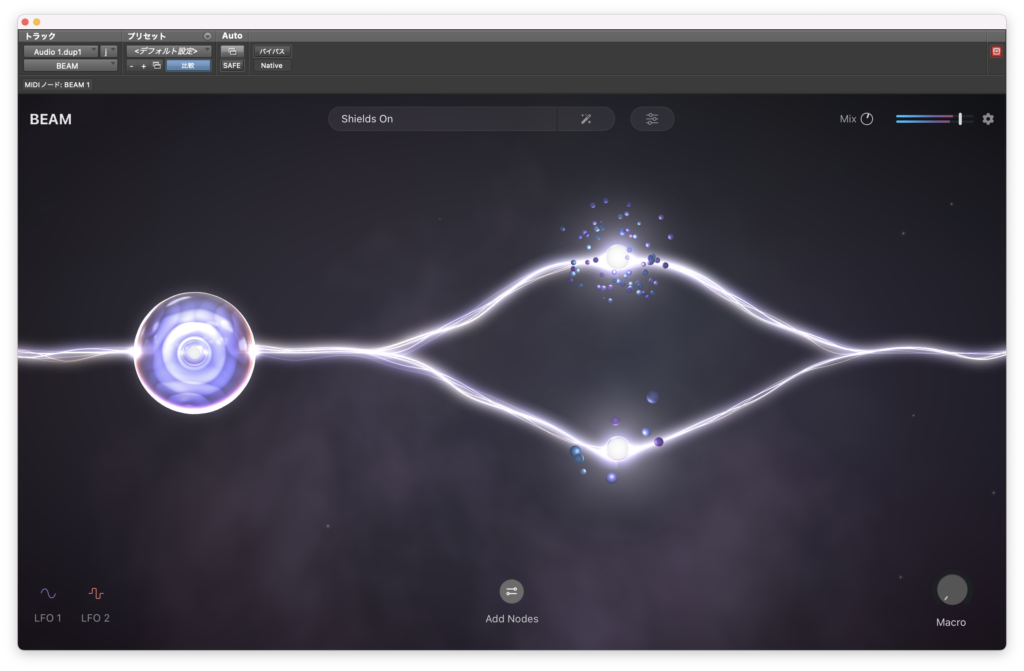
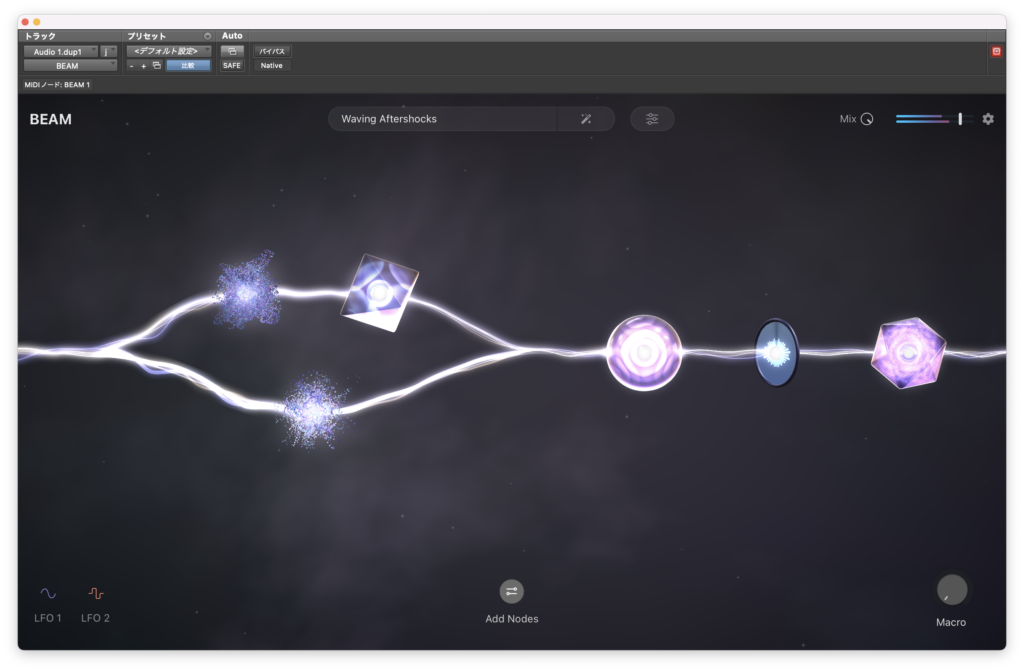
エレキギター
最後にエレキギターでも試してみます。まずバイパス↓
デフォルトだとこんな感じ↓
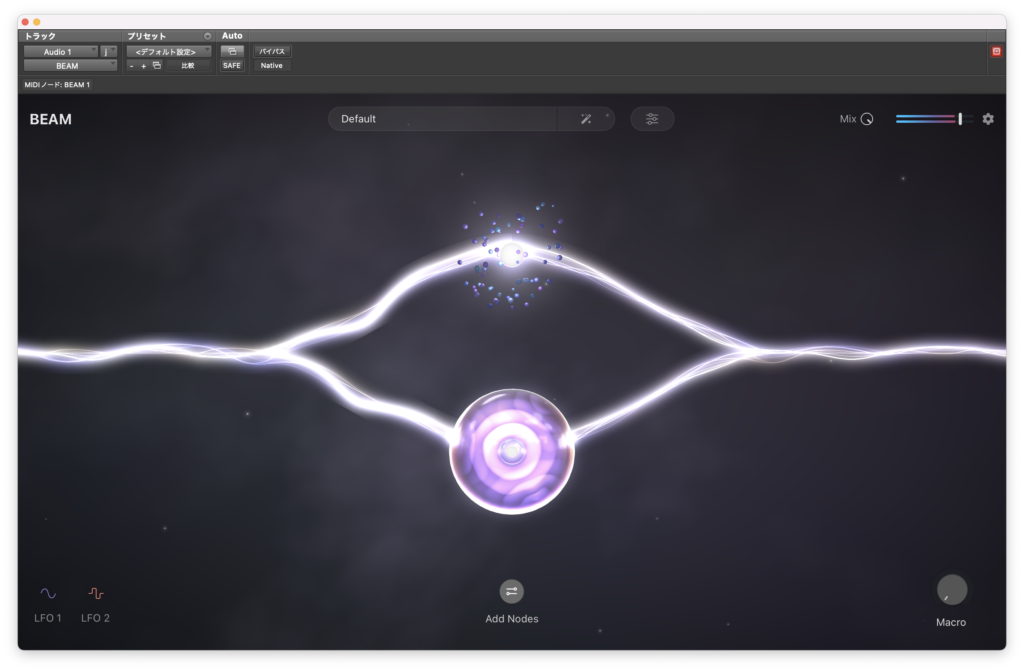
プリセットから試していきます。
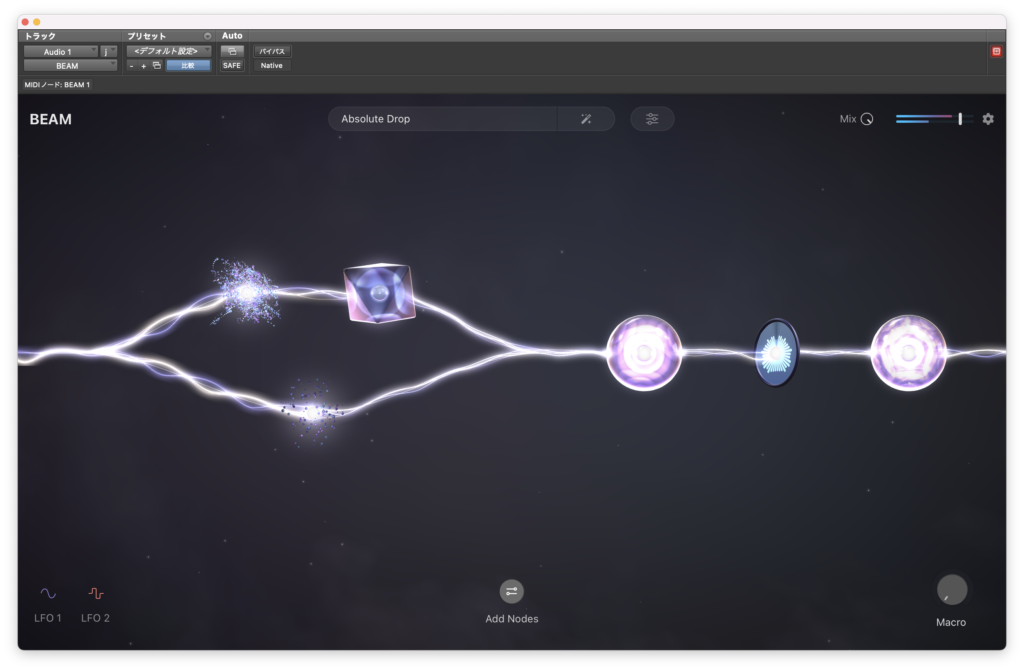
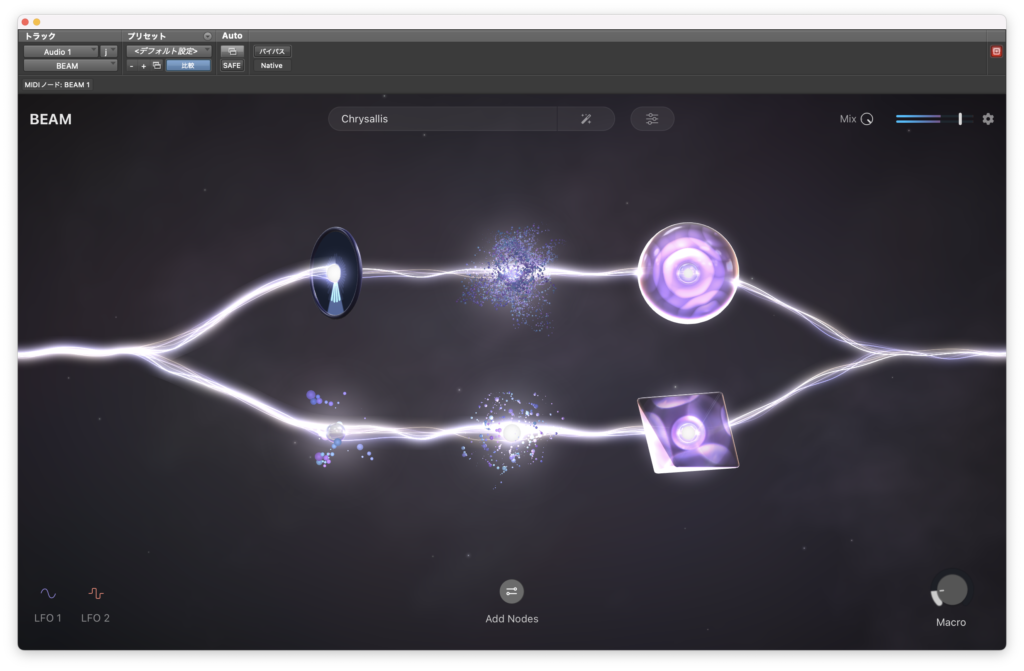
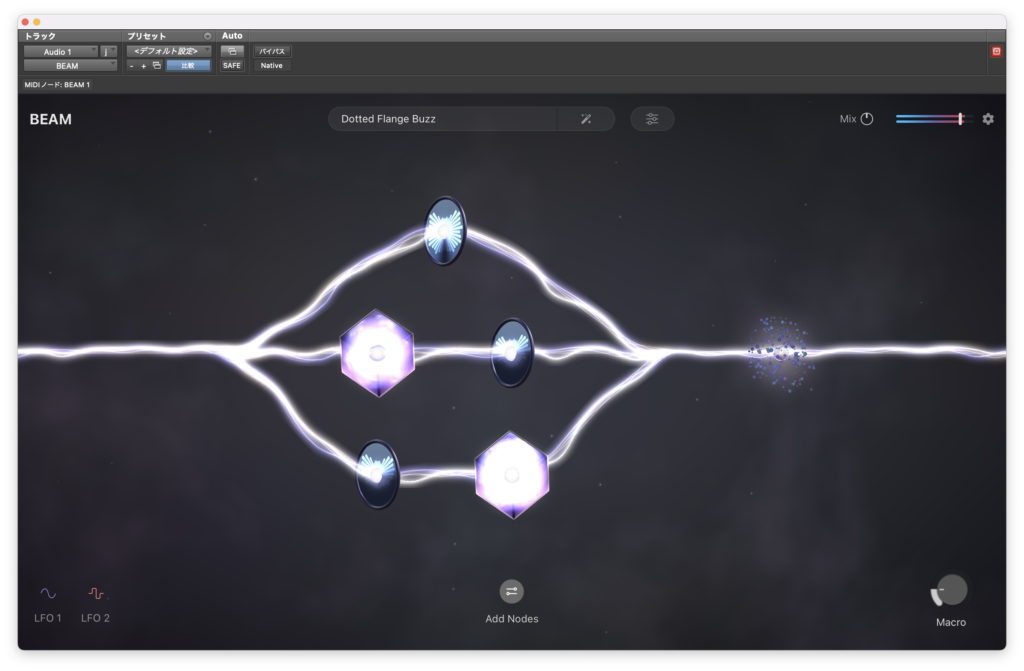
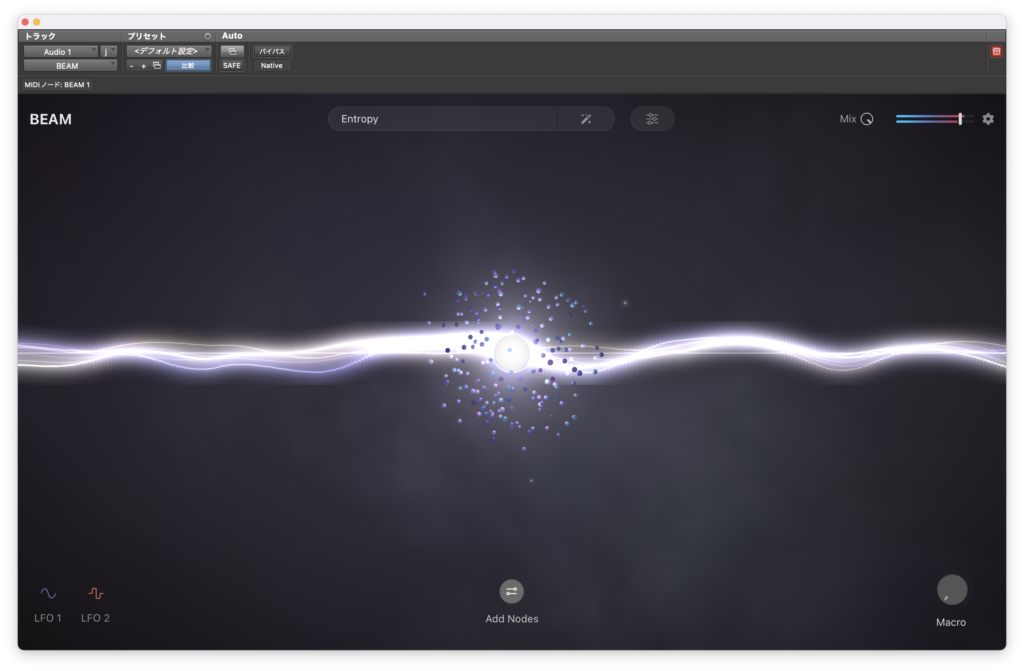
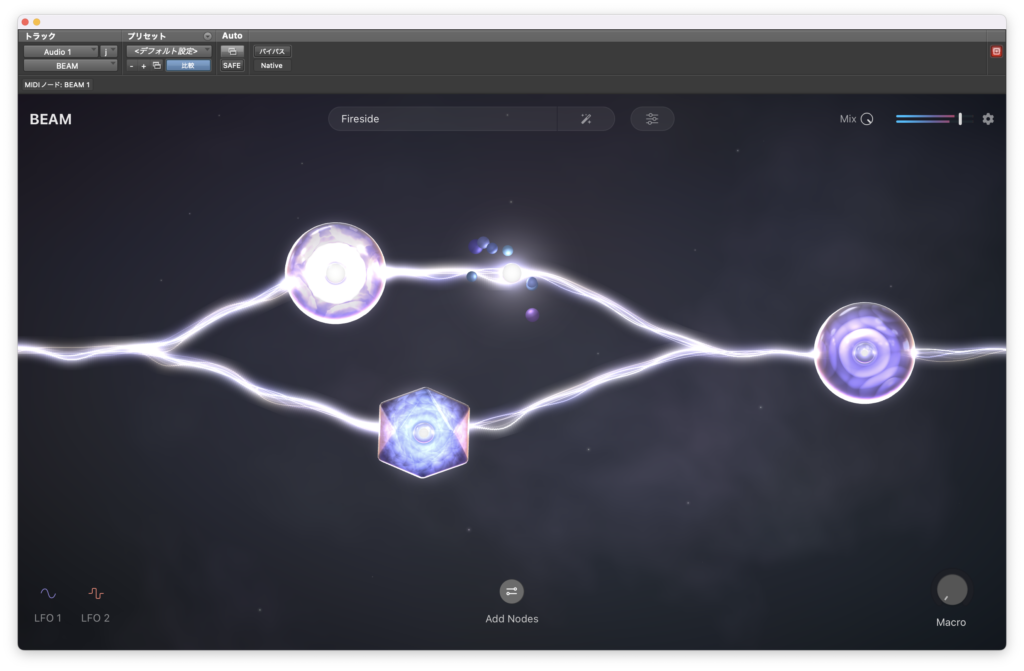
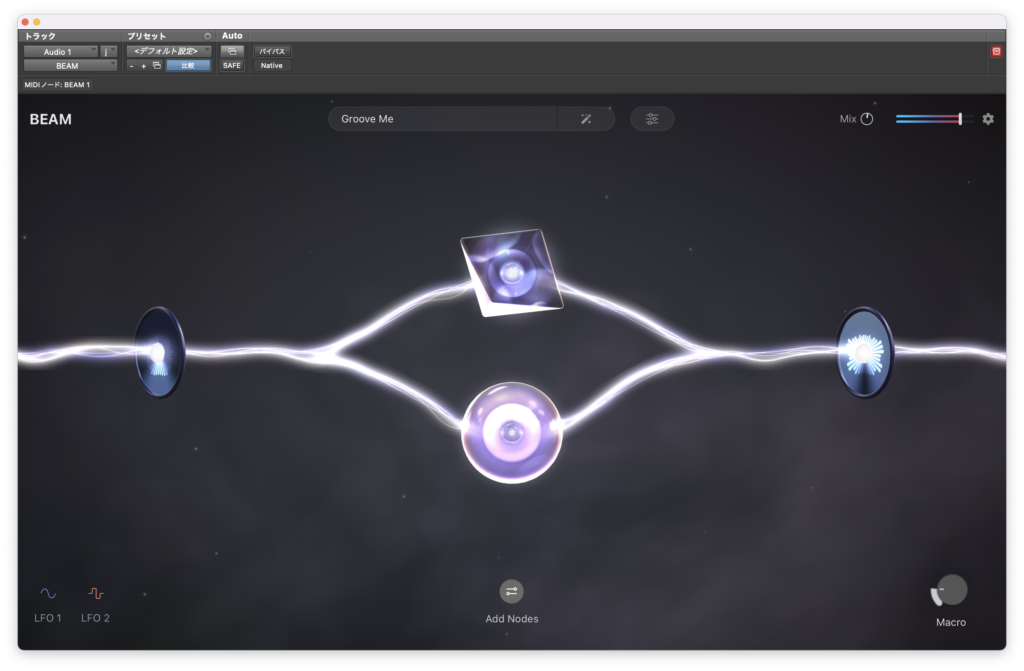
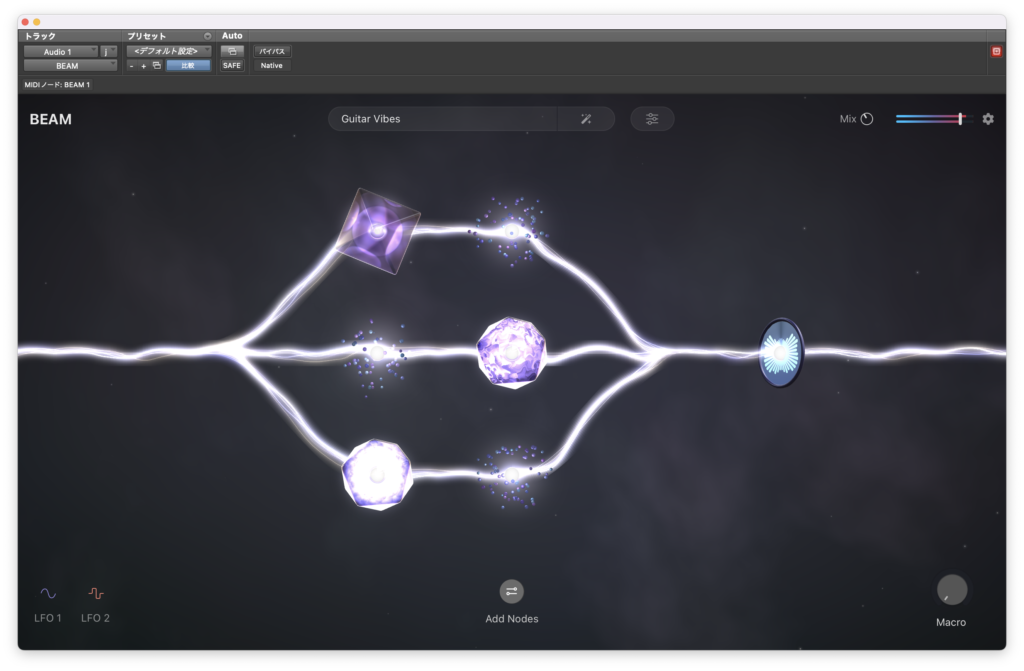
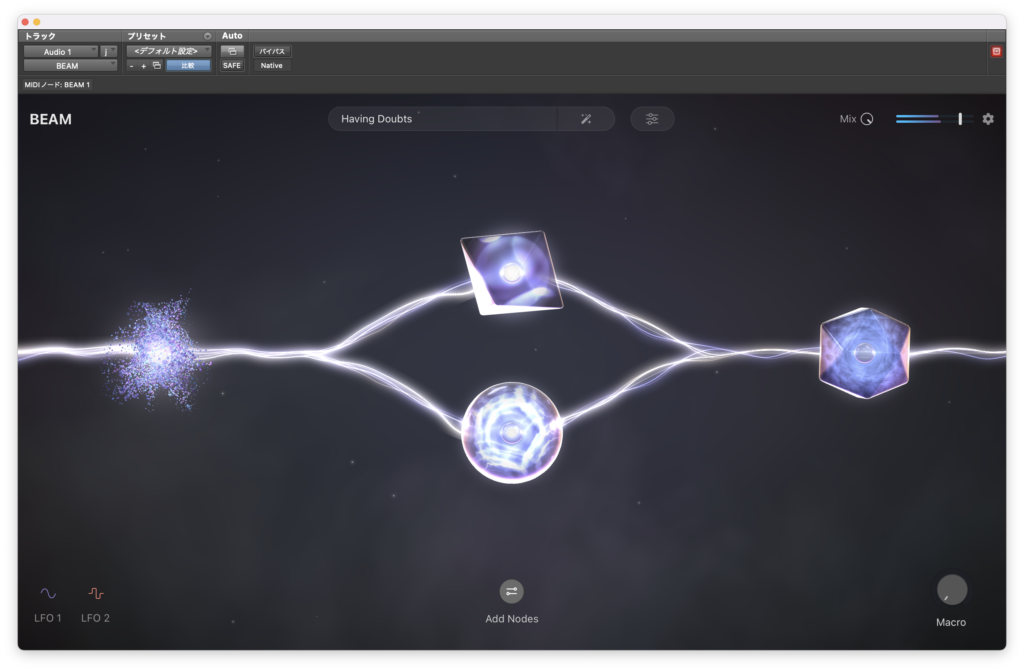
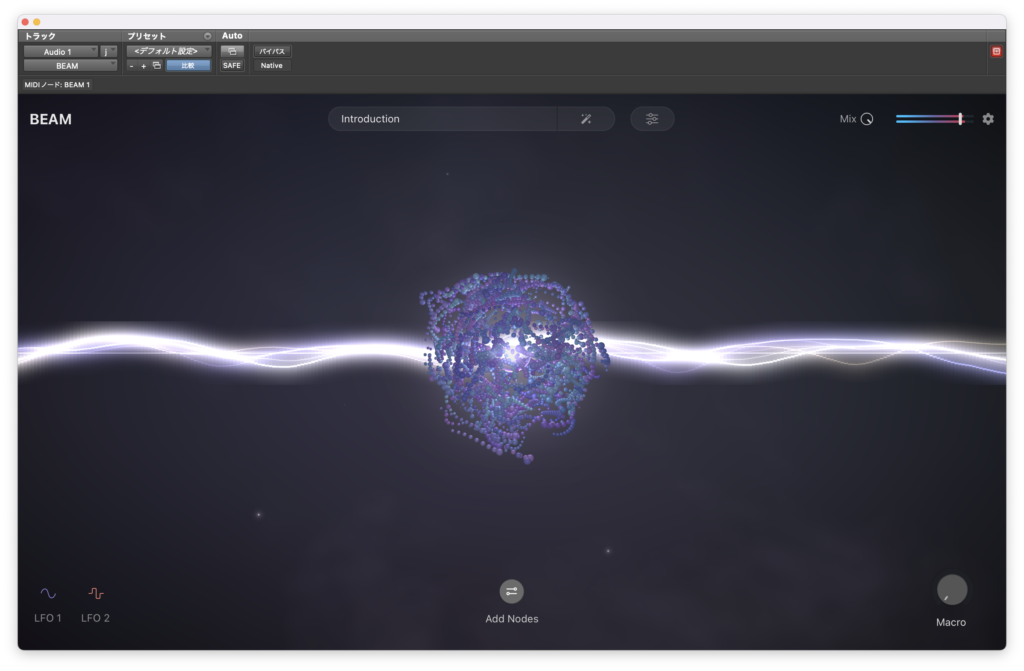
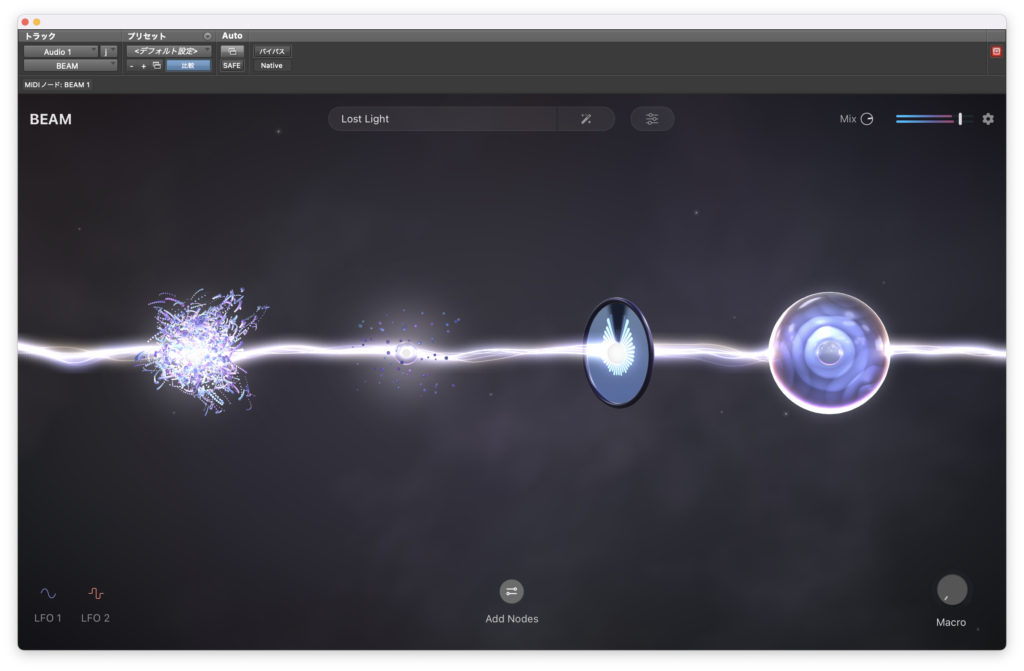
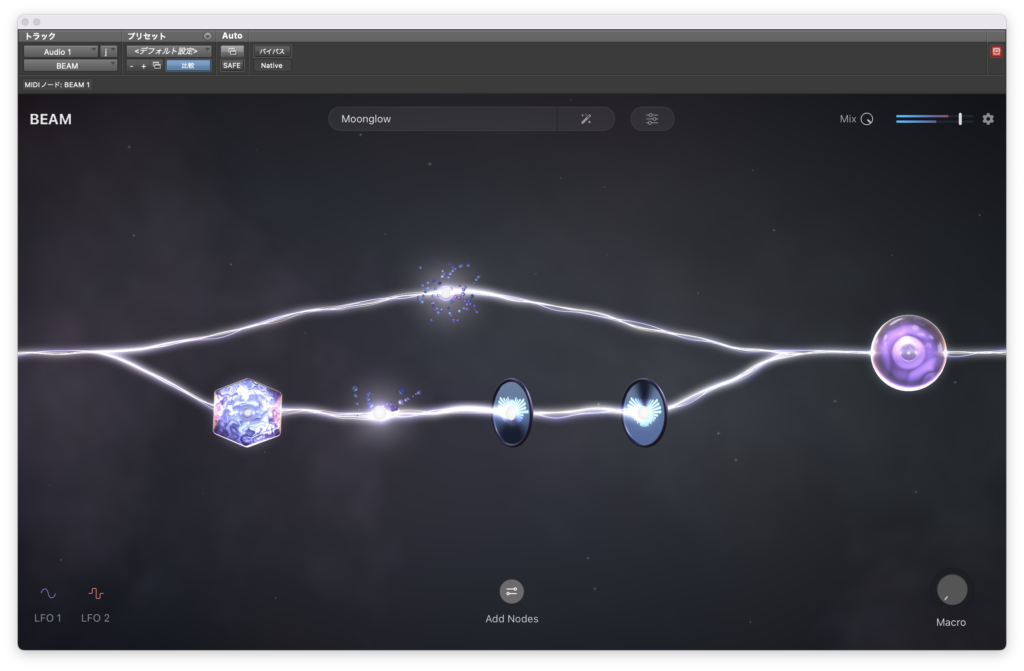
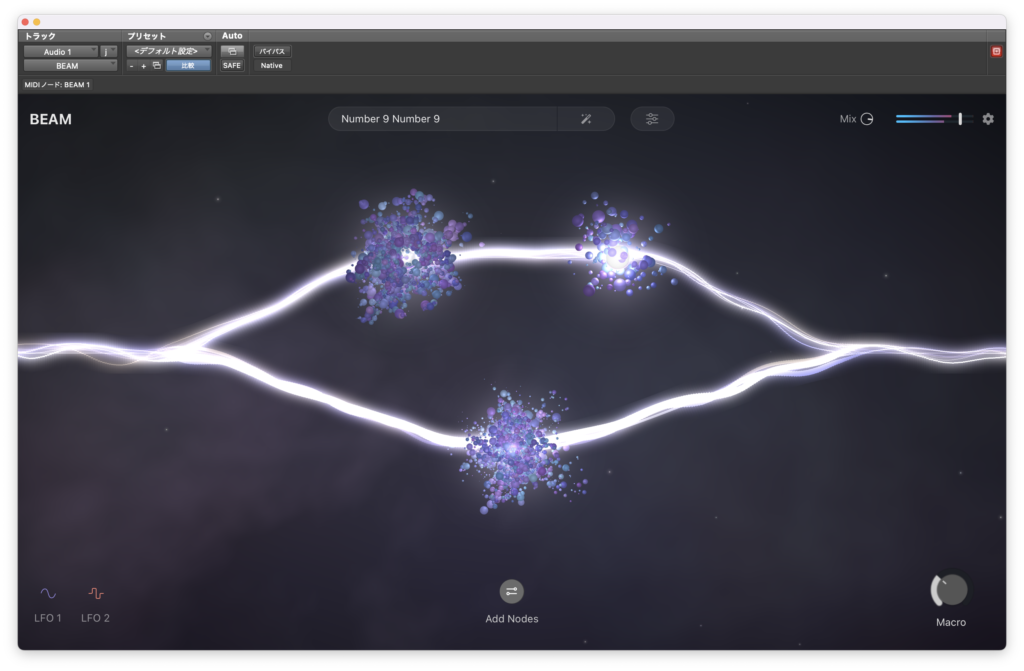
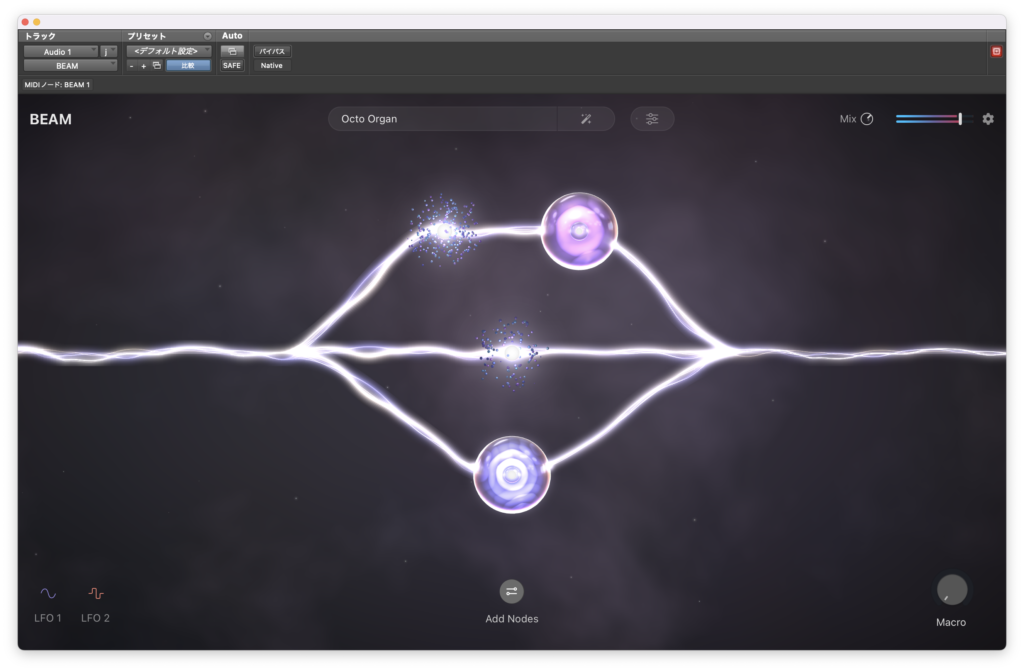
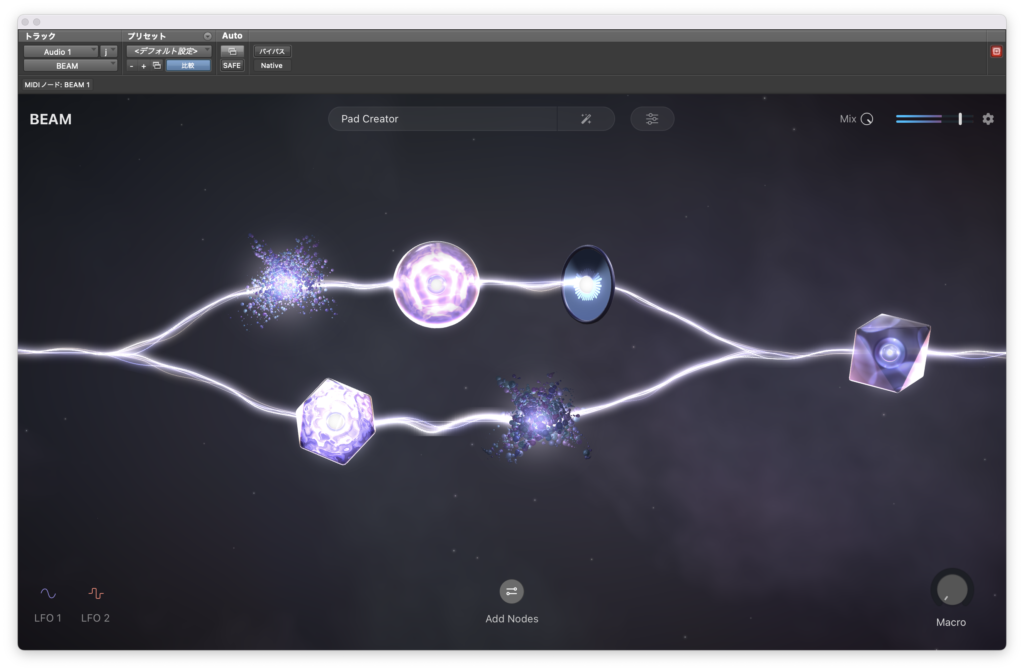
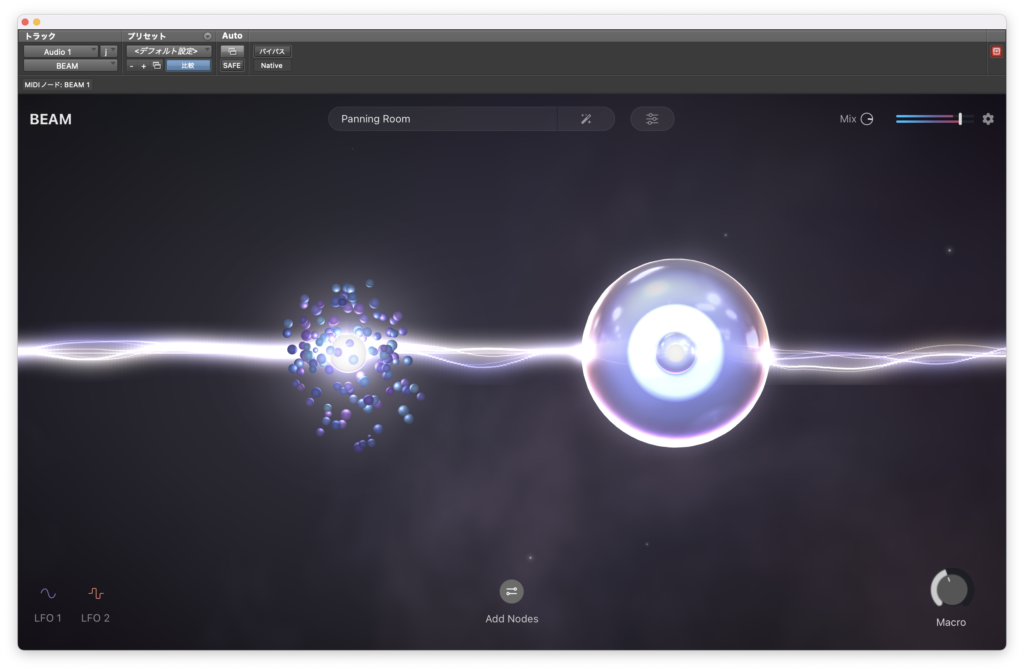
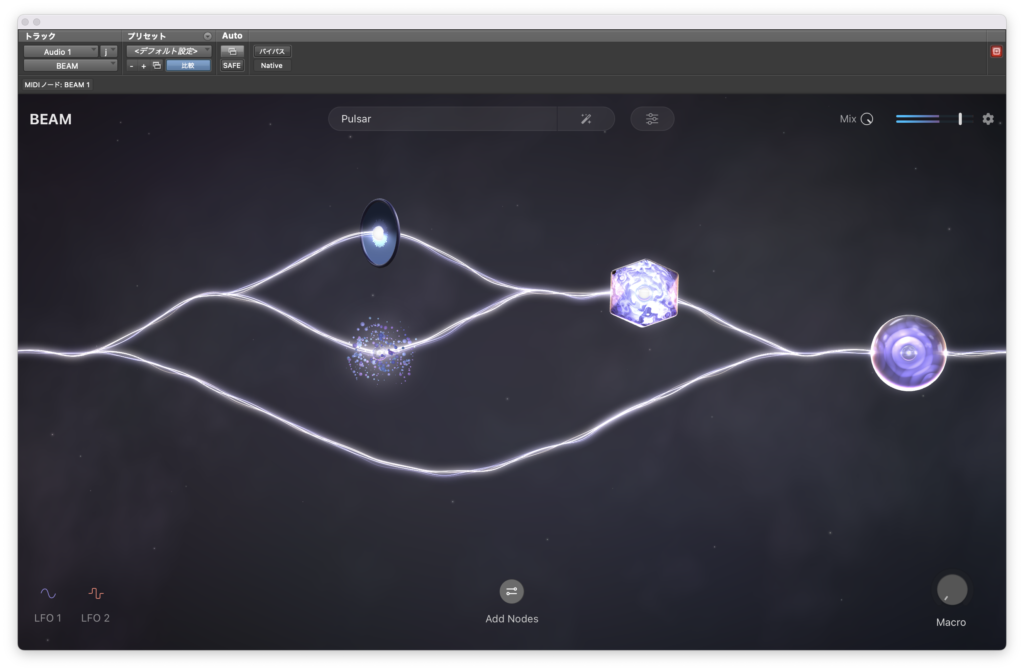
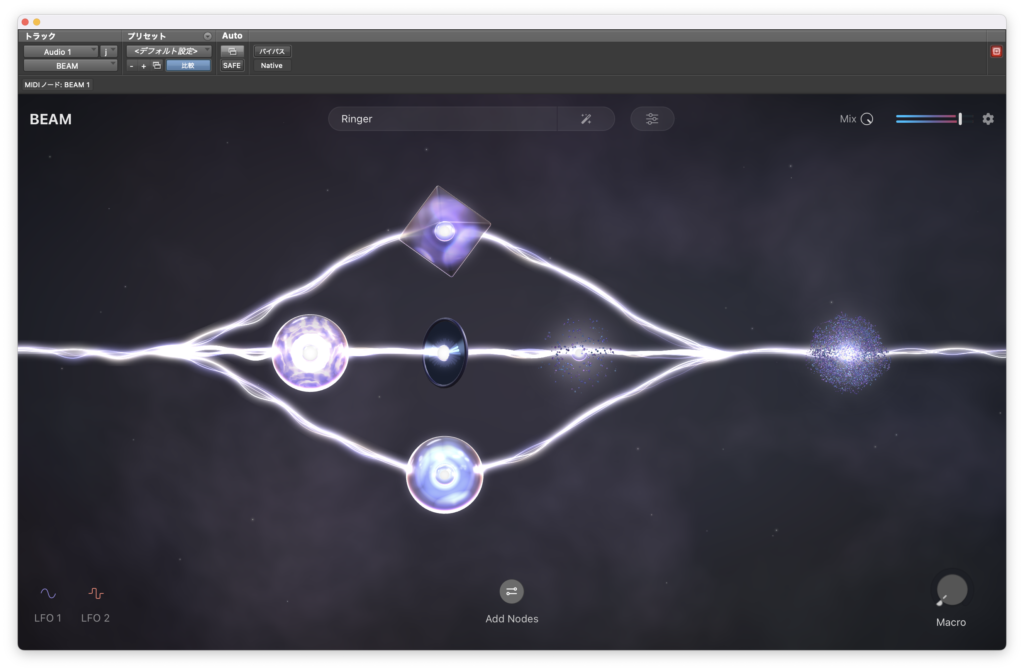
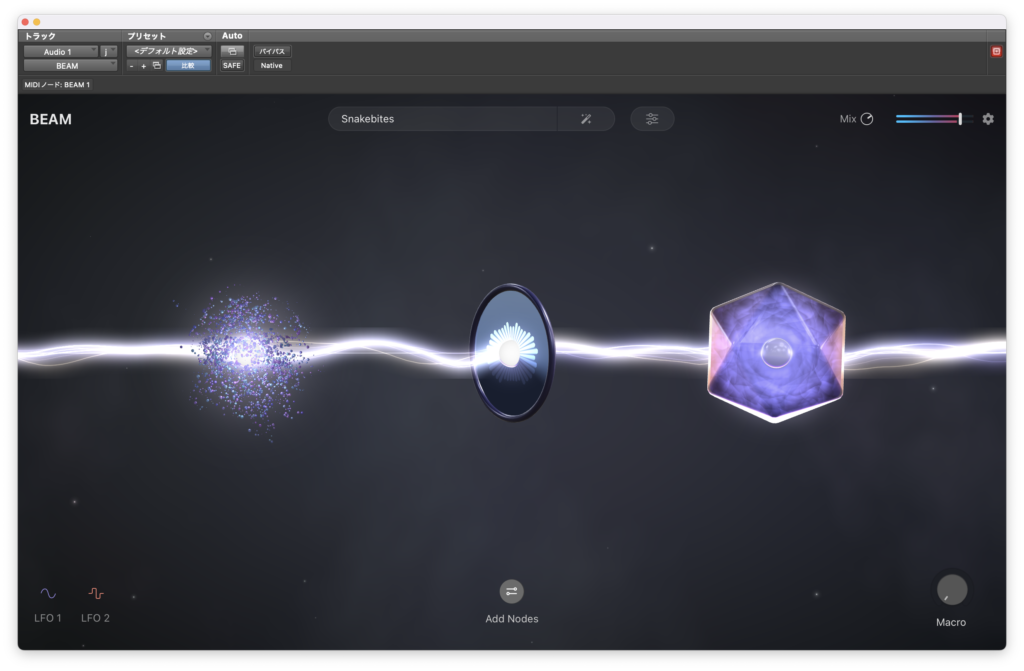
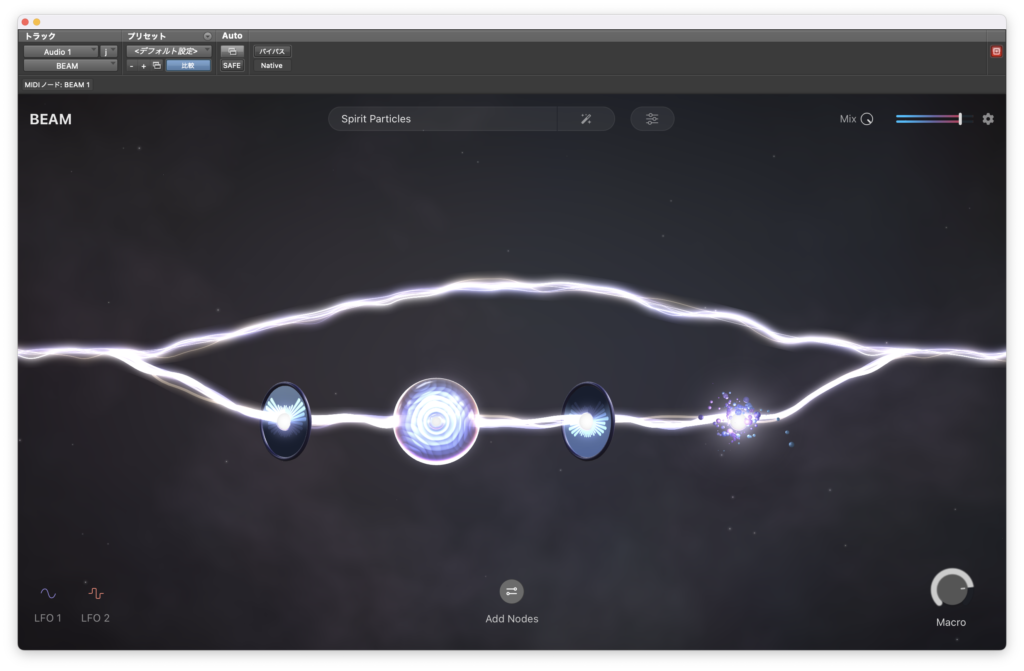
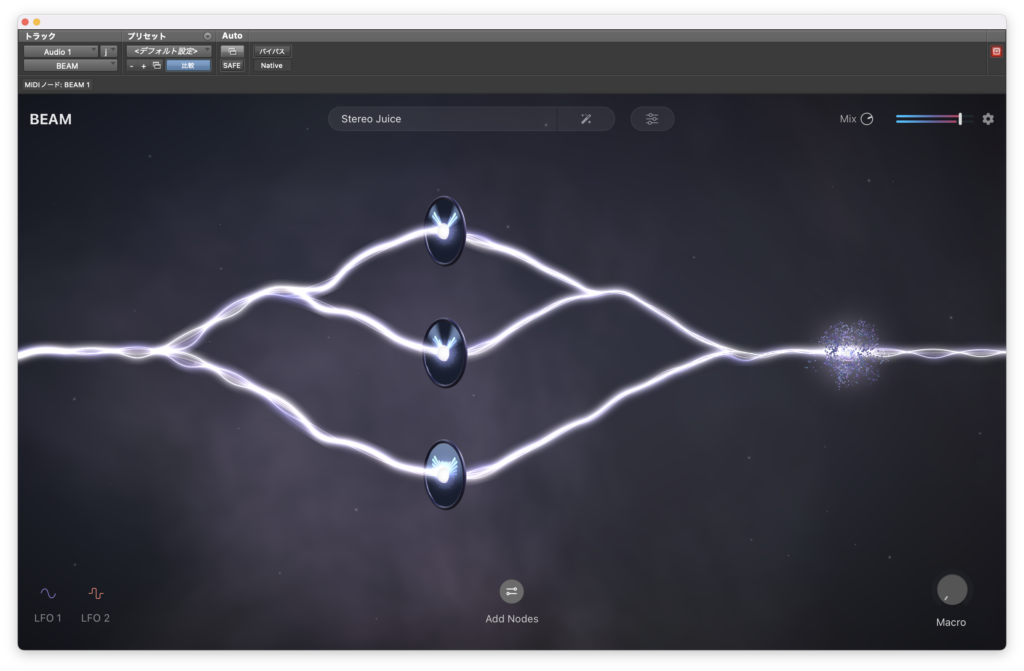
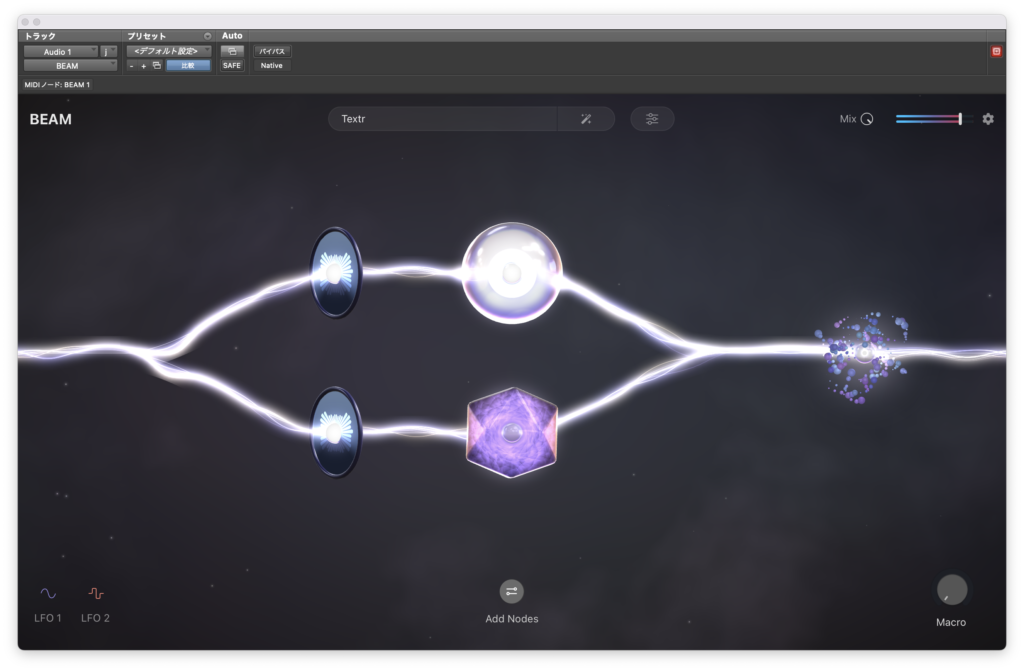
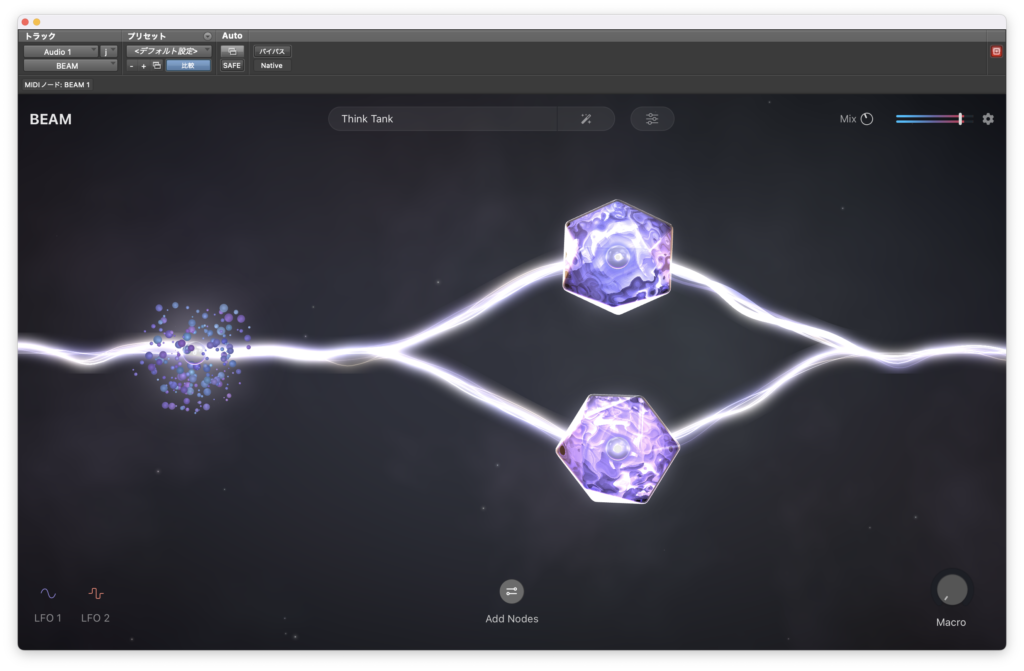
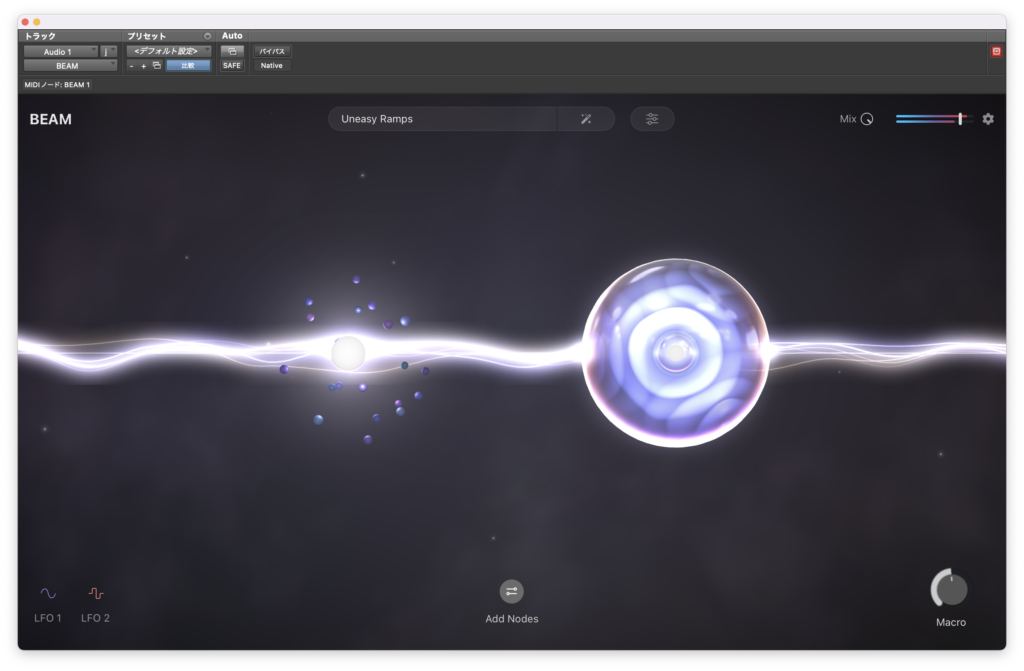
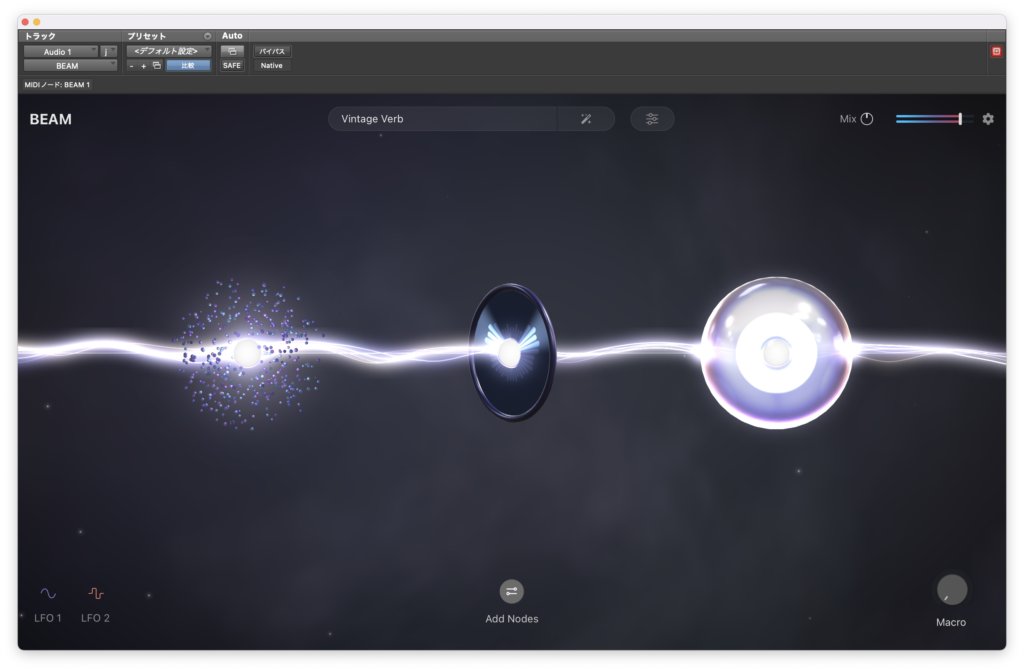
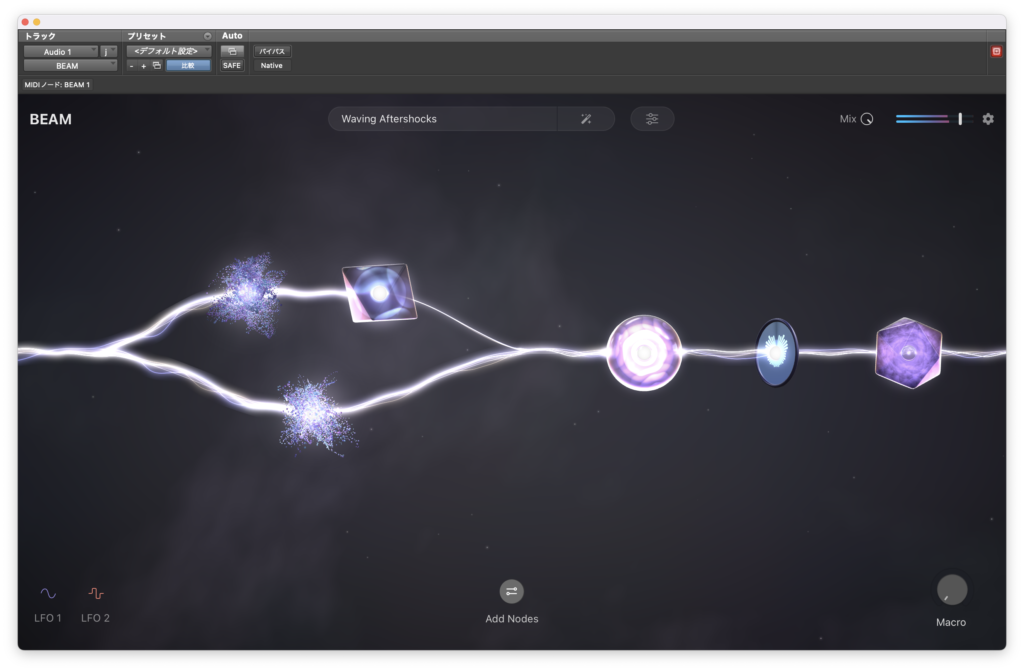
まとめ
かなり音作りの幅が広いプラグインですね。
発想次第で幻想的なディレイ/リバーブから強烈なエフェクト音までカバーできそうです。
ただ、UIの処理にパワーを持っていかれるのかやや負荷は重め。
ショップサイトはこちら↓
今月のプラグインセール情報をまとめてみました。
よかったら見ていってください。
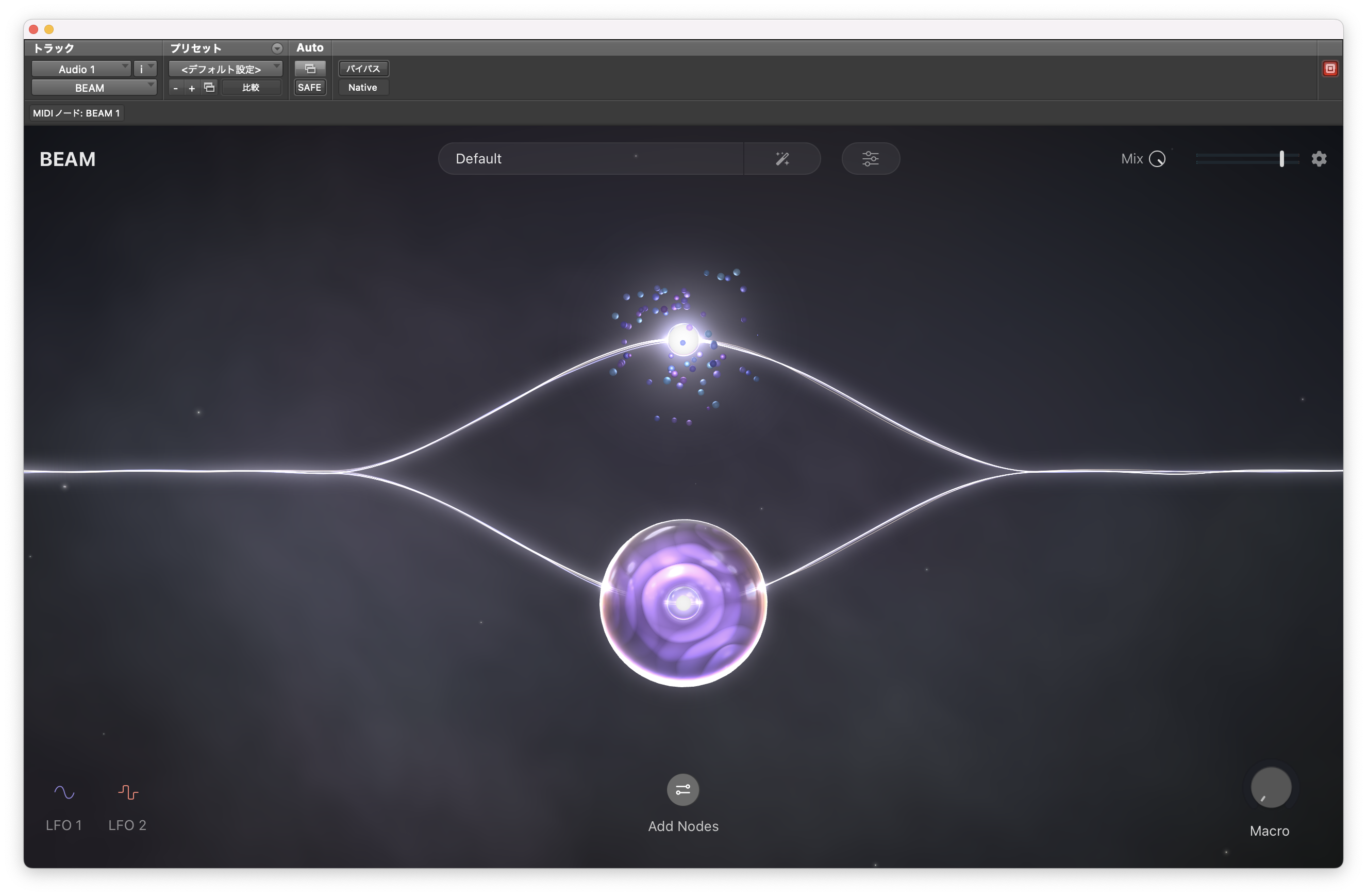


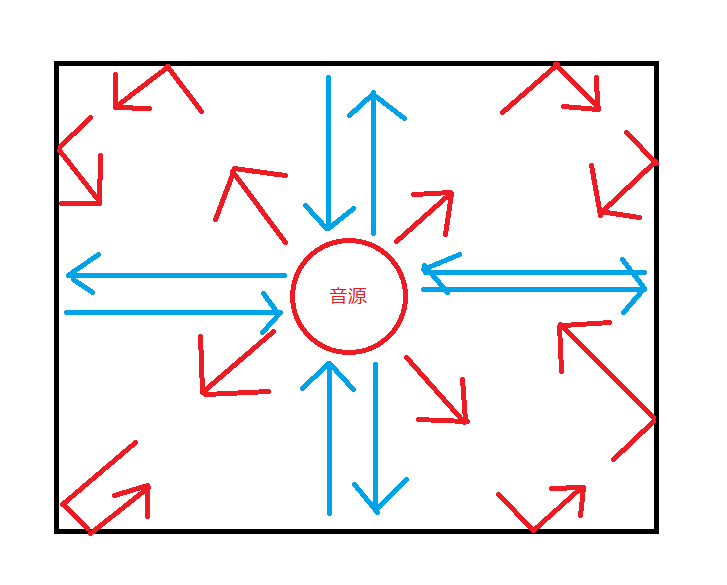




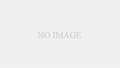



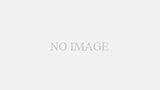

コメント